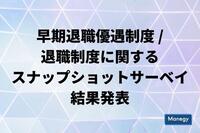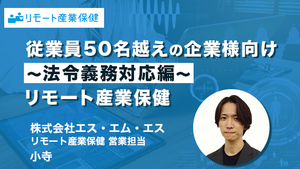公開日 /-create_datetime-/
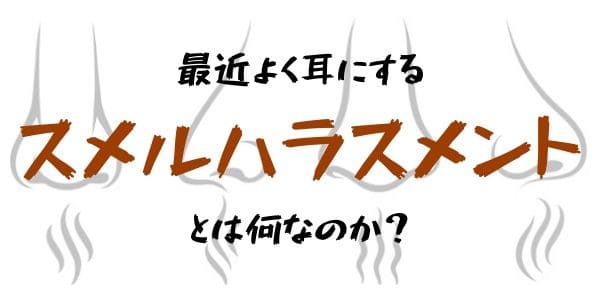
職場や学校などでのセクハラやパワハラが社会問題として注目されるようになってから久しいですが、最近ではこうしたハラスメント(嫌がらせ)の新種としてスメルハラスメント(スメハラ)も問題になっていることをご存知でしょうか?
今回はスメハラについて解説し、においの事例や企業が対応するにあたっての注意点なども併せてご紹介します。
スメルハラスメント(スメハラ)とは?
スメハラとはスメルハラスメントの略で、におい(スメル)によって周囲を不快にさせ、何らかの不利益を与えてしまうことを指します。
たとえば販売員の口臭が気になって購買意欲がそがれてしまったという経験はないでしょうか?
また、職場の同僚のきつい体臭が原因で、同じ場所に居続けるのがつらいといった例もあるでしょう。
上記の事例は、どちらもにおいによって他者に不快感を与えている点でスメハラのケースに該当します。
人は生きている限り呼吸し続けるので、においから完全に逃れることはできません。だからこそ、においが職場・他者に与える影響を考慮し、独自のスメハラ対策を講じる企業も増えています。
たとえば接客する機会が多い業種・職種では顧客との距離が近い分、におい対策に力を入れていることが多いです。
メガネの販売を手掛ける「オンデーズ」もそのうちの一社です。同社では従業員に、勤務中の禁煙を義務化したり、昼食後の歯磨きを徹底させたりするなど、においに関する規定を設けてスメハラ問題の発生を防ぐ対策を立てています。
スメハラとして報告される「におい」の種類
「においによる不快感」を訴えるケースは想像以上に多いですが、以下はスメハラの原因となるにおいの代表的な例です。
・汗のにおい
発汗は体温調節の役割を果たす一方、不快なにおいの原因になることがあります。特に気温が上がる梅雨から夏の時期は汗のにおいが気になり始める方も多いでしょう。
においを自覚している場合は制汗剤や拭き取りシートなどのケア用品を使用して対策を立てることができますが、本人に自覚がない場合はスメハラの状態が続いてしまいます。
・口臭
口臭もスメハラの原因の一つです。口臭は自覚していない人も多く、本人に気付かせることが難しいものです。口臭の原因は食事内容、虫歯や歯周病など口腔内の状況、消化器系の疾患など多岐にわたります。
小売業や営業職など、顧客と直接話をする機会が多い業務の従事者は、自覚がなくても適宜口臭のチェックをすることが望ましいでしょう。
・タバコのにおい
タバコのにおいは服や髪の毛に付着するため、喫煙者が喫煙所から離れたとしても周囲ににおいを発し続け、スメハラとなってしまうことがあります。
タバコのにおいを不快に感じる非喫煙者は非常に多いので、喫煙者は防臭・消臭対策を心掛けましょう。
タバコのにおいが残りがちな口腔内にはマウススプレーを使用し、においが染みついたスーツには毎日消臭スプレーを吹きかけるなどして各自でにおいケアを行うことをおすすめします。
上記以外には40代、50代から本格化する加齢臭もあります。
「いい香り」がスメハラになるケースも
スメハラの原因は汗やタバコといった、わかりやすい「不快なにおい」だけに限りません。
本来ならば人に好印象を与える香りであっても、使い方や使用量によっては周囲に迷惑をかけてしまうことがあります。
・香水や化粧品のにおい
濃厚な香りの香水や、化粧品に含まれる香料はスメハラの原因になります。
最近では男性でもおしゃれの一環として香水をつけていることがあり、加害者は女性だけではありません。
香水は控え目につける、もしくは職場ではつけないようにするなどして自分のお気に入りの香りが「香害」とならないよう注意しましょう。
化粧品のにおいを指摘されたことがある場合は、無香料の化粧品を選ぶことで解決できます。
・柔軟剤の強い香りも原因に
香りづけ機能がある柔軟剤が人気を博しているのと同時に、この柔軟剤のにおいに悩まされている人が急増しているのをご存知でしょうか?
いい香りにしたい、との思いから柔軟剤を多めに使用すると、つけ過ぎの香水と同様に「香害」となる可能性があります。職場で着用する予定の服には使用を控える、使用量を控え目にするなどして「他者の嗅覚」に配慮したいものです。
職場でできるスメハラ対策は?
スメハラはにおいの元となっている人が自ら対処しなければ解決しませんが、本人にどのように対処を促すかについては、人格の否定につながらないようにしなければなりません。
職場でスメハラ対策を行う場合は以下の点に注意して実施しましょう。
・職場全体の問題として注意喚起する
個人を名指しで批判・注意することは避け、従業員全員が守るべきマナーとして、具体的なにおい対策を掲げましょう。たとえば「帰社後は汗を拭くなどして身だしなみに注意しましょう」「強い香りが苦手なお客様にご迷惑がかからないよう、香水は控え目に」などです。
・スメハラ被害の報告を受け付ける窓口を用意する
においの元となっている本人に直接注意することは人間関係のトラブルに発展しやすく、また、言い方によっては人格の否定になりかねません。
スメハラを含めた各種ハラスメントを報告する窓口を設ければ、加害者と被害者が直接対立せず、第三者を含めた解決策の模索が可能になります。
まとめ
スメハラへの対処は個人のプライベートや体質に踏み込んでしまいがちですが、だからこそ、個人への批判となってしまう事態は避けたいものです。
部署の責任者や管理部門の担当者は「誰でもスメハラの加害者になりうる」という認識を前提に、スメハラを「職場全体の問題」と捉えながら対応する姿勢を忘れないようにしましょう。

その他のハラスメントに関して詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
関連記事:改めて気を付けて!アルハラ
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -
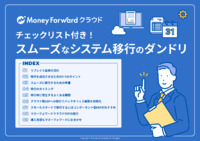
チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ
おすすめ資料 -
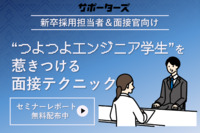
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -
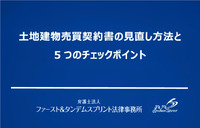
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -
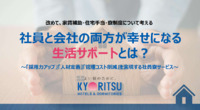
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

電子署名の適法性 ~日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性~
おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース