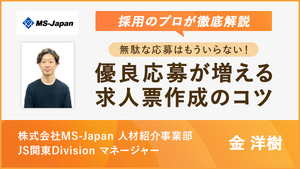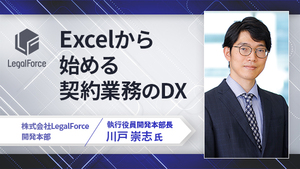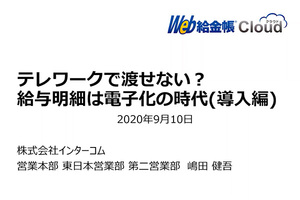公開日 /-create_datetime-/

領収書や契約書を作成される方は必ず目にする「収入印紙」。この収入印紙は何のために必要なのか?収入印紙はどんな時に必要で、購入金額はいくらになるのか?電子契約等ではどのような取り扱いになるのか?といったことについて解説していきます。
目次【本記事の内容】
ギフト券5000円分が貰える!
管理部門の情報収集キャンペーンのお知らせ
収入印紙とは、「国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票」です。納付者があらかじめ、納付金額分の収入印紙を購入しておき、文書に貼付することで、手数料や罰金、税金の支払いが完了する仕組みとなっています。現在は、主に「印紙税」の支払いのために使用されます。
実は、「収入印紙を貼る」行為は、「税金を納付する」ことなのです。法人税や消費税、個人所得税などと違い、税金として表舞台に立つ機会が少ないため認知度が低いですが、印紙税は立派な税金のひとつです。国税局の「印紙税の手引」によれば、
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となります。課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもあります。
(出典: 国税庁)
と説明されています。よく領収書に収入印紙を貼り付けるシーンを見かけますが、このように印紙税は私たちの生活にも深くかかわる税金なのです。
ちなみに少しだけ経理の話に触れておくと、収入印紙を使った時の勘定科目は「租税公課」になります。収入印紙を買い置きしておくような場合は「貯蔵品」を使います。
印紙税とは
前の章でも確認したように、印紙税とは「経済取引に伴って利用される契約書などにかかってくる税金」です。具体的にはどのような書類に印紙税がかかってくるのでしょうか。「印紙税の手引」より、印紙税の対象になる書面の一覧は以下のようになります。
- 不動産等の譲渡、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書(第1号文書)
- 請負に関する契約書(第2号文書)
- 約束手形又は為替手形(第3号文書)
- 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券(第4号文書)
- 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書(第5号文書)
- 定款(第6号文書)
- 継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
- 預貯金証書(第8号文書)
- 倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券(第9号文書)
- 保険証券(第10号文書)
- 信用状(第11号文書)
- 信託行為に関する契約書(第12号文書)
- 債務の保証に関する契約書(第13号文書)
- 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書)
- 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書(第15号文書)
- 配当金領収証又は配当金振込通知書(第16号文書)
- 金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)
- 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 (第18号文書)
- 第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳(第19号文書)
- 判取帳(第20号文書)
(出典: 国税庁)
例えば第2号文書の「請負に関する契約書」などはよく見かけるかもしれません。請負人が納品物を完成させ、注文者がそれに応じて報酬を払うという契約です。
また第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」も重要です。売買取引に関する契約書などがこれに当たります。
収入印紙はどこで買える?購入できる場所
今まで印紙税の対象になる文書を確認してきました。それではこの文書に貼り付ける収入印紙はいったいどこで買うことができるのでしょうか?収入印紙の購入場所について少しだけ見ていきます。
収入印紙というと重々しい印象を受けるかもしれませんが、意外と簡単に購入することができます。市役所や郵便局ではもちろん、一部のコンビニエンスストアでも購入できます。
納税が必要な文書に、収入印紙金額に見合う量を貼り付け、消印を押すことによって準備が整います。
小売店などでレシートに収入印紙をくっつけて、それに消印をする光景を見たことがある人は多いかもしれません。この消印が極めて重要で、これを押印することによって初めて納税が可能になります。収入印紙の交換は郵便局で行うことができます。(手数料1枚5円)
収入印紙が必要な書類と貼るべき金額の決定方法に関して
収入印紙が必要な書類には、契約書、領収書の他に、約束手形や為替手形、株券、定款、船荷証券、信用状、通帳などがあります。
納税額が定額なものには、定款や船荷証券、信用状などがあり、不動産売買契約書や、請負に関する契約書、売上代金の領収書などは、課税文書に記載のある金額によって納税額が決まります。
国税庁から出ている「契約書や領収書と印紙税」には、印紙税額の情報が載っています。文書の番号や契約金額によって印紙税額は変わってきます。印紙税額の一覧表の文書別に、必要な印紙税額の例を見てみましょう。なお、記載金額や契約金額は消費税を含みません。
金額計算例①:不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書
課税文書:特許権の譲渡に関する契約書
譲渡金額:6千万円であった場合
上記の場合、契約者は6万円の印紙税を課税されます。
金額計算例②:請負に関する契約書
課税文書:映画俳優の専属契約書
契約金額:2億円
上記の場合、契約者は10万円の印紙税を課税されます。
金額計算例③:定款
課税文書:株式会社などを設立する際の定款(原本のみ)
記載金額:なし
上記の場合、定款を作成した会社は4万円の印紙税を課税されます。
金額計算例④:継続的取引の基本となる契約書
課税文書:売買取引基本契約書
特定の記載金額:なし
上記の場合、契約者は4千円の印紙税を課税されます。
金額計算例⑤:売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
課税文書:製品売上に対して発行した領収書
記載金額:7千万円
上記の場合、売主は2万円の印紙税を課税されます。
金額計算例⑥:売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
課税文書:借入金の領収書
記載金額:5万円
上記の場合、領収書を発行した会社は200円の印紙税を課税されます。
収入印紙の貼り方と負担は誰がするのか?
次に見ていきたいのは「収入印紙の貼り方と負担」についてです。収入印紙を貼るという作業の中で特に重要なのが、「消印をしっかりする」作業です。前の章でも触れましたが、消印をしなければ収入印紙が無効になってしまいます。
まず印紙税の負担についてですが、領収書ならば金銭を受け取った側(つまり小売などであれば小売店側)が負担するのが通常です。また当事者同士で作成した契約書であれば、両者で折半するのが一般的です。
例えば売上金額が5万円を超える場合、領収書に収入印紙を貼らなければなりません(2020年6月時点)。小売店側が用意した収入印紙を領収書に貼り、消印を押印します。これは収入印紙を再利用されないためのものなので、消印以外の場合はすべて無効になってしまいます。
次に契約書の場合です。契約書の左上に収入印紙を貼るのが一般的ですが、特に取り決めのようなものもないので、双方で添付個所を相談することもできます。領収書と同じく必ず消印をし、収入印紙を再利用できないようにしておきます。
収入印紙を貼らない事で起こるペナルティ
次に収入印紙を貼らないことで起こるペナルティについて見ていきます。収入印紙はこれまで説明してきたとおり、収入印紙を課税文書に貼って消印をすることで、税金を納付するものです。つまり、収入印紙をきちんと規則に沿って貼付・消印しなければ、脱税とみなされることになります。税金を払っていないので、当然罰則がついて回ることになります。納税漏れが見つかった場合にはいくらかの過怠税を要求されることになり、油断していると多くのお金を支払わなければいけなくなります。
過怠税は3倍の印紙税額に!
税務調査などで、納税漏れが発見された場合は、納付しなければならなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり3倍の印紙税額を徴収されます。
また、消印がない場合も、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっているので注意が必要です。
さらに、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
「印紙税くらい」と軽く考えていると、突然の税務調査で、痛い追徴金を受けることになるので、きちんと収入印紙で納税するようにしましょう。
税務調査で指摘を受ける前であれば、自主的に所轄税務署長へ納付していない旨の申出をした場合、印紙税額の1.1倍の納付で済みますので、自社の印紙税処理に問題がないか、改めて確認してみてください。
印紙税を必要額よりも多く納付してしまった場合
印紙税を納付する中で、本来よりも多くの税金を払ってしまう場合があります。例えば領収書に収入印紙を貼る時に、本来よりも1枚多く添付してしまうケースなどがあります。
もちろん救済措置はあります。印紙税を多く納付してしまった場合は、過誤納のあった文書を所轄の税務署に持参し、還付の手続きをすることができます。
電子的な書類の場合、印紙税はどうなる?
最近では電子的な文書を使ってやり取りをする場面も増えています。この場合、印紙税は適用されるのでしょうか?印紙税は作成された課税文書にかかってくるものです。ここで鍵になってくるのは「文書の作成とは何を指すか?」です。
印紙税法基本通達第44条によると、文書の「作成」とは、課税文書になる用紙等に課税事項を書き、これを当該の目的に従って使用することを言います。課税文書が作成された「時」は、場合にもよりますが、交付や認証を以て「作成」したことになります。印紙税法基本通達は以下のように定めています。
2課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平13課消3-12、平18課消3-36改正)
(1)相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時
(2)契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時
(3)一定事項の付け込み証明をすることを目的として作成される課税文書 当該最初の付け込みの時
(4)認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書 当該認証の時
(5)第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時
(出典:国税庁)
例えば小売店の例を考えてみると、領収書に収入印紙を貼り、それをお客様に渡した時に初めて、「課税文書を作成」したことになります。
そこでもしこれが電子だった場合を考えてみましょう。電子の場合、データを送付することはあるものの、書類を交付するようなことはありません。従って電子的な書類の場合は、印紙税が適用されないのです。
まとめ
普段仕事でよく使用する収入印紙は、意外と使用の判断が難しく、納税していない場合は過怠税が重いなどの側面があります。
少額だからと油断していると、税務局から指摘を受け、思わぬ金額を支払うことになるので、国税局の規則に沿ってきちんと納税するようにしましょう。

おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -
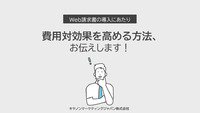
Web請求書の導入にあたり費用対効果を高める方法、お伝えします!
おすすめ資料 -

中堅大企業のための人事給与BPO導入チェックポイント
おすすめ資料 -
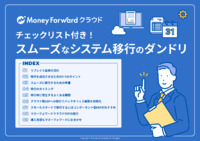
チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -
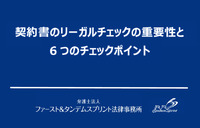
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

働く人の意識を変える定点観測
おすすめ資料 -
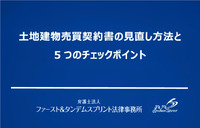
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -
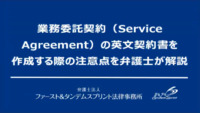
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -
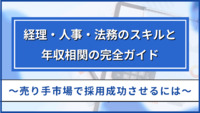
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

経理は転職サイトを利用すべき?経理人材の転職市場での価値を解説!
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

電車通勤のメリットとデメリット 株式会社ビズヒッツ調べ
ニュース -
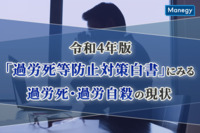
「令和4年版 過労死等防止対策白書」にみる過労死・過労自殺の現状
ニュース -

厄介な上司を賢く扱う!?明日からできる「マネージングアップ」とは【キャスター田辺ソランのManegy TV #14】
ニュース