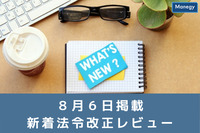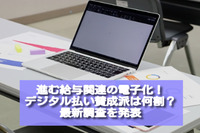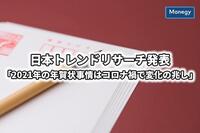公開日 /-create_datetime-/

2018年9月末で、2015年に施行された改正労働者派遣法から3年が経ち、人材派遣に関する「3年ルール」の最初の期限がやってきました。
3年ルールとは、おおまかにいうと「同じ派遣先に、同じ派遣社員が3年以上続けて勤務できない」という法的な取り決めです。この改正法の施行により、企業側は同じ部署などで3年を超えて派遣社員を業務に従事させたい場合、正社員や契約社員として直接雇用するなどの措置を取らねばならなくなりました。
同法では派遣元となる人材派遣会社が3年を超えて就労している派遣社員を「無期雇用」で雇えば、同じ派遣先で3年を超えても就労しつづけられるといった「雇用安定のための措置」も認められていますが、ここでは企業が派遣社員を直接雇用する際の手続きや注意点について解説していきます。
関連記事:人事担当者が知っておきたい、人材派遣の仕組みや種類について
目次【本記事の内容】
派遣社員の直接雇用は法的にOK?
いまではさまざまな業種において当たり前となっている人材派遣ですが、1980年代までは法律で禁止されているワークスタイルでした。国内における人材派遣業を可能にしたのは、1985年に成立し、1986年に施行された労働者派遣法(以下、派遣法)です。
同法が施行された当初、人材派遣が可能だったのは13業種のみでしたが、その後数回にわたって規制緩和がおこなわれ、港湾、建設、警備あるいは医療関連業務や弁護士・社会保険労務士などの一部の職業を除き、現在ではほとんどの業種で人材派遣をおこなうことが可能となっています。
しかし派遣社員という雇用形態が広がるにつれて、「派遣切り」など労働者にまつわる問題も表面化したため、派遣法においては、2012年には日雇い派遣を禁止するなどの改正が、2015年には冒頭に述べた「3年ルール」を法律に盛り込むなどの改正がおこなわれてきました。
派遣社員の直接雇用については、上記の派遣法に「派遣会社は派遣先との間で、原則として派遣労働者の雇用期間終了後に派遣先が派遣労働者を直接雇用することを禁止する契約を結んではいけないこと」が定められています。
これは派遣社員を直接雇用する際の大前提というべきものであり、派遣期間の終了後であれば、派遣先の企業が、派遣社員を直接雇用しても法的に何の問題もないことを意味しています。まず、こうした派遣期間終了後の直接雇用について解説します。
<一般派遣の場合>
一般の登録型派遣においては、求職者は人材派遣会社に登録をおこない、仕事があるときだけ派遣元となる人材派遣会社と雇用契約(労働契約)を結びます。この雇用契約は派遣期間の終了とともに終了となるものであるため、派遣期間の終了後であれば、派遣先の企業が派遣社員を直接雇用しても問題はありません。
<紹介予定派遣の場合>
紹介予定派遣は、最長6ヵ月の派遣期間を定めたうえで、派遣先企業と派遣社員の双方の合意があれば、派遣期間の終了後に、派遣先企業が派遣社員を直接雇用するという人材派遣のシステムです。
紹介予定派遣については、派遣法に定められた下記の条項がルールとして適用されます。
紹介予定派遣を含め派遣会社による職業紹介によって派遣労働者を直接雇用した場合には、派遣会社に紹介手数料を支払う必要がある。
この条項のうち、ポイントとなるのは「派遣会社による職業紹介によって派遣労働者を直接雇用した場合」という文言です。
紹介予定派遣は、その業務において「人材派遣」と「人材紹介」という2つの業態をおこなうことになるため、紹介予定派遣のシステムを利用して派遣先の企業が派遣社員を直接雇用した場合には、派遣先企業は派遣元である人材派遣会社に紹介手数料を支払わなければなりません。
ところで、派遣法にはもうひとつ、下記のような条項も定められています。
派遣先が、派遣終了後に派遣会社を介さずに、派遣労働者を直接雇用した場合には、紹介手数料を派遣会社に支払う必要はない。
これは、派遣期間の終了後であれば、派遣先の企業が派遣社員を直接雇用しても紹介手数料を支払う必要がないことを規定した法律ですが、紹介予定派遣の場合は、そもそも派遣先企業が直接雇用することを前提としているシステムのため、上記の条項の適用は難しいと思われます。この条項はあくまで一般の登録型派遣を対象としたものと見てよいでしょう。
なお紹介予定派遣の場合は、一般の登録型派遣とは違い、派遣による就業がはじまる前に派遣先企業が派遣社員の面接をおこなったり、人材派遣会社から派遣社員の履歴書を取り寄せたりすることが認められているほか、派遣期間の終了後に直接雇用が決まった際には、契約を結ぶ前に、直接雇用後の業務内容や労働条件を派遣社員に明示することなどが義務づけられています。
<派遣期間中に直接雇用をおこなう場合>
上に述べたのはあくまで「派遣期間の終了後」の例ですが、派遣期間中に派遣社員を派遣先企業が「直接雇用したい」となった場合、だいぶ話は異なります。
この場合、派遣先企業は、派遣元である人材派遣会社が派遣社員と結んでいる雇用契約を解消させたうえで、当該の派遣社員と新たに雇用契約を結ぶ必要があります。これは、いわば派遣先による派遣社員の「引き抜き」にあたる行為であるため、派遣先企業と人材派遣会社のあいだでかわされる人材派遣契約の内容によっては、派遣先企業が派遣元に違約金や紹介手数料を支払わなければならない場合もあります。
また、派遣期間中の「引き抜き」行為は、派遣先と派遣元の信頼関係を損ねる可能性もあるため、今後の付き合いを円滑におこなうことを考えても、派遣社員の直接雇用は「派遣期間が終了した後」におこなったほうがよいといえるでしょう。
社会保険や労働保険、税務関係の手続きは?
上にも述べたように、派遣社員が雇用契約を結んでいたのは人材派遣会社であるため、直接雇用をおこなう際には、新たに派遣先企業が保険や税に関する手続きをおこなう必要があります。
保険に関する手続き
社会保険と雇用保険については、新規採用の場合とおなじく資格取得届を作成して提出する必要があります。なお届出の期限は、健康保険と厚生年金保険については採用日から5日以内、雇用保険の届出は採用月の翌月10日までとなっています。
なお、労働者災害補償保険(労災保険)については個人ごとの手続きは不要です。
税に関する手続き
上記の保険と同様に、中途採用をおこなうときとおなじ手続きが必要となります。
税務の手続きにおいては、「前の勤務先」にあたる人材派遣会社(派遣元)から前職分(派遣社員であった期間で人材派遣会社から給与が支払われていた期間)の源泉徴収票を受け取り、それを年末調整処理に反映させます。
まとめ
冒頭に述べた「3年ルール」の影響などにより、最近では多くの人材派遣会社が「無期雇用」の派遣制度を採用しはじめました。これは文字通り、派遣社員が人材派遣会社と「無期限」で雇用契約を結ぶものであり、派遣先での直接雇用への切り替えを難しくする側面も持った制度ともいえるため、派遣会社によっては優秀な派遣社員の「囲い込み」が指摘されているのも実情です。
こうした現状から考えると、一時的な労働力として人材派遣を利用したい企業はともかく、将来的に直接雇用をおこなうことも視野に入れている企業の場合は、人材派遣会社と契約をおこなうときに、直接雇用をする際の条件を確認しておくことがますます重要になってくるといえます。
また働く側にとって直接雇用への移行は、派遣のときよりも賃金が下がったり、おなじ直接雇用でも正社員ではなく契約社員で不安定な立場に置かれたりといった不利益が生じる場合もあります。お互いに「こんなはずじゃなかった」という事態を避けるためには、派遣社員→直接雇用への移行の際には、労働条件や契約の内容について、双方が慎重に検討することが必要といえそうです。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
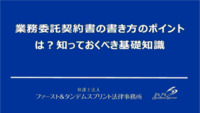
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -
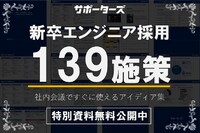
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -
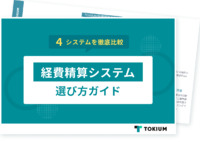
失敗しない!法対応と業務効率化を実現する経費精算システム選び方ガイド【4社の比較表付き】
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -
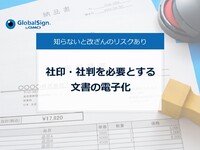
社印・社判を必要とする文書の電子化
おすすめ資料 -

コロナで変わった人事現場の実態 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -

<人的資本開示 実践編 > 人的資本と組織サーベイ
おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -
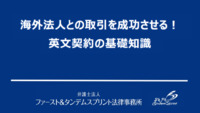
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース