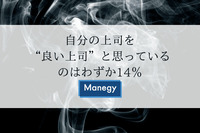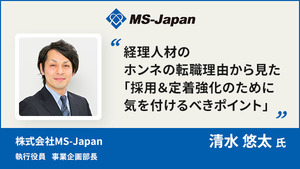公開日 /-create_datetime-/
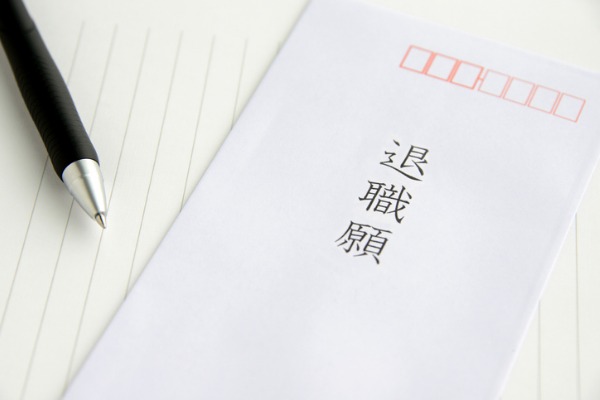
会社員が自ら会社を辞めるとき、つまり労働者からの申し出によって雇用者との労働契約を終了する際には、通常は書面によって事前に退職を会社側に通告することが企業の就業規則に定められています。
もちろん、いきなり会社に行かなくなるという辞め方はもってのほかですが、いざ会社を辞めたいと思ったときには「退職願」「退職届」「辞表」のどれを提出するのが正しいのでしょうか?
ここでは「退職願」「退職届」「辞表」のそれぞれの違いや用途、具体的な書式などについて解説していきます。
目次【本記事の内容】
退職願と退職届の違い
まず「退職願」ですが、これは労働者が雇用者に対して労働契約の解除を願い出るための書類です。
簡単にいえば退職願は、会社員が「退職したい」という自分の意向を会社に伝えるものといえるでしょう。そのため退職願は、雇用者側に受理された時点ではすぐに退職とはならず、労働者と雇用者による話し合いなどを経て、雇用者側が退職を承諾した段階ではじめて退職が決定します。また、退職願については、雇用者側が退職を承諾するまでの間であれば撤回することも可能です。
一方、「退職届」は「退職します」という決定事項を労働者が雇用者側に通知するものであり、雇用者に受理された時点で退職が決定する書類です。そのため退職届については一度受理されてしまったら基本的に撤回はできません。
退職の意思表示をするタイミング
退職願や退職届を出すタイミングについては、たとえば「退職予定日の1ヶ月前」といったように、通常は企業が定める就業規則において期日が定められています。ただし正社員のように雇用期間の定めがない労働者の場合は、法律上は14日前までに申し出れば退職できることが可能となっています。
一方、契約社員のように雇用期間の定めがある労働者の場合は、雇用者と労働者の双方の合意がなければ、契約を途中で勝手に解消することはできないため、契約期間中に自分の都合で仕事を辞めるのは難しいといえます。これは雇用者側も会社の都合で契約期間中に契約社員や派遣社員を一方的にクビにしたりはできないことを意味していますが、病気療養などの「やむを得ない事情」がある場合に限り、契約期間の途中でも退職できることが法律では認められています。
さらに、こうした契約社員や派遣社員といった有期契約の労働者については、契約の初日から1年が経過したあとは自由に退職できることが、暫定措置として労働基準法に定められています(ただし、専門職等を除く)。
ちなみに、労働者が自らの意思で退職届を提出するケースとしては、退職願を会社に対して提出したものの、会社側が辞めさせてくれない場合などがあげられますが、就業規則に定められた正当なルールに則って退職届が出された場合、会社側にはこれを受理する義務があり、断ることはできません。そのため退職届をどうしても会社が受理してくれず、会社を辞められないといった事態が生じることがあります。そういった場合、労働基準局や都道府県にある労働局の相談センターに相談しなくてはならなくなることがあります。
退職願や退職届を書いてはいけないケースも
労働者が会社に対して退職願や退職届を提出するのは自らの都合で会社を辞める場合であり、会社側の都合によって「退職させられる」ときは、これらの書類を提出する必要はありません。
気をつけなければならないのは、企業が会社側の都合で社員を退職させるのに、社員に退職願や退職届を書かせようとするケースです。会社都合で社員を退職させたという事実が残ると、企業のイメージダウンや助成金の支給カットなどにもつながる場合があるため、「会社側都合で社員を退職させた」と認めることを嫌がる企業もあるようです。一方、労働者も自己都合と会社都合では、失業手当が支給される時期や期間などに大きな違いが出てきてしまうため注意が必要です。
ちなみに会社都合で退職した場合はハローワークで手続きをしてから約1ヶ月後には失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取れますが、自己都合の場合は待機期間7日+3ヶ月の間、支給を待たなければなりません。また、失業手当の支給期間も、会社都合の場合は雇用保険の被保険者であった期間に応じて90~330日と長く設定されているのに対して、自己都合の場合は90~150日に限定されています。
なお、悪質なケース以外でも、あくまで手続きの関係で社員に退職届の提出を求める企業もありますが、そうした場合には「会社側の都合で退職する」ということをきちんと記した通知書を会社からもらうのを忘れないようにしましょう。
「辞表」は「退職願」や「退職届」とは違う?
それでは「辞表」は退職願や退職届とどう違うのでしょうか?
辞表は「退職の意思を伝える」ための書類であることには変わりありませんが、一般の会社員が提出するものではありません。
辞表とは、会社の運営に関わっている役員クラスの人が辞任するときや、公務員が仕事を辞める際に提出する書類を指します。民間企業の社員の場合は会社と労働契約(雇用契約)を結んでいるため、この労働契約を解約するために退職願や退職届を出すのですが、企業の取締役や公務員の場合は、会社や職場と労働契約を結んでいるわけではありません。
通常、企業の役員が会社と取り交わしているのは「役目をお任せしますよ」という委任契約であり、公務員の場合は国や行政から職を命じられるという「任用」によって働いています。そのため、役や職を辞する際には辞表を提出することになるのです。
企業によっては「辞表を出すのは課長以上の役職についている人」と取り決めているケースも見られますが、いずれにしろ特に役職についていない社員が会社を辞める際に辞表を出すのは「書類が違う」ということになるので気をつけましょう。
辞表については「役員や公務員の人が出す退職願」と覚えておくといいかもしれませんね。
退職願と退職届の書式の違い
退職願や退職届の書式ですが、会社側が決まったフォーマットを用意していることは少なく、書式は自由となっているケースが多いようです。
退職願・退職届ともに通常は白無地の封筒と便箋を用意し、文面は黒インクなどを用いて記します。封筒の表面には「退職願」(あるいは退職届)、裏面左下には所属部署と氏名を書きます。
下記は退職願と退職届の一般的な文面です。
<退職願>
「このたび、一身上の都合により、平成○○年○月○日をもちまして退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」
<退職届>
「このたび、一身上の都合により、平成○○年○月○日をもちまして退職いたします。」
退職願と退職届では「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」「退職いたします。」といったように、文末に大きな違いがあるので注意しましょう。
なお本文のあとには、数行空けて退職願や退職届を提出する日付と自分の名前を書き捺印したうえで、「○○株式会社 代表取締役 ○○殿」といったように最後に企業の代表者の氏名を記入します。
まとめ
「退職願」「退職届」「辞表」の違いについてご理解いただけたでしょうか?
一般企業に勤める会社員の場合、辞表を提出することはまずないと思われますが、退職願と退職届については、それぞれの意味をしっかりと理解したうえで、状況に応じて書類を使い分けることが必要となります。
使用法を間違えないためには、
「退職願」→会社側が退職を承諾するまでは撤回できる。
「退職届」→いちど受理されたら基本的に撤回できない。
というように覚えておくとよいかもしれません。
いずれにしても会社を辞める際には慎重に検討を重ねたうえで、会社の就業規則に沿った形で手続きを行うことが大切といえるでしょう。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -
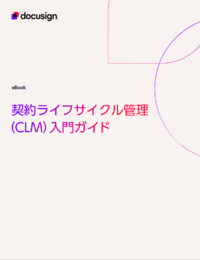
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -
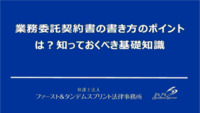
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

BillOneの導入で請求書業務はこう変わる
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -
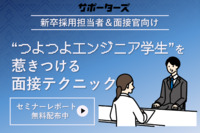
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -
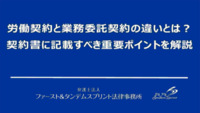
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -
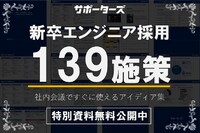
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース