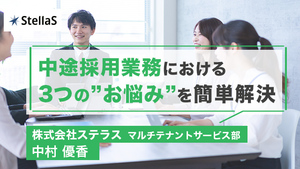公開日 /-create_datetime-/

現在、売り手市場と言われる企業の採用活動の中で、高校生の新卒採用が注目を浴びています。
大卒者やキャリア経験者の人材確保が困難な状況を背景に、企業の高卒採用への意欲が高まっているのです。
日経新聞の記事によると、「主要企業の19年卒の高卒採用計画数は18年卒実績に比べて8.2%増え、厚生労働省も19年卒の高卒求人倍率は7月末時点で2.37倍の高水準となる見通し」と発表されており、企業が積極的に高卒者採用に乗り出していることがわかります。
こうした背景を踏まえて今回は、高卒者の就職活動について見ていきましょう。
関連記事:採用担当は要チェック! “就活ルール”廃止決定でどうなる人材採用計画
高卒就活と大卒就活の違い
高卒者の就職活動(以下、就活)は、大卒者の就活とはその方法、時期、手順が大きく異なります。
一般的に大卒者の就活は、就活者本人が就職サイトに登録し、サイトを通して、企業に直接履歴書やエントリーシートを送付して選考に臨みます。
大学にも「就活課」が存在することが多いですが、こちらは就活についてのアドバイスを行うのが主な役割です。企業から提供された求人票の設置は行いますが、基本的には紹介や推薦をしてくれるわけではありません。
一方、高校生の就活は学校・ハローワーク・企業が連携して行う仕組みになっています。
高校生の本分である学業に支障がでないよう、また、適正な職業選択が促されるよう、行政、学校組織、経済団体により、就活に関する規制や禁止事項が設けられています。
就職活動を行う当事者である学生(以下、学生)と高卒者の求人活動を行いたい企業(以下、企業)は、その事項を遵守しながら採用活動を行わなければなりません。
企業は、必ずハローワークで求人票を作成し、求職者の学校を通して採用活動を行うことがルールとなっています。学生も同様に、学校を通して就活を行わなければなりません。
高卒就活の流れ
厚生労働省が発表した、19年卒の高卒者採用の具体的なスケジュールは、下記の通りです。
【新規高等学校卒業者の採用選考スケジュール】
○ ハローワークによる求人申込書の受付開始 6月1日
※ 高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を確認したのち、学校に求人が提出されることとなる。
○ 企業による学校への求人申込及び学校訪問開始 7月1日
○ 学校から企業への生徒の応募書類提出開始 9月5日(沖縄県は8月30日)
○ 企業による選考開始及び採用内定開始 9月16日
6月1日から、企業は募集したい人材について、ハローワークで求人の申し込みを行うことができます。また、7月2日からはハローワークの確認印を受けた求人票を各学校へ持参し、高校へ求人活動のための訪問をすることができます。
学生は、公開された求人票の情報などを見ながら1社を選び、全国高等学校統一応募用紙と呼ばれる、履歴書にあたる書類を作成。9月5日(沖縄は8月30日)から、学校を通して企業に提出します。
その後、9月16日から企業による選考活動が開始するという流れになっています。
規制や禁止事項によるメリットとデメリット
高卒者の就活に上記のようなルールが設けられているのは、まだ若い高卒者を守る意図が大きいのですが、問題点が指摘されているものもあります。それぞれのルールには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
・1人1社制
従来から1人の学生がある会社に応募した場合、選考結果が出るまで他の求人に応募することができないことになっています。地域により10月または11月からは2社まで応募することができますが、基本は1人1社制です。
このルールのメリットは、企業側から見ると内定辞退を防げる点です。高卒就活では、応募は高校からの推薦という形になるため、内定辞退はないものというのが前提なのです。1人1社制のおかげで、学生・企業ともに、早期でのマッチングが可能になっていると言えるでしょう。
一方で、求職者は1社しか求職活動を行えないため、実際に選考過程を踏むことでの会社への理解を深める機会を複数社で持つことができず、応募する会社が本当に自分にマッチしているのか、判断が難しくなるという点がデメリットとなっています。
・学校とハローワークを経由しなければならない
企業はハローワークでの登録後、学校を通して求人活動を行うことが決められています。実際の選考は、学校の就活課や担任の先生が求人に適切な生徒を選定してから、ようやく正式に始められることになります。
このルールは、企業にとっては、多数の応募の中から適切な人材を選定する役割を学校が担ってくれるため、採用活動の負担軽減になるという点が、メリットとして挙げられます。しかし一方で、一度の面接以外、求職者と直接コンタクトする機会がないため、人柄や志向を知る機会が少なくなるというデメリットも含まれます。
生徒から見ても、ハローワークの情報サイト上だけの、限られた中で情報収集をしなければならず、知りたいことが十分得られないリスクがあります。さらに、学校の推薦による応募のため、内定決定後にミスマッチを感じたとしても辞退できない点が、デメリットとなることがあるでしょう。
このように、高卒就活独特のルールは、売り手市場下で求人活動を行う企業にとっては、「内定辞退のリスクを下げられる」「適当な求人者と出会えれば早期に採用を決定できる」点がメリットとなっています。
一方で、当事者間の理解を深める機会や、学生が企業を選択する機会が少ないことで、入社後にミスマッチが起こりやすいという問題もあります。
まとめ
企業と学生の両者が、良い採用活動、良い就職活動を行うためには、高卒採用制度のメリット・デメリットを把握した上で、それぞれに可能な範囲でできる限りの行動を起こすことが大切になるでしょう。
入社後のミスマッチ防止を考え、採用担当者は会社見学の実施など、学生に自社理解を深めてもらえる機会を作ってみてはいかがでしょうか。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

請求書受領サービスの 失敗しない選び方
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

コロナで変わった人事現場の実態 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -
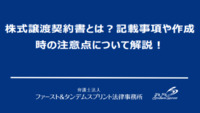
株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -
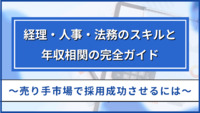
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -
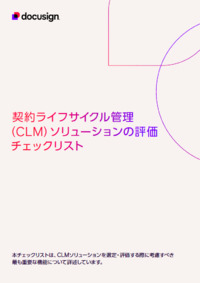
どう選ぶ?契約ライフサイクル管理(CLM)ソリューションの選定に役立つ評価チェックリスト
おすすめ資料 -
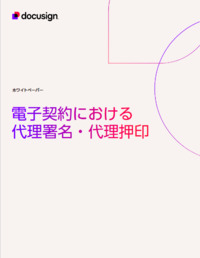
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -
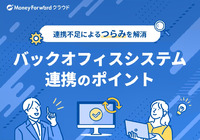
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース