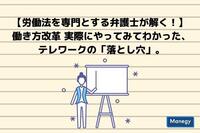公開日 /-create_datetime-/

多様な経歴を有する裁判官や検察官、弁護士の育成を目指し、社会人や法学部出身者以外も対象にして始まった法科大学院制度だが、スタート時の2004年度こそ志願者が72,800人だったが、今年度は8,159人にまで激減、廃止や募集を停止するところが相次いでいる。
文部科学省によると、ピーク時には74校の法科大学院が存在したが、来年度に学生を募集するのは36校にとどまるという。その最大の理由が、修了者の司法試験合格率の低迷だ。
今年の司法試験合格者は、5,967人(前年比932人減)が受験し1,543人(前年比40人減)が合格。しかし、この中には法科大学院を修了しなくても司法試験受験資格が得られる「予備試験」の通過者が290人。その合格率は72.5%で、法科大学院修了者の22.5%を大きく上回る高い合格率を示している。
曲がり角にある法科大学院制度について、政府は、制度見直しの概要をまとめたが、入学総定員(今年度約2,300人)の管理を行い、各大学院による定員変更を現行の届け出制から認可制に変更するという。
また、法学部進学者が学部3年、法科大学院2年の計5年で修了し司法試験を受験できる「法曹コース」創設と共に、法科大学院教育・司法試験連携法の改正案を、来年の通常国会に提出するとしている。
この法改正によって、法科大学院が自由に定員を増やせないようにするほか、定員規模を決める際には、文科相が法曹需要などを的確に判断できるよう法相と協議する仕組みも規定する。
ところで、この迷走を続ける法科大学院制度は、司法の果たす役割が大きくなるという見通しから創設されたが、政府の見通しとは逆に、職に就けない弁護士が増え、司法試験受験者が激減。それでも政府は、法科大学院制度見直しによって、当面は入学定員約2,300人を維持する方向のようだが、これにより司法試験受験者が増えるかどうかは不透明だ。
法科大学院の迷走とは裏腹に、企業にとっては法務需要がますます高まること予想されるだけに、法務担当者や総務担当者としても、こうした動きは気になるところといえるのではないだろうか。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
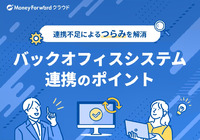
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -

<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方
おすすめ資料 -
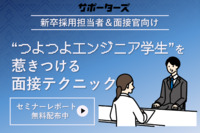
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -

経理BPO業務事例のご紹介
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -
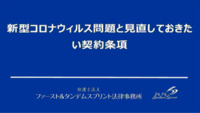
新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -
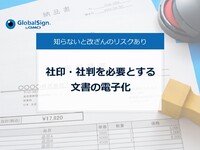
社印・社判を必要とする文書の電子化
おすすめ資料 -
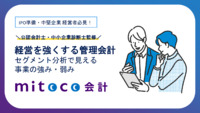
経営を強くする管理会計 セグメント分析で見える事業の強み・弱み
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

電車通勤のメリットとデメリット 株式会社ビズヒッツ調べ
ニュース -
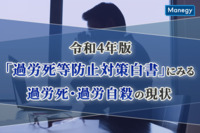
「令和4年版 過労死等防止対策白書」にみる過労死・過労自殺の現状
ニュース -

厄介な上司を賢く扱う!?明日からできる「マネージングアップ」とは【キャスター田辺ソランのManegy TV #14】
ニュース -

「生前贈与」「マイナンバー一本化」「助成金・補助金の違い」などの記事が人気 マネジーニュースランキング(11月7日~11月13日)
ニュース -

SNS上の誹謗中傷を排除する、改正プロバイダ責任制限法で手続き簡略化が可能に
ニュース