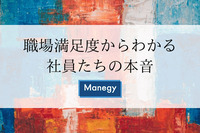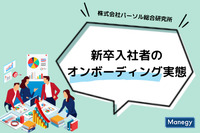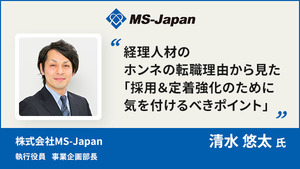公開日 /-create_datetime-/

株主総会とは、株式会社における最高意思決定機関です。会社の実質的な所有者である株主の意思により重要事項が決議されるよう、株主総会の詳細は会社法により定められています。この記事では、株主総会とは何のために行うものなのか、その目的と内容に関して会社法での規定を簡単にわかりやすく解説します。
関連記事:お土産廃止で出席者減少・・・、イマドキの株主総会事情
目次【本記事の内容】
株主総会とは?
株主総会とは、株式会社の最高意思決定機関です。すべての株式会社は株主総会を置かなければならないと会社法で定められており(295条)、株主総会以外で株式会社に置かなければならないと会社法が定めているのは1人以上の取締役だけです(326条1項)。
会社法は、さまざまな部品を組み立てた「機械」のようなものとして会社をみなします。それぞれの部品は「機関」と呼ばれ、株式会社の機関には株主総会と取締役のほか取締役会、代表取締役、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人などを置くことができます。
会社に置かれる機関のなかで株主総会は、会社の組織形態や人事、株主の利益に関することなど、会社にとってもっとも重要なことを決議する権限が与えられています。国の機関に例えてわかりやすく簡単にいえば、株主総会は「国会」のようなものだといえるでしょう。
株主は、株式を購入することにより会社に出資する立場ですから会社の実質的な所有者であるといえます。株主を構成員とする株主総会が株式会社の最高位置決定機関として位置づけられていることは、「重要な決定は会社の所有者にゆだねる」という理念の表れであるといえます。
株主総会の権限
株主総会の権限は、3人以上の取締役により構成される「取締役会」を置いているかどうかによって異なります。
取締役会を置いていない場合
取締役会を置いていない株式会社の場合には、株主総会は「一切の事項について決議をすることができる」と定められています(会社法295条)。
取締役会を置いている場合
取締役会を置いている株式会社の場合には、株主総会は、
- 法定事項
- 定款で定めた事項
について決議をすることができるとされます(会社法295条2項)。
ここで「法定事項」とは、
- 取締役や監査役の選任や解任など重要な人事について
- 定款の変更や会社合併、分割、解散など組織の形態について
- 株式の合併や剰余金の配当、役員の報酬など株主の利益について
などのことです。
また、「定款で定めた事項」とありますが、株主総会で決議すべき法定事項について「株主総会以外の機関で決定する」と定款に定めても、その定めは効力を発揮しません(295条3項)。
株主総会の種類
株主総会の種類には、
- 定時株主総会
- 臨時株主総会
の2つがあります。
定時株主総会
定時株主総会は年に1回、決算の発表後に行われます。決算の承認とそれにともなう余剰金分配決議、役員の選任決議を行うことが定時株主総会の目的で、会社法により開催が義務付けられています(124条2項)。定時株主総会は会社法により決算から3ヶ月以内に行うこととなっています。日本では、3月決算の会社が多いため、株主総会も5月~6月に行われることが多くなります。
臨時株主総会
臨時株主総会は、会社の合併や分割、株式交換など株主総会で決議されるべき重大なことが発生した際に臨時に行われるもので、時期や回数などに制限はありません。
株主総会の決議
株主総会の決議には、決議する内容により、
- 普通決議
- 特別決議
- 特殊決議
の3種類があります。
普通決議
普通決議は、役員の報酬や取締役・監査役の選任など、法律や定款に特別な定めがない事項について決議します。議決を行うためには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数が出席することが必要で、出席者の議決権の賛成過半数により決議されます。
特別決議
特別決議は、会社法で定められた、より重要とみなされる事項を決議するためのものです。特別決議の具体的な決議事項はたとえば次のようなものです。
- 定款の変更、事業の譲渡、解散など
- 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転など
- 資本金の減少
特別決議を議決するためには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数が出席することが必要で、出席者の議決権の賛成が3分の2以上で決議されます。
特殊決議
特殊決議は、特別決議よりさらに重要とみなされる事項について決議するためのものです。会社法309条3項に該当するケースと309条4項に該当するケースがあります。
<会社法309条3項による特殊決議>
309条3項による特殊決議では、
- 全株式を「譲渡制限株式」とする定款の変更
- 吸収合併契約の承認
- 新設合併契約の承認
についての決議が行われます。議決を行うためには、議決権を行使することができる株主のうち過半数(「株主の議決権」ではなく「株主」の過半数)の出席が必要で、議決権の3分の2以上の賛成をもって決議されます。
<会社法309条4項による特殊決議>
309条4項による特殊決議は、「配当、分配、議決権につき株主ごとに異なる取り扱い」を定款で定める場合に行われます。議決を行うためには総株主の過半数の出席が必要で、議決権の4分の3以上の賛成をもって決議されます。
株主総会の招集
株主総会を開催するためには「招集」の手続きを行わなければなりません。会社法により招集の方法が定められています(会社法296条~307条)。
招集の決定
株主総会を招集するためには、
- 株主総会の日時・場所
- 株主総会の目的
- 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使できるか
- 株主総会に出席しない株主がインターネットによって議決権を行使できるか
を、取締役会を設置していない株式会社では取締役が決定し、株主総会を招集します。取締役会を設置している会社の場合は、上の事項を取締役会で決定し、代表取締役が招集します。
少数株主による招集
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月以上前から保有している株主は、株主総会の目的と招集の理由を示した上で、株主総会の招集を請求することができます。また、請求したのに招集手続きが取られない場合には、裁判所の許可を得たうえで株主総会を招集することができます。
招集の通知
株主総会の招集は、書面またはインターネットによって通知しなくてはなりません。通知を発送しなければならない期間は、
- 公開会社 …2週間前
- 書面決議やインターネットによる決議を定めた非公開会社 …2週間前
- 上を定めなかった非公開会社 …1週間前
- 取締役会を設置していない会社 …定款で1週間以下の期間を定めることもできる
と定められています。
株主総会の流れ
株主総会の流れは、だいたい以下のようになるのが一般的でしょう。
株主総会招集の決定
上で解説した通り、取締役会を設置していない会社では取締役が、取締役会を設置している会社では取締役会が招集を決定します。
招集通知
定められた期間までに招集通知を発送します。
総会の準備
想定問答集を作成することが必要な場合もあるでしょう。
株主総会当日
(1)開会の宣言
(2)出席株主数と株式数の報告
(3)議事進行のルールや発言の仕方についての説明
(4)監査報告
(5)報告事項 …事業報告と計算書類、連結計算書類などが報告されます。
(6)議案上程 …基本的に会社側から議案が上程されますが、株主から議案が提出されることもあります。
(7)質疑応答
(8)決議
(9)終了宣言
議事録の作成と保存
株主総会の議事録は、会社法施行規則72条により義務付けられています。本店に10年間、支店に写しを5年間保存し、株主や会社債権者の請求による閲覧やコピーに応じます。
まとめ
株主総会は、株式会社の最高意思決定機関です。株式会社の実質的な所有者である株主により重要な意思決定が行えるよう、株主総会の権限や決議、招集などについての詳細が会社法で定められています。決議された内容は会社に重大な影響を及ぼしますので、株主総会を開催するにあたっては万全の準備が必要となるでしょう。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
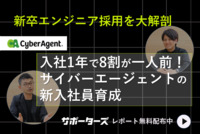
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -
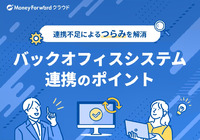
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -
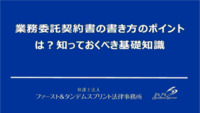
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

若手社員の早期離職を防止するためにできること
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -
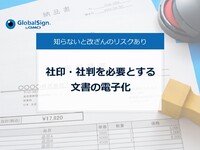
社印・社判を必要とする文書の電子化
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース -

若い世代が職場で直面する差別や偏見とは?
ニュース -

電車通勤のメリットとデメリット 株式会社ビズヒッツ調べ
ニュース -
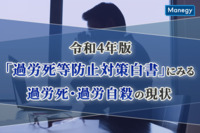
「令和4年版 過労死等防止対策白書」にみる過労死・過労自殺の現状
ニュース