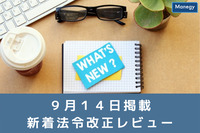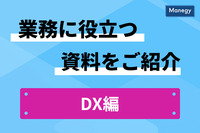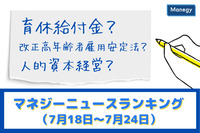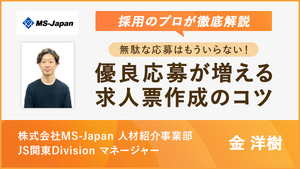公開日 /-create_datetime-/
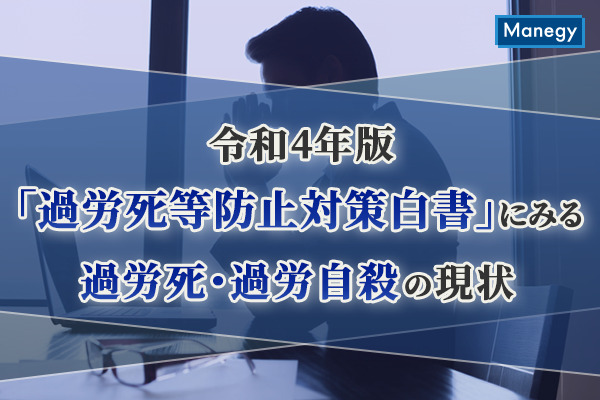
政府は過労死や過労自殺の現状を分析した「令和4年版 過労死等防止対策白書」を公表しました。はたして、新型コロナウイルスの感染拡大やテレワークが、働く人にどのような影響を与えたのでしょうか。
テレワークの頻度が高いほど“うつ傾向・不安”が少ない
「過労死等防止対策白書」に盛り込まれているのは、労働時間やメンタルヘルス対策等の状況、過労死等の現状、過労死等をめぐる調査・分析結果、過労死等の防止のための対策の実施状況などです。
その中で注目したいのが、テレワークの頻度が高い人ほど、うつ傾向や不安が少ないという調査結果です。
新しい働き方の一つとして、徐々に浸透しつつあったテレワークは、新型コロナウイルス感染症の予防対策として、一挙に導入が進みました。テレワークの普及によって、通勤の負担が大幅に軽減され、十分な睡眠時間をとれるようになったことが、うつ傾向の減少につながったようです。
うつ病や精神障害は中高年層に増加傾向
うつ病や精神障害の原因は、男性では「仕事内容・仕事量の大きな変化」、女性では「悲惨な事故や災害体験」「セクハラを受けた」などで、一般的には青年期に発症するケースが多いとされています。
しかし、労災認定数を分析した結果によると、労働環境によっては中高年でも発症する可能性が高く、近年、中高年層で増加傾向を示していることがわかりました。
長時間労働など労働環境が悪化した状態で働き続けることは、心身に大きな負荷がかかり、精神的にも肉体的にも大きなダメージを受け、仕事中に倒れてしまうことや、自ら命を絶ってしまうケースもあります。
過労死の撲滅を目指した「過労死等防止対策推進法」
働き過ぎで心身の健康を害し、死に至るということを一般的に「過労死」と呼んでいます。厚生労働省の認定基準によると「日常業務に比較して特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を発症前に受けたことによって発症した、脳・心臓疾患」とあります。
また、精神的にうつ状態から自ら命を絶つ「過労自殺」は「客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷により精神障害を発症しての自殺」と定義しています。
過労死の撲滅と、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現を目指して施行されたのが「過労死等防止対策推進法」です。
勤務条件による自殺の原因は「仕事の疲れ」が最多
過労死を未然に防ぐために企業側がとるべき対策として、厚生労働省は長時間労働の削減、過重労働による健康障害の防止、働き方の見直し、職場におけるメンタルヘルスケア、職場のパワハラ予防・解決、相談体制の整備を呼びかけています。社員の健康を守るために、労務管理の担当者は、自社の状況を再点検してみてはいかがでしょうか。
白書では、勤務条件が原因で自殺したケースも分析していますが、「仕事の疲れ」が28.3%でもっとも多く、「職場の人間関係」が24.6%、「仕事の失敗」が17.0%、「職場環境の変化」が14.0%で続いています。
また、過労死等の防止のための対策の実施状況や、企業の取り組み事例をコラムとして紹介しています。それらを参考に職場から過労死や過労自殺者を出さないために、職場環境改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。
まとめ
2021年度に精神障害の労災認定が認められた業種は、「医療、福祉」の件数がもっとも多いようです。新型コロナウイルスの感染拡大によって、医療機関や高齢者の福祉施設、保育園などの労働環境が悪化したことはテレビや新聞のニュースで盛んに報じられたように、皆さんもご存じでしょう。ただ、医療・福祉現場の労働環境の悪化は、コロナ禍による一時的なものではないことも現実です。
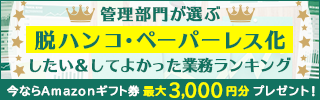
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
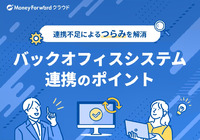
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -

<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -
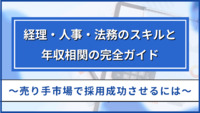
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -
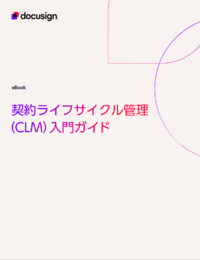
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -
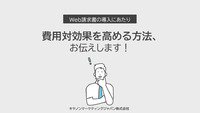
Web請求書の導入にあたり費用対効果を高める方法、お伝えします!
おすすめ資料 -
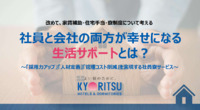
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -
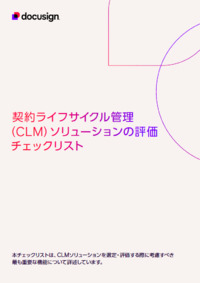
どう選ぶ?契約ライフサイクル管理(CLM)ソリューションの選定に役立つ評価チェックリスト
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース