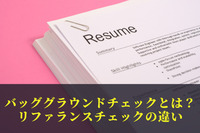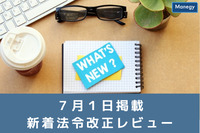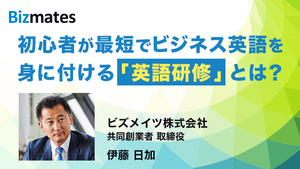公開日 /-create_datetime-/
iDeCo加入年齢を69歳まで拡大する狙いと背景は?
確定拠出年金法の一部が改正され、「iDeCo」の受給開始年齢の上限が75歳まで延長されることになりましたが、加入対象年齢についても、現行の64歳以下から69歳まで拡大する検討に入ったことが明らかになりました。
加入も運用もすべて自分自身で行う私的年金
個人型確定拠出年金「iDeCo」は、加入も運用もすべて自分自身で行う私的年金で、公的年金の1階部分が国民年金、2階部分を厚生年金とすれば、3階部分に相当するものです。
公的年金と組み合わせることで、老後の生活をより豊かにするための私的年金は、個人で毎月掛金を拠出し、投資信託などでの運用益と掛金の合計額を受け取れるという制度です。
超高齢社会となり、公的年金の給付水準も下がる一方で、現役世代の負担もますます重くなる傾向にあります。それを象徴するかのように、老後に安定した生活を送るためには「2,000万円が必要」という試算が大きな話題となったことが思い出されます。
個人の資産形成の手段を貯蓄から投資へうながす狙い
公的年金だけでは老後の安定した生活ができないとなれば、自力で資産形成しなければなりません。しかし、これだけ長く低金利が続いている状況では、貯蓄による資産形成にも限界があります。
そこで注目されているのが、公的年金に上乗せできる個人型確定拠出年金です。政府が加入年齢の引き上げの検討に入ったのは、個人の資産形成の手段を貯蓄から投資へうながす狙いがあるようです。
iDeCoは、掛金を投資信託などの金融商品で運用し、その運用益で資産形成するものですから、運用次第では資産形成に有利に働きます。しかも、税制優遇措置もありますから、上手に活用すれば、家計の所得増にもつながる制度といえるでしょう。
老後の生活が成り立たない現行の年金制度
ところで、iDeCoの加入者数は、現在250万人ほどです。加入年齢引き上げとなれば、加入者数が増加することが見込まれます。岸田政権が掲げる「資産所得倍増プラン」にも、貯蓄を投資に振り向ける機会を広げることが盛り込まれるようです。
少子高齢化により働き手が減少していることから、高齢者でも仕事を続けられる環境整備も着々と進んでいます。高齢でもiDeCoに加入しやすくする法改正は、歓迎すべきかもしれません。
しかし、別の見方をすれば、現行の年金制度では老後の生活が成り立たないことを、政府が認めたことになるのではないでしょうか。いずれにしても、公的年金で老後の安心が保てないのであれば、老後に備える何らかの手を打つ必要があります。
現実味を帯びてきた老後資金 “2,000万円問題”
その一つがiDeCoの加入ですが、貯蓄や株式投資よりも有利なのは、税制優遇措置が取られていることです。
毎月の掛金は、小規模事業共済の控除の対象になります。また、投資信託などで運用する運用益は非課税となり、将来年金や一時金として受け取る場合も、退職控除や公的年金控除の対象となります。
公的年金の1階部分である国民年金の保険料の納付期間も、現行の20歳以上60歳未満の40年間から、64歳までの45年間へと5年延長する検討を始めています。どうやら、公的年金の給付水準の低下は避けられず、老後資金としての“2,000万円問題”が現実味を帯びてきているようです。
まとめ
先が見通せない不確実な時代ですが、「公的年金だけでは老後生活を保障できない」「自分で老後資金を作っておく必要がある」ことだけは確かなようです。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

BillOneの導入で請求書業務はこう変わる
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

経理BPO業務事例のご紹介
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖
おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -
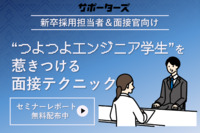
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -
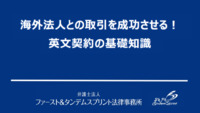
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース