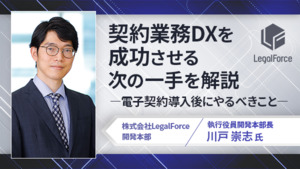公開日 /-create_datetime-/

給与とは別に自社株を従業員に譲渡する「社員持ち株制度」を導入する株式会社が増えています。なぜ、株式を従業員に持たせるのでしょうか。この制度に伴うメリットやデメリット、そして制度導入の流れや注意点などについてお伝えします。
社員持ち株制度とは?
従業員が毎月一定額を拠出し、その勤める株式会社の株式を買い付けることを、社員持ち株制度(従業員持ち株制度)といいます。
社員持ち株制度によって従業員へ提供される株式は、会社から支給するのでなく、必ず従業員が対価を支払って購入する形式を採らなければなりません。なぜなら、給与代わりに株式を譲渡することは、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めた労働基準法24条1項(賃金通貨払いの原則)に違反してしまうからです。
日本における社員持ち株制度は、戦後すぐに始まり、普及していったといわれます。アメリカ合衆国のEmployee Stock Ownership Plan(ESOP:退職給付として従業員に株式を割り上げる制度)にならって導入されたものとされます。
しかし、当初は社員にとっての制約が大きかったのも確かです。
社員株主は他の株主と同様に、毎年一定の配当をえることができ、退職時には会社あるいは従業員持ち株会が買い取ってくれるのですが、在職中の自由な売却は許されていない場合がほとんどでした。つまり、インカムゲインとしての配当収入をえることはできても、キャピタルゲインとしての値上がり差益をえることはできなかったわけです。
今でも、従業員に株式を直接譲渡するのではなく、「従業員持ち株会」が従業員に代わって株式を預かる形式を採り、配当は定期的に渡すけれども、キャピタルゲインをえられない運用としているところがほとんどです。持ち株会が組織され、自社株買い戻しのルールを明確に定めておくことで、自社株を会社が買い戻すときにその価格をめぐってトラブルになることを避けやすくなります。
なお、社員持ち株制度とストックオプションを混同してしまう人がいますが、両者は明確に異なる概念ですので、ご注意ください。
社員持ち株制度は、実際に株式を会社が従業員に譲渡する(従業員持ち株会が組織されている場合は、会社が同会に譲渡する)ものですが、ストックオプションは決められた時期に決められた価格でその会社の株式を購入することができる「権利」を渡すことです。また、ストックオプションを渡す相手は従業員に限定されません。
社員持ち株制度を導入する企業側のメリット・デメリット
社員持ち株制度は、企業側にとってもメリットがあります。自社株を従業員(従業員持ち株会)が保有することによって、会社の方針に賛同する会社以外の安定株主が増えて、経営が盤石になるからです。従業員持ち株会の会長に、自社の総務部長などが従業員代表の立場で就くことも多いです。もっとも、従業員持ち株会の議決権行使には不透明性が付きまとうため、社外の株主からクレームが付く危険性もありますので、注意を要します。
また、従業員持ち株会を介して従業員が自社株を保有することで、従業員が経営参画意識を持つようになります。会社が多くの利益を出せば出すほど、配当額も高くなるからです。よって、ただ指示待ちで業務を行うのでなく、「どうすれば、会社の利益アップに貢献できるだろうか」という経営者と同じ視点から仕事を行う、モチベーションや意識の高い従業員も増えていくでしょう。そうして、さらに会社の業績が向上していく好循環にも期待できます。
社員持ち株制度は、福利厚生の一環ともなりえます。たとえ従業員の給与やボーナスの額を上げにくい事情があっても、持ち株の配当が増えれば従業員の満足度は向上していくでしょう。
さらに、社員持ち株制度は、会社オーナーの相続対策や事業承継対策にもなります。オーナーの同族株主以外の従業員に自社株を取得させることで、自社株評価額を減らし、後継者の税負担を減らすことができるからです。一般的には、株価が高ければ企業価値が高まるわけですが、一方で、後継オーナーに多額の税負担を課すことに繋がります。
一方で、デメリットもあります。従業員持ち株会から退会を希望する従業員が一時的に増えた場合、資金不足によって制度を維持できなくなる危機にさらされるだけでなく、経営難にも陥るおそれがあります。
また、仮に会社の業績が悪化して配当を下げざるをえない、または無配当とするしかない事態に陥ったときには、従業員のモチベーションを下げて、会社への不信感すら浮上してしまうおそれがあります。これは、前述した従業員の経営参画意識を醸成するメリットと表裏をなします。
社員持ち株制度に加盟する社員側のメリット・デメリット
社員側にとっては、自社株という資産形成の選択肢が増える大きなメリットがあります。銀行などの金融機関に預けていても、極めてわずかな金利しかえられない時代には、自社株の配当は魅力的な定期収入となります。特に従業員持ち株会が従業員の代わりに株式を保有する場合、株式投資というよりも貯蓄の性格が色濃くなります。
また、従業員の拠出金に加えて、会社が補助金(奨励金)を支給すると、より多くの株式を取得できるため、従業員の会社に対する忠誠心も増すでしょう。
しかし、会社が万が一、倒産した場合には、従業員は職場だけでなく株式という積立資産まで一度に喪失してしまう点は、社員持ち株制度のデメリット(潜在リスク)として挙げるべきでしょう。
また、証券取引所で取引する上場株式と異なり、時機を見極めてのトレードによってキャピタルゲインをえることができないため、株式投資の本来の醍醐味は従業員に与えられていません。
社員持ち株制度の導入フローと注意点
社員持ち株制度を導入する場合、それに伴い、従業員持ち株会を設立する場合がほとんどでしょう。
従業員持ち株会は、法人税の回避や設立コスト削減の側面から、法人ではなく「組合」とすることが一般的です。組合は権利義務の主体である法人格を持たないため、従業員の株式を代理で「保有」するわけではありません。組合が預かっている株式は、あくまで各従業員が保有している法的な取り扱いとなります。
組合であれば、商業登記や官公庁への届け出などの手続きを省略できるため、株式会社などに比べて簡易に設立できるメリットがあります。ただし、組合が預かる株式を優先配当株式などに変更する場合には、定款変更や商業登記変更など、一定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
組合としての従業員持ち株会の設立にあたっては、発起人を選出しなければなりません。この発起人は、設立後に理事長や理事・監事などに任命されうる候補者となります。自社株まわりの業務は一般に総務セクションの管轄となりますので、理事長候補には総務部長が就任することが多いです。
従業員持ち株会の参加資格に関するルールも、あらかじめ明確に決めておくと、後のトラブルを回避できます。参加資格を一定の勤続年数以上の従業員に限ることで、新入社員の離職を減らし、会社への定着を促すことができると期待されます。
パート、アルバイト、派遣社員などの非正規従業員は、参加資格を与えない運用が一般的ですが、正社員とほぼ同等の勤務実態があれば、参加資格を与えたほうが全体の公平性を保てます。
取締役については、従業員持ち株会とは別に、役員持ち株会を組織することもあります。役員に自社株を購入させるときは奨励金(補助金)の支給ができないためです。
まとめ
社員持ち株制度(従業員持ち株制度)には、会社と従業員の双方にメリットがあります。しかし、デメリットやリスクも存在することを忘れずに意識して運用する必要があるでしょう。従業員持ち株会を立ち上げる際には、会社とは別組織の「組合」となり、設立や運用上の注意点があります。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
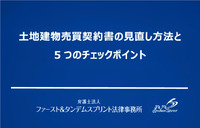
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -
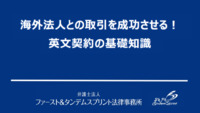
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

「人事給与アウトソーシング(BPO)サービス」導⼊事例集【三菱総研DCS】
おすすめ資料 -
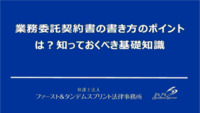
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

食の福利厚生【OFFICE DE YASAI 】
おすすめ資料 -
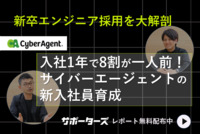
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース -

若い世代が職場で直面する差別や偏見とは?
ニュース -

電車通勤のメリットとデメリット 株式会社ビズヒッツ調べ
ニュース -
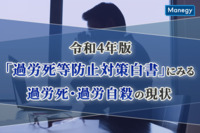
「令和4年版 過労死等防止対策白書」にみる過労死・過労自殺の現状
ニュース