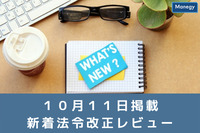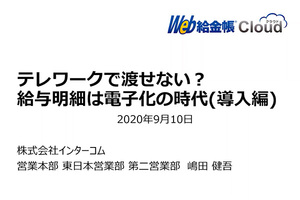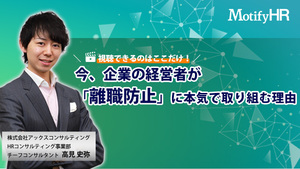公開日 /-create_datetime-/
認知度と評価が高まる育児・介護休業法の改正、全体の8割が働き方の変化に期待

少子高齢化が大きな問題になっている日本では、仕事と育児や介護とを両立させることが、国を挙げて緊急のテーマになっています。そのために制定されたのが「育児・介護休業法」であり、これまでに一定の成果を上げてきました。
その育児・介護休業法が改正・施行されたことに伴い、民間調査機関が一般企業の社員に対して意識調査を行いました。この記事では調査結果の概要と、育児・介護休業法の仕組みおよび今回の改正点について解説します。
育児・介護休業法のあらまし
育児・介護休業法とは、男女が共に仕事と家庭を両立することを支援する法律です。対象は正規雇用と非正規雇用とを問わず、勤務先に規定が整備されていなくても法によって休業が保証されます。
育児・介護休業法は、以下に挙げる四つの制度により構成されています。
・育児休業制度:1歳未満の子どもがいる両親がそれぞれに休業できる制度
・介護休業制度:要介護状態の家族を介護する場合に休業できる制度
・子の看護休暇:未就学児の病気やケガなどで看護が必要な場合に休業できる制度
・介護休暇制度:要介護状態の家族を介護するために短期的な休業を取得できる制度
この制度では、休業中に勤務先から給与が支払われない場合でも、要件を満たしていれば雇用保険の適用により、育児休業給付金などを受け取れます。詳細は厚生労働省のホームページなどで確認してください。
育児・介護休業法の改正ポイント
改正後の育児・介護休業法は、2022年4月1日から段階的に施行されています。ではどこが変わったのか、厚生労働省のガイドラインの要点をまとめて紹介します。
今回の改正の目的は、育児休業などを取得しやすい環境を作ることと、父親の育児参加を促すこと、さらに今までよりも休業の仕組みを柔軟にすることです。
まず事業主は、主に育児休業に関して職場での周知を促し、対象者がいつでも相談できる体制を整備する必要があります。その上で可能なら研修なども実施して、保険や休業給付などについてもアドバイスできる仕組みを整えなければなりません。
父親の育児参加に関しては「産後パパ育休」が新しく創設され、さらに育児休業の分割取得が認められます。また、契約社員・パート・アルバイトのような有期雇用社員についても、休業の取得条件が緩和されて、育児休業などが取りやすくなります。
育児・介護休業法に関する意識調査の概要
さて、こうして利用者に一歩歩み寄った育児・介護休業法は、社会人にはどのように受け止められているのでしょうか。今回の意識調査から、企業の人事・総務担当者と、配偶者が出産予定の会社員という、二つの異なった立場の意見を紹介しましょう。
調査概要:「育児・介護休業法の改正」に関する調査
調査期間:2022年8月9日(火)〜2022年8月10日(水)
調査方法:インターネット調査
調査人数:1,048人(企業の人事・総務担当者:506人/配偶者が出産予定の会社員:542人)
調査対象:企業の人事・総務担当者/配偶者が出産予定の会社員
モニター提供元:ゼネラルリサーチ
●今回の改正について
改正をすでに知っていて、内容まで把握している人は全体の約50%、内容までは知らない人は約38%でした。また改正の内容を高く評価する人は約28%で、ある程度評価する人は約59%でした。全体のおよそ9割が改正について知っており、しかも評価しているという予想を超えた結果になっています。
●今後の働き方の変化について
育児・介護休業法が改正されたことで、職場での働き方が大きく変化するという回答は約27%、多少は変化するという回答が約55%で、8割以上はなんらかの変化が現れると期待しているようです。
●人事・総務担当者への質問
改正への対応が迫られる担当者に対する質問では、職場での対応がすでに進んでいると答えた人が約74%を占めました。具体的に対応が必要な業務については、「就業規則の変更」や「社内制度の整備」などが挙げられています。
一方で懸念されることとしては、「業務全体への影響」「独身者の理解が得られない」「高齢男性の理解度が低い」などの意見が目立ちました。
●配偶者が出産予定の会社員への質問
最後に、実際に配偶者が出産予定の会社員への質問を見てみると、今回の改正による効果について期待しているという答えは、全体の約67%におよびました。また、育児休業を利用するかどうかについては、80%を超える人が前向きな回答をしています。
ただし職種や業種、企業規模によっては、利用が難しいという意見も寄せられています。
まとめ
男性の育児休業取得率は、2011年の調査ではわずか2.63%でした。それから10年を経て、2021年には13.97%にまで上昇しています。しかし2025年までには30%を達成するという政府の目標とはまだ開きがあります。今後、育児・介護休業法の改正が、どの程度効果を発揮するのかについて注目する必要があるでしょう。
今回の意識調査では、育児・介護休業法の改正に期待する人の割合がかなり高いことがわかりました。その期待に応えるためにも、各企業や事業所には制度を活用する仕組み作りが求められます。また社会全体で、仕事と育児・介護を両立できるような環境を整備することも、安心して生活できる将来のために今進めておくべきことではないでしょうか。
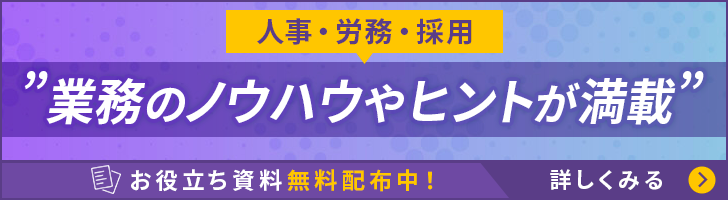
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
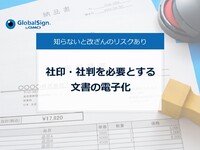
社印・社判を必要とする文書の電子化
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -
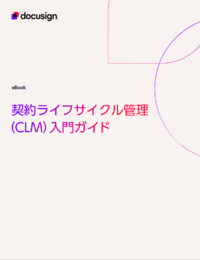
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -
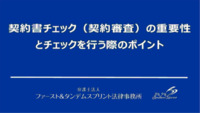
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -
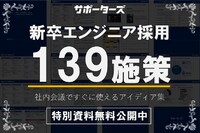
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
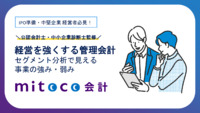
経営を強くする管理会計 セグメント分析で見える事業の強み・弱み
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -
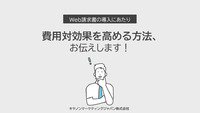
Web請求書の導入にあたり費用対効果を高める方法、お伝えします!
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

コロナで変わった人事現場の実態 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース