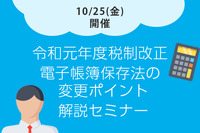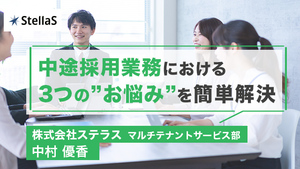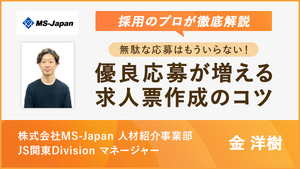公開日 /-create_datetime-/
パワハラ実態調査発表! 被害者の割合や対応、防止措置の効果は?
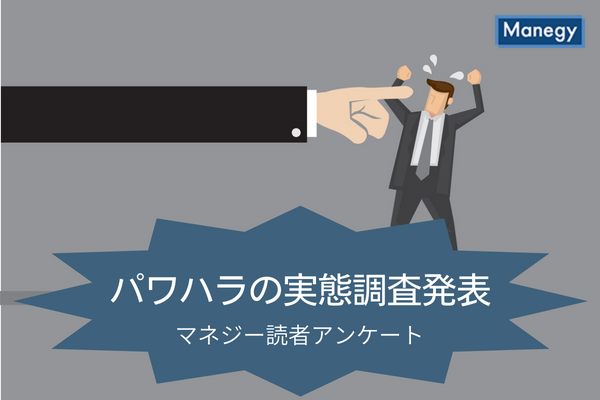
今年(2022年)4月、「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が中小企業も含めて完全義務化されました。
パワハラ防止法は2020年6月に大企業が先行して施行されています。
※詳細は厚生労働省の公式資料「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」をご確認ください。
人事・総務担当者にとって、自社のパワハラ防止対策は重要な業務です。
そこで「マネジー」では、パワハラ被害者の割合やどのようなパワハラを受けたかとその対応、各企業の取り組みに関する読者アンケートを実施しました。
本記事でその結果をご紹介します。
調査概要
「マネジー」パワハラに関する読者アンケート
調査期間:2022年8月19日~8月26日
有効回答数:493名
調査対象:当社運営メディアに登録中の20代~60代の管理部門・士業に従事する男女
調査方法:インターネット調査
パワハラの被害者は過半数以上! 泣き寝入り派が多数
最初は、回答者自身がパワハラを受けたことがあるかを尋ねました。結果は以下のとおりです。

上記のとおり、過半数の人がパワハラを受けたことがあるのが分かりました。
パワハラは、誰の身にも起こりえます。加害者が意識せず、指導や冗談のつもりで行っていても、受ける側の心身に悪影響を与えることであれば、ハラスメント(嫌がらせ)になるのです。「はい」が半数以上という結果から、意識的な加害行為はもちろん、加害者の“無自覚な”言動や職場全体の認識の甘さなどが原因となっている可能性が考えられるでしょう。
2問目は、1問目で「はい」と回答した人に対し、どのようなハラスメントを受けたかを尋ねました(複数回答可)。
・身体的な攻撃…4.9%
・精神的な攻撃…45.2%
・人間関係からの切り離し…10.8%
・過大な要求…21.9%
・過小な要求…4.5%
・個の侵害…11.6%
最多回答は「精神的な攻撃」で半数近く。「身体的な攻撃」よりも表面化しにくい「精神的な攻撃」は、さまざまなハラスメントのなかでも起こりやすく、認識が甘い人なら誰でも加害者になることが表れた結果と言えるでしょう。
また「過大な要求」と「過小な要求」は、上司から部下への行為というパターンが多いことが予想されます。特に「過大な要求」は、業務過多や能力以上の業務を強制するといった達成困難な要求により、心身の不調に繋がりやすくなります。
3問目は、パワハラに対してどのように対応したかを聞きました(複数回答可)。
・自身の意思を相手に直接伝える…9.7%
・相談窓口に相談…6.3%
・上司、またはそれに該当する方にパワハラ行為を相談…10.8%
・部署移動、または転勤を要求…5.1%
・休職…3.7%
・退職…15.4%
・何も行動していない…20.5%
最も多かったのは「何も行動していない」、いわゆる“泣き寝入り”で5人に1人が該当します。次に多かった「退職」も“泣き寝入り”になるので、被害者の多くは我慢していることが分かりました。
また、本来は強い味方になるはずの「相談窓口」は、利用者がごくわずかという結果に。人事・総務担当者は自社の課題として、相談窓口の設置・有効化に取り組む必要がありそうです。
パワハラ防止措置で効果を発揮しているのは少数派
4問目は回答者全員に向けて、自社や所属組織はパワハラ防止措置を講じているかを質問しました。結果は以下のとおりです。

上記のとおり、半数以上が「はい」ですが、まだ対応していない企業も多いのが判明しました。
パワハラ防止法には企業が行うべき措置が明示されており、それらは全て義務です。3問目で「相談窓口に相談」をあげた人が少なかったのも、そもそも自社に相談窓口がないということかもしれません。
最後の5問目は、4問目を踏まえて「パワハラ防止措置は効果を発揮していますか?」と尋ねました。

結果は、過半数が“効果あり”と答えていますが、効果を感じていない企業も多いようです。特に、今年4月から取り組み始めたばかりの中小企業は、対応を強化・改善していくことで効果が表れ始める可能性があるでしょう。
いかがでしたか?
本調査では、パワハラの被害者は多い一方で、有効な措置をとっている企業は十分でない現状が見えてきました。パワハラを防止するためには、企業や組織が全ての従業員に「パワハラ=悪」と明確に周知させる必要があります。そして、パワハラ防止措置を効果的に機能させるためには、人事・総務担当者がその内容をしっかりと理解して、安心して働ける環境づくりを進めなければなりません。
なお、「マネジー」および「マネジーtoB」ではパワハラ防止などに役立つ記事をご紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。
重要な法令関連の情報をココからまとめてチェック

おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -
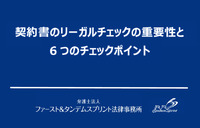
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -
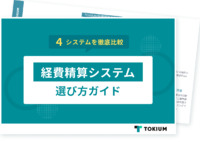
失敗しない!法対応と業務効率化を実現する経費精算システム選び方ガイド【4社の比較表付き】
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -
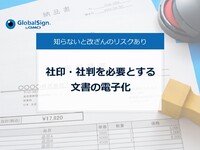
社印・社判を必要とする文書の電子化
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

テスト記事
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -
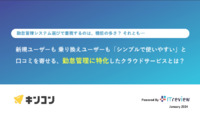
新規ユーザーも 乗り換えユーザーも「シンプルで使いやすい」と 口コミを寄せる、勤怠管理に特化したクラウドサービスとは?
おすすめ資料 -
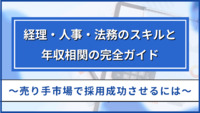
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -
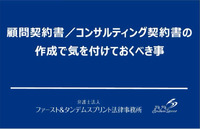
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース