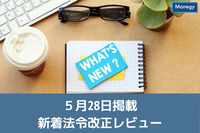公開日 /-create_datetime-/
再編後の東証で経過措置による問題が浮上、上場基準の達成に期限設定の可能性も

東京証券取引所(東証)は、2013年以来続いていた市場区分を改め、2022年4月4日より新たな区分で再スタートを切りました。その目的は、さらなる国際化への対応と、投資マネーが集まりやすくなる環境づくりです。
ところが、いざ新体制で臨んでみると、新規区分へ移行する上での経過措置に問題があることが明らかになりました。
この記事では、経過措置が抱える問題点、市場区分見直しの意味と今後の展開について解説します。
東証市場区分見直しの背景
見直し前の東証市場区分は、「市場第一部」「市場第二部」「マザーズ」「JASDAQ」の四つでした。しかし、この区分は根本的に、市場の線引きがあいまいになるという問題を抱えていました。
日本取引所グループ(JPX)も認めていることですが、まず市場第一部でさえコンセプトが不明確であり、その他の3市場にも重複部分があり、全体的に区分が不明瞭な点が指摘されていました。
また、新規上場基準に比べて上場廃止基準が大幅に低く、ほかの市場から市場第一部への再上場基準が緩やかだったため、上場した企業が積極的に企業価値を高めるような仕組みになっていませんでした。このような課題を解消するために、東証では新たな市場区分への再編を決めたのです。
新たな市場区分
東証の新たな市場区分は、「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」という3層構造になりました。今回の区分では、株式の流動性や時価総額などの企業経営基準に加え、収益基盤や資産など、経営・財政状況の指標になる基準が大幅に見直されています。
上場した企業は、活動状況(事業の流動性)をチェックされるほか、企業価値の向上に努めながら持続的な成長を目指すことが義務づけられます。ただし、より幅広い企業に上場の機会を提供するため、グロース市場ではほかの市場よりも上場基準がかなり緩和されています。
浮かび上がった「経過措置」の問題
ある組織が構造や体制を変更する場合には、一定期間の経過措置を設定することがあります。これは急激な改変により、組織の維持に大きな混乱が生じないようにするためです。
今回の市場再編でも、円滑な移行を図るために経過措置が設けられました。ところが、このことが予想外の問題を引き起こしたのです。
●市場第一部を維持したい大手企業
日本国内の大手企業にとって、東証一部上場というステータスは、一度手に入れると手放せない企業価値となります。今回の再編により、市場第一部は実質的にプライム市場に移行しました。しかし上場基準が変わったことで、現状ではその基準を満たせない大手企業も出ています。場合によっては、スタンダード市場で上場せざるを得ない状況も発生するでしょう。
こうしたケースを避ける目的で、東証では基準達成に向けた計画書の提出があれば、現在基準を満たしていない企業でも、希望する市場区分への上場を認めるという経過措置を導入しました。
●期限設定のない経過措置
今回問題になっているのは、東証が設定した経過措置に期限がなかったことです。そのため、中には基準達成まで10年という計画書を提出した企業もあります。さらに全体では、プライム市場に移行したおよそ1,800社のうち、約300社が現状で上場基準を満たしていないことも分かりました。
これでは、市場における企業価値を高めるという目標にはほど遠く、市場を活性化させるという重要な目的にも、出だしから黄信号が点灯してしまいます。こうした状況を改善するために、現在東証では証券会社、民間調査機関、研究者などを含めた有識者会議を開き、事態の打開策を探っています。
今後予測される市場再編の影響
5~6月時点では、市場再編による目立った効果はみられず、海外投資家による売りが買いを上回る「売り越し」の状態が続くなど、海外からの投資マネーを増やすという目標も大きく後退しています。
もう一つ注視すべきなのは、再編による東証株価指数(TOPIX)の動きです。東証では市場再編に続けて、2022年10月から2025年1月の期間で、TOPIXの構成銘柄を段階的に移行する予定です。事実上、この期間を経過措置と考えてもいいでしょう。
今後プライム市場の基準を満たせない企業は、TOPIXの銘柄からも徐々に外されていくため、株価の下落が生じるかもしれません。
再編が落ち着けば、各市場の企業は今までよりも企業価値を高める方向に動き、それが市場の活性化につながって、国内・国外からの投資マネーが増える可能性があります。東証および市場関係者の思惑通りに進んだ場合、東京証券取引所は以前よりも活況を呈することになるでしょう。
まとめ
以前の市場第一部の中には、プライム市場の基準を満たせずに、基準達成に向けた計画書を提出した企業があると同時に、基準を満たしながらもあえてスタンダード市場に上場した企業もあります。いずれにせよ、再びプライム市場が優良な企業の指標になるのは、これからの企業の取り組み次第ではないでしょうか。
ただし、再編後の現状をこのままにはしておけないため、上場先の市場を再考してもらうことや、各企業にいっそうの経営努力を求めることも必要になるでしょう。場合によっては、経過措置に期限を設けることが検討されるかもしれません。

おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

コロナで変わった人事現場の実態 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -
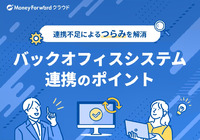
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -
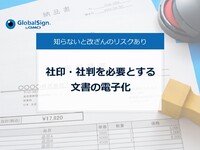
社印・社判を必要とする文書の電子化
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「人事部の実態と業務効率化」に関するサーベイ結果調査レポート【MURC&DCS共同制作】
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -
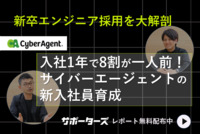
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース