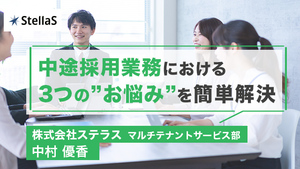公開日 /-create_datetime-/
20代~50代の男女のうち36.4%が「資産形成の余裕がない」

食料品や公共料金の値上げラッシュも、急激な円安も止まる気配がみられず、頼みの賃上げも値上げ幅に追いつかず、庶民の生活を容赦なく圧迫している。
給料が上がらないのであれば、支出をできるだけ抑える工夫が必要だが、それも限界がある。預貯金に余裕があれば、投資で資産を増やすこともできるが、それが可能なゆとりのある人は、果たしてどれだけいるのだろうか。
「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleapが、20代から50代の男女1,000名を対象に実施した「資産形成についての意識調査」によると、「資産形成をする貯蓄の余裕がない」と答えた人は36.4%であった。
年収別に資産形成をしている割合をみていくと、1,000万円以上は82.3%だが、300万円未満では50.5%にとどまっている。しかもこの資産形成には、株式や投資信託、不動産だけでなく、預貯金や生命保険、勤務先の積み立て・仮想通貨も含めての割合だ。
純粋な意味での投資に絞れば、投資で資産形成をする割合はさらに低くなる。年収300万円未満の世帯の86.9%が「資産形成に危機感がある」と回答しているが、投資に回したくても回す余裕がないというのが実態だ。
通常国会が閉幕したことを受けて開いた参院選前の記者会見では、岸田首相は「物価・賃金・生活総合対策本部」を立ち上げ、首相本人が先頭に立って迅速な対策に取り組み、「さまざまな社会課題を成長のエンジンに変えて持続可能で力強い成長を実現する」ことを表明した。
では、どのようにして「持続可能で力強い成長を実現する」のかといえば、企業が溜め込んだ320兆円ともいわれる内部留保や、個人が保有する1,100兆円近くの預貯金を分配・投資に回すという「資産所得倍増プラン」である。
当初掲げていた“所得倍増プラン”に、いつの間にか“資産”が組み込まれたようだが、本年度末までに総合的な「資産所得倍増プラン」を策定するようだ。
しかし、急激に進む円安や、長期化の様相を呈しているロシアによるウクライナへの軍事侵攻の影響など、日本経済にマイナス影響を及ぼす要素ばかりが目につき、しかも、これまでの値上げラッシュは序の口で、今秋以降に本格化するという観測もある。
そんなときに「貯蓄から投資へ」と呼びかけられても、果たして投資による資産運用へと動き出すのだろうか。しかも、投資にはリターンもあればリスクもある。投資を検討する前に、家計の支出を見直すなどの地道な節約を心がける方が確実かもしれない。
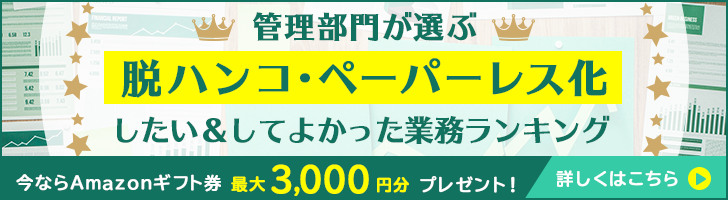
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
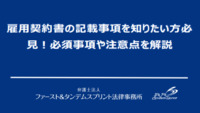
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -
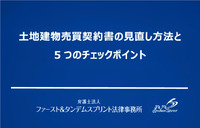
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

BillOneの導入で請求書業務はこう変わる
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -

「人事部の実態と業務効率化」に関するサーベイ結果調査レポート【MURC&DCS共同制作】
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース