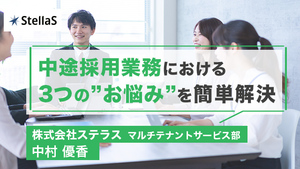公開日 /-create_datetime-/

近年、OSS(オープンソースソフトウェア)はIT業界における新たな潮流として注目を集めつつあります。しかし、プログラマーや開発者ではない人にとっては、実際のところOSSとは何か、どのような仕組みで運用されているのかについて、詳しくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、OSSとは何か、利用するメリット、デメリット・注意点について詳しく解説します。
OSS(オープンソースソフトウェア)とは
OSS(オープンソースソフトウェア)とは、ソフトの開発者がソースコードを無償で公開し、その利用はもちろん、内容の改変や再配布が自由に認められているソフトウェアのことです。
通常、ソフトウェアのソースコードはソフト作成者の知的財産となるので、利用にあたってはライセンス料の支払いが必要です。またその場合、当然ですがソースコードの改変は厳禁とされます。こうした一般的なソフトウェアのことは「プロプライエタリソフトウェア」と呼びます。いわばこれと真逆の特徴をもつのが、OSSであるわけです。
代表的なOSSとしては、プログラミング言語であるJAVAやPHP、OSのLinux、WebブラウザのFirefoxなどがあります。ITに詳しくない人でも、これらソフトウェアの名前は聞いたことはあるでしょう。実際、OSSは無償ではあるものの、クオリティが高く信頼でき、企業がOSSを使って事業活動を行うことも多いです。特に、プログラミングをする開発者にとっては、OSSは今や必須のシステムといえます。
OSSとライセンスの仕組み
OSSは無料で提供されていますが、全く自由に使用できるわけではありません。OSSの認定を行っている「OSI(The Open Source Initiative)」という組織がライセンスを管理し、利用にあたっての要件やルールを設定しています。
ソフトウェアがOSSとして認められるかどうかは、OSIが定めている10の定義に合致しているかどうかによります。定義は以下の10項目です。
・自由な再配布を認めること。
・ソースコードの無償配布を認めること。
・派生ソフトウェアの作成・配布を認めること。
・配布者が誰かわかるように、作者オリジナルのソースコードを判明可能にすること。なお、パッチファイルの配布を許可している場合のみ、ソースコードの配布は制限可能。
・特定の個人・グループに差別を行わないこと。
・ソフトを使用する分野に対して差別を行わないこと。
・プログラムに関する権利は、プログラムの再配布者全員に平等に認められること。
・ライセンスについて、特定の製品にだけ有効となるような制限を設けないこと。
・ライセンスについて、他のソフトウェアに制限を設けないこと。
・ライセンスについて、特定の技術に依存するようなルールを設けないこと(中立性の確保)
以上の10項目に当てはまるライセンスをもつソフトウェアであれば、OSIによりOSSと認可されます。
OSS(オープンソースソフトウェア)のメリットとデメリット
では、OSSを利用する場合、どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか。
●OSS(オープンソースソフトウェア)のメリット
OSSを利用する大きなメリットが、無料でソースコードを使用できる点です。通常のソフトウェアの場合だとライセンス料が発生しますが、OSSであればそのようなコストは発生しません。費用を抑えてソフトウェアを利用したいときは便利です。
また、ソースコードが公開されているので、プログラム上に問題が見つかっても、すぐに修正可能です。たとえばプログラム中にバグが見つかった場合、誰でも自由にすぐに修正できるので、この意味ではセキュリティ面でも安心できるソフトウェアが多いといえます。
さらに、一般的なソフトウェアの場合、権利をもつ企業が倒産したり、他の企業によって吸収合併されたりした場合、それ以降のサポートを受けられない可能性もあります。一方、OSSであれば、開発者ではなくコミュニティによってプログラム上必要な改変が行われるので、急にソフトウェアが使えなくなるといった事態は基本的に起こりません。
●OSS(オープンソースソフトウェア)のデメリット・注意点
OSSのデメリットの一つに、ソフトウェアの利用にあたって手厚いサポートが受けられない点があります。
ライセンス料を取ってソフトウェアを提供している企業の場合、使用する側はコスト負担こそ発生しますが、一般的にはその対価に見合ったアフターサポートを受けることができます。特に、ソフトウェアの運用に慣れていない企業・人にとっては、そのような支援体制の有無が重要になる場合が少なくありません。
しかしOSSでは、中には一定のサポートを提供するケースもあるようですが、基本的にはライセンス料を取っている開発者ほどのアフターサポートは受けられません。もしOSSを活用する場合は、サポートのみを当てにするのではなく、技術者同士の横の連携で情報共有することも重要になってきます。
また、OSSだからといって利用上に制約が全くないわけではないので注意が必要です。無償で提供はされますが、ソフトウェアの著作権者は存在し、利用にあたって一定の制約を課していることもあります。
たとえば、OSSでは「コピーレフト型」のライセンス形態をとっていることが多いです。コピーレフト型のラインセンスとは、OSSを利用して作られたプロダクトについても、OSSと同じ条件で配布しなければならない、とするルールのことです。この条項が付いている場合は、それに従う必要があります。
まとめ
OSSとは、ソフトの開発者がソースコードを無償で公開し、その利用、内容の改変、再配布が自由に認められているソフトウェアです。OSSの利用には無償利用できる、必要な修正をいつでも行える、開発者に倒産などの事態が起こっても継続利用できる、などのメリットがあります。一方、利用にあたって手厚いサポートはあまり期待できないこと、無償とはいえ制約なしで利用できるわけではないこと、といったデメリット・注意点があります。理解を深めた上で、上手に利用することがおすすめです。
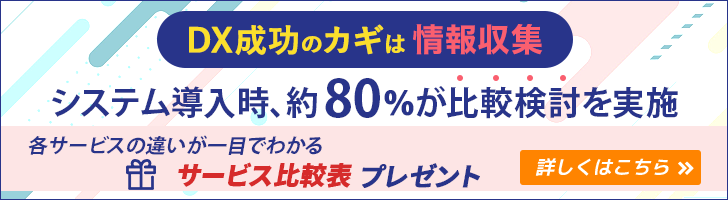
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -
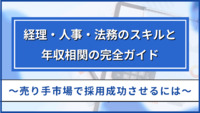
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -
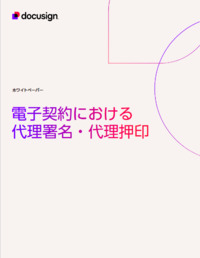
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -

電子署名の適法性 ~日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性~
おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
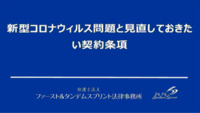
新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -
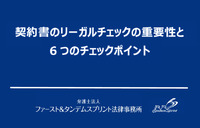
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -
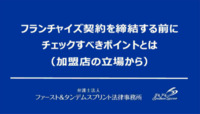
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -
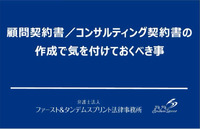
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

「人事給与アウトソーシング(BPO)サービス」導⼊事例集【三菱総研DCS】
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース