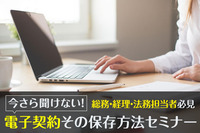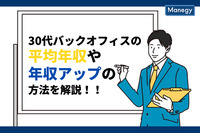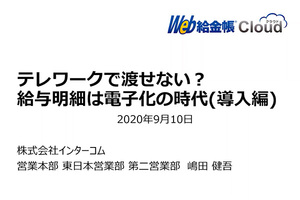公開日 /-create_datetime-/
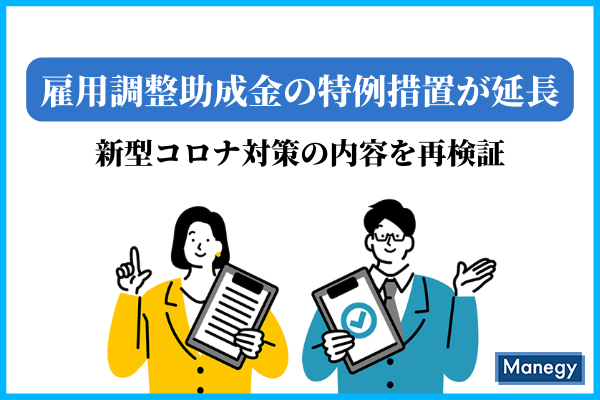
令和2年4月1日から令和4年6月30日までの期限付きで、新型コロナウィルス問題への対応策として、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
現在期限が近づきつつあるこの特例措置ですが、新型コロナ問題解決の見通しが立たないことから、政府は8月末までの延長を検討しているようです。雇用を守るための重要な制度である雇用調整助成金について、この記事で具体的な内容をあらためて検証してみましょう。
そもそも雇用調整助成金制度とは?
雇用調整助成金制度は、新型コロナウィルス問題以前から施行されており、とくに経営上の問題で事業規模の縮小に迫られている事業主を支援し、雇用の維持を図ることを目的にしています。
条件としては、事業主が従業員の雇用を維持するために、休業・教育訓練・出向などの雇用調整を行う必要があります。さらにその他の受給要件を満たした場合に、休業手当などに該当する費用が支給される仕組みです。
新型コロナウィルス問題対策としての特例措置
新型コロナウィルス問題で経営が悪化する企業が増える中、令和2年4月から雇用調整助成金には特例措置が設けられています。いわば緊急事態とも言える現状で、一時的に制度の条件を緩和することにより、雇用維持の強化を図るねらいです。
本来は、新型コロナウィルス問題の解決を前提に、徐々に特例措置も縮小される予定でしたが、依然として出口が見えない現状を考慮して、政府は延長の協議に入ったものと考えられます。
特例措置の主なポイント
雇用調整助成金の活用を検討中なら、通常枠で申請するよりも、特例措置の枠で申請したほうが有利です。では通常枠と特例措置では内容にどのような違いがあるのか、その主なポイントを解説しておきましょう。
●助成率の引き上げ
支給される助成金の助成率は、通常枠では中小企業が3分の2で、大企業では2分の1です。これが特例措置では中小企業が5分の4、大企業は3分の2へと引き上げられています。条件によっては、10分の10の全額給付になる可能性もあります。
●上限額の引き上げ
通常枠での1日1人あたりの支給上限額は、申請期間にかかわらず8,265円です。特例措置では当初13,500円でしたが、令和4年3月からは9,000円に引き下げられています。しかし業況特例と地域特例に該当している場合、支給上限額は15,000円となります。
●雇用保険の要件等緩和
雇用調整助成金は本来雇用保険の被保険者が対象ですが、特例措置ではこの条件が外されています。
●計画届要件の緩和
通常枠では、雇用調整などにかかわる複数の計画届を提出する必要があります。一方特例措置では、計画届を提出する義務はすべて不要になっています。
●生産指標要件の緩和
業績悪化の目安となる生産指標は、通常枠の場合3ヵ月で10%以上の売上高(生産高)減少が条件です。それが特例措置では1ヵ月で5%以上の減少に緩和されています。
特例措置が設けられた当初と比べると、支給上限額が減額されてはいます。しかし、その他の要件緩和は継続されているので、新型コロナ問題により経営が悪化したケースであれば、特例措置で申請することをおすすめします。
雇用調整助成金の申請にあたって
最後に、雇用調整助成金を申請する上での注意点を挙げておきます。まず現在実施されている特例措置とは、新型コロナ問題で経営が悪化している事業者が対象です。それ以外の理由によるケースでは、通常枠で申請することになります。
また、事業主が従業員の雇用を維持するために、労使間の協定に基づいた休業などの雇用調整を行っており、その上で休業手当を支払っていることも条件です。
こうした条件に当てはまる事業主のもとで、基本的には雇用保険の被保険者が助成金の対象になります。しかし今回の特例措置では、アルバイトなど雇用保険の被保険者以外でも、「緊急雇用安定助成金」の対象になるため、雇用調整助成金と同じ条件で支援が受けられます。
申請するにあたっては、計画届の提出は必要ないため、休業等の実施後に都道府県労働局かハローワークで手続きを行います。その後労働局の審査を経て支給が決まれば、雇用調整助成金が事業者に対して支給されます。
まとめ
新型コロナウィルス問題が解決されないまま、社会は徐々にコロナ前の状況に戻りつつあります。しかし飲食店や観光業をはじめ、いまだに多くの業種では本来の売り上げを回復できていません。雇用を維持できなくなった事業主と、仕事を失った人たちは依然として苦しい状況に置かれています。
このような現状を考慮して、今回雇用調整助成金の特例措置が延長されることになったと考えられます。新型コロナ問題で苦闘している方は、可能な限りこの制度を有効に活用したほうがよいでしょう。
原則として助成金には返済する義務がありません。まだ先が見えない今の社会状況では、国や自治体による継続的な支援が必要です。多くの人々の雇用を維持するためにも、雇用調整助成金が長期的に実施されるように、社会全体で見守ってゆくことが必要かもしれません。

おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
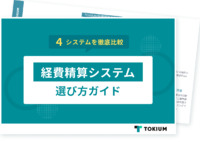
失敗しない!法対応と業務効率化を実現する経費精算システム選び方ガイド【4社の比較表付き】
おすすめ資料 -
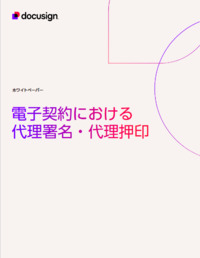
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -
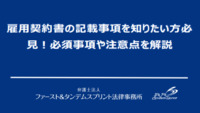
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
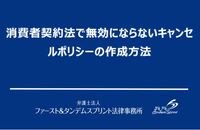
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -
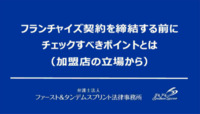
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

コロナで変わった人事現場の実態 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -
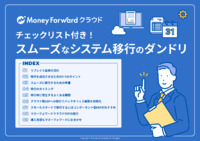
チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース