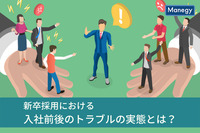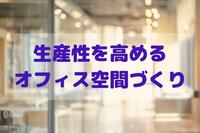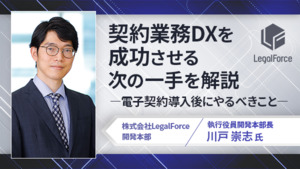公開日 /-create_datetime-/
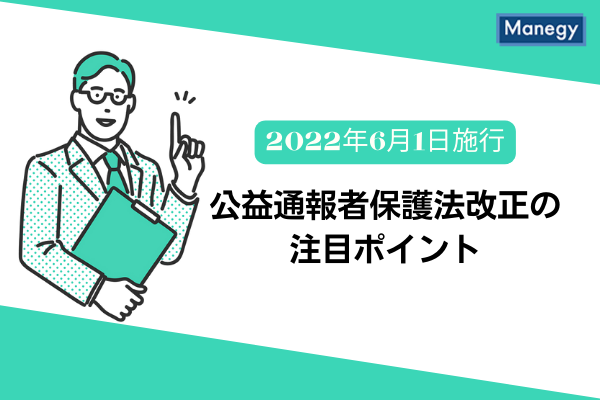
2006年(平成18年)に施行された公益通報者保護法が、2022年6月1日に改正公益通報者保護法として、再度施行されることになりました。この制度が抱えていた、いくつかの課題を解消することが目的だと考えられます。
今回の改正では、この法律の実効性を高める規定が盛り込まれています。かなり細かい措置まで付け加えられているため、この記事ではなるべく理解しやすく、今回の法改正の内容について解説します。
公益通報者保護法の制度概要
少しくだけた表現になってしまいますが、どの世界にも悪いことを考える人はいるものです。それが冗談で済まされるならまだしも、社会的に被害者が出るような事態になると、法律によって厳しく規制しなければなりません。
また、悪事をたくらむ者は、それを何とかして隠そうとします。たとえば企業内部で不祥事が起きた場合でも、それを幹部クラスが隠ぺいするような事件は、過去に何度も明るみに出てきました。
こうした事件は、内部通報者の協力で事実が判明することがあります。しかし通報者にとっては、自分が籍を置く企業ですから、もしも身元を特定されてしまうと、最悪の場合職を失うかもしれません。
公益通報者保護法とは、ひとことで言えば、こうした内部通報者の立場を保護する制度です。
公益通報者保護法改正の目的とは?
どのように優れた制度であっても、実行力を伴わないと本来の機能を発揮できません。公益通報者保護法でも、以前から実効性に関わる課題が指摘されていました。
実際にこの法律では、企業内に通報制度を設ける義務はなく、企業に対する制裁措置も規定されていませんでした。
そこで今回の改正では、今までの問題点を解決して実効性を高めるために、主に以下に挙げる三つのポイントが強化されます。
①事業者みずからの自浄作用を高める
②行政機関などへの通報をしやすくする
③通報者に対する保護を強化する
これら3本の柱を太くすることで、事業者がみずから不正を是正することと、内部通報者がより安全に保護されることが期待できます。これは事業者側にとっても、非常にメリットが大きい法改正だと言えるでしょう。
公益通報者保護法改正の主な内容
ある企業に在籍する者が、その企業の不正について内部から通報を行う場合、通報先によって二つのケースに分類されます。一つはその企業に直接通報する「内部通報」であり、もう1つは行政機関やマスコミなどに通報する「内部告発」です。
今回は、これら二つを含めた総合的な改正が行われますが、以下に主な改正点の概要をまとめてみます。尚、実際の法律では極めて難解な表現が使われているため、ここではなるべく理解しやすい表現にして解説しましょう。
●事業者に対する規制強化
従業員数が300人を超える事業者には、公益通報に対応する仕組みの整備と、担当責任者を指定することが義務づけられました。従わない場合には行政処分の対象になります。300人以下の事業者については、今回は努力義務にとどめられています。
また、公益通報の担当者には守秘義務が設けられ、第三者に対して自身の業務を明かしてしまうと、罰金の処分が科せられる場合もあります。
総じて言えるのは、事業者が今後みずから率先して、公益通報者保護法に基づいた体制を整えなければならないということでしょう。
●内部告発に関する要件緩和
この改正点は条文にすると非常に難しいのですが、要点だけに絞ると、内部告発をする通報者に対して、通報に必要な条件のハードルが下げられるのです。
その反面、事業者にとっては厳しい状況になると考えられるため、公益通報に対応する仕組みの整備を、積極的に進めることになると予想されます。
●公益通報者に対する保護の強化
改正前には在職中の従業員(役員は除く)のみが保護の対象でしたが、今回の改正により、退職後1年以内の元従業員と役員なども追加されました。保護対象者の範囲が広がったわけです。
さらに、改正前は刑事罰の対象になる不正行為のみ通報可能でしたが、改正後には行政罰の対象にまで範囲が拡大されます。これらの点も、事業者にとっては条件の厳格化と言えるでしょう。
事業者はどのように法改正に備えるべきか?
今回の法改正では、従業員数300人を目安に、規模が大きい事業者は法律への対応が義務化され、中小規模の事業者は努力義務という経過措置がとられることになりました。
ただし今後のことを考えると、事業者は規模の大小を問わず、内部通報を受け付ける窓口の設置や通報者の安全確保を、積極的に進める必要があるでしょう。同時に社内での教育や啓発活動も、継続的な取り組みとして実施しなければなりません。
まとめ
一般的に法律というものには、最初に見切り発車に近い状態で実施され、徐々に課題が積み重なってきた時点で、それを解消する法改正に踏み切るという傾向があります。
公益通報者保護法に関しても、同様の流れで今回内容が見直されることになりました。
この法律が施行された根本的な理由は、事業者がみずから不正を解決するための、自浄作用の向上にあったと考えられます。そのため事業者にとって今回の改正ポイントは、かなり厳しい条件が追加されたと感じられるでしょう。
しかし、見方を変えると今回の法改正によって、事業者による不正を予防する効果が格段に高まる可能性があります。事業者にとっても、不正が明るみに出た場合と比較すれば、それを未然に防ぐことには非常に大きなメリットがあるでしょう。
社会全体に対する影響を考慮しても、今回の公益通報者保護法改正には、極めて重要な意義があるのではないでしょうか。それぞれの事業者は、法改正の意味を充分に理解して、決して不正を許容することのない企業風土を再構築する必要があるでしょう。
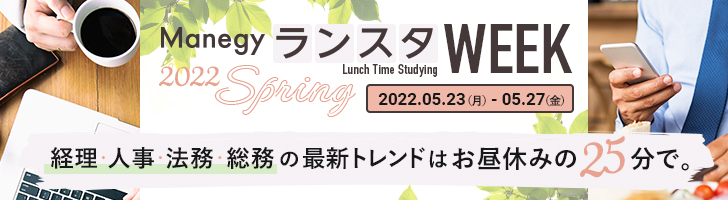
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

働く人の意識を変える定点観測
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -
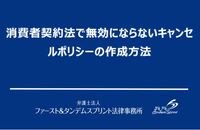
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -
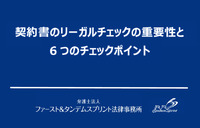
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -
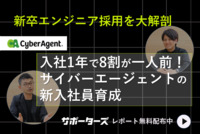
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -
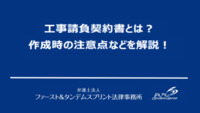
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -
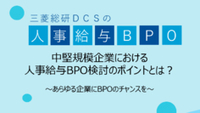
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース