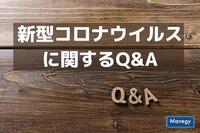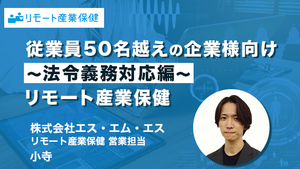公開日 /-create_datetime-/

ガソリン価格や小麦粉など、生活必需品や食料品の値上げが相次ぎ、2月の生鮮食品を除く消費者物価指数は、前年同月比0.6%増と7か月連続の上昇となり、このような状況が続くと、国民生活は一段と厳しくなりそうである。
そこで危惧されているのがインフレへの懸念である。三井住友DSアセットマネジメント株式会社が4月に発行したマーケットレポート「“インフレ”時代の到来? 最近の物価上昇の要因とは」によると、これからは“インフレと向き合う時代”と警鐘を鳴らしている。
レポートで示された物価上昇の要因は、コロナ禍での供給制約や経済再開に伴う需要増加による原材料価格の上昇、そしてウクライナ情勢の緊迫化が、原油や天然ガス、小麦をはじめとする穀物などの商品価格の上昇に拍車をかけていることだ。
さらに追い打ちをかけているのが、円安による輸入コストの増加だ。これまでは「有事の円買い」といわれてきた。しかし、ロシアのウクライナへの武力侵攻では、なぜか円が買われず、円ドル為替レートは115円付近の水準から、一時126円超となるなど、今年3月以降、急速に円安が進んでいる。
この円安によって、円建ての輸入コストは約9%上昇する計算になるというから、原油や天然ガスなどのエネルギーをはじめ、原材料の多くを輸入に頼る日本経済に及ばすマイナス影響は深刻となりそうだ。
こうした物価上昇が一時的なものであればいいのだが、ウクライナを巡る緊迫した情勢は長期化すると見られている。そうなれば、原油や天然ガスなどの価格は、当分は高止まりする可能性が高くなる。
ところで、欧米では景気が好調に推移しインフレ傾向にあるが、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)は、金融政策の量的緩和縮小と終了に舵を切っている。ところが日銀は、大規模な金融緩和を継続する姿勢を示している。
なぜ、有事なのに円が買われないのか。それは、金融政策の違いによるが、膨大な借金財政を抱えている日本は、利上げに踏み切ることもできない状態だ。つまり、インフレ懸念が現実味を帯びてきたというわけである。
物価上昇にスライドして賃金も上昇すればいいのだが、今年の賃金上昇率では、その期待を叶えることは難しく、消費行動を見直すなどの生活防衛策が必要なことだけは確かなようだ。

おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

「人事部の実態と業務効率化」に関するサーベイ結果調査レポート【MURC&DCS共同制作】
おすすめ資料 -

<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方
おすすめ資料 -
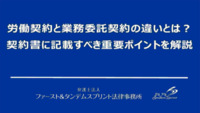
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -
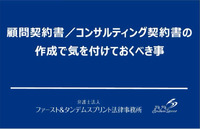
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -
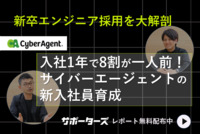
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース