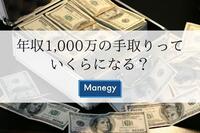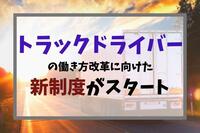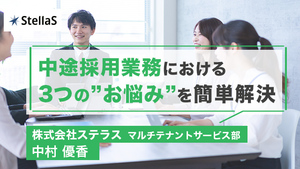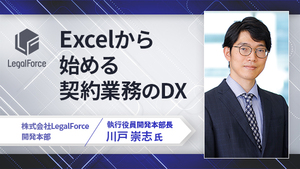公開日 /-create_datetime-/

多くの企業がICT(Information and Communication Technology)事業に関わるようになり、実体を持たないモノに対しても、発明や使用に関する保護の必要性が高まっています。これを実現する仕組みが「ビジネスモデル特許」です。
IoTやAIなどに使われる技術は、他者に流用されないように厳重に管理されなければなりません。この記事では、そのために規定されたビジネスモデル特許について解説します。
ビジネスモデル特許とは?
特許と聞くと、成功すれば巨万の富を築けるアイデア商品というイメージがあるでしょう。私たちの日常生活には、特許製品が無数に存在しています。例えば温水洗浄便座、お掃除ロボットのような家電製品から、カップ麺のような食品まで、誰もが知っている大ヒット商品の多くが特許を取得しています。
ところが、ビジネスモデル特許は一般的な特許とは異なり、実体化したモノではありません。これまでとは違った、新しいビジネスモデルが対象になるのです。ただし、ビジネスの仕組みや方法では特許を取得できません。アイデアそのものではなく、コンピューターを利用するようなビジネスの応用技術が対象になるのです。
ビジネスモデル特許の具体例
より分かりやすくするため、ビジネスモデル特許の具体例をいくつか挙げてみましょう。
現在広く一般的に経理システムなどで利用されている、パソコンなどで使う自動仕訳システムもビジネスモデル特許を取得しています。このシステムは、それまで人が手作業で行っていた会計業務を、クラウドコンピューティングによる会計処理のプログラムとして自動化しました。
また、ほとんどのECサイトが導入している注文方法の、いわゆるワンクリック注文もビジネスモデル特許を取得しています。これはインターネットで商品を注文する時に、購入者情報を登録しておけば、注文のたびに住所や決済方法を入力しなくても、ワンクリックで商品購入手続きが完了するシステムです。
こうしたビジネスモデルは、これまでにはなかった画期的な新システムですが、特許の対象になるのはそのアイデアや仕組みではなく、システムを稼働するための具体的な技術です。確かに目に見えるモノではありませんが、コンピューターの仮想空間上に実体があるモノという見方ができるかもしれません。
ビジネスモデル特許の動向
特許庁が公開しているデータによると、ビジネスモデル特許は「ビジネス関連発明」と表現されています。この分野の動向は、一般の特許に比べると非常に特徴的です。まずビジネス関連発明全体の出願件数では、2000年と2001年に一大ブームが巻き起こりました。この時の出願件数は、年間20,000件に迫る勢いでした。
ところがその後年々出願件数は減少し、2011年には5,000件をやっと超えるレベルにまで低下。そのまま下落が続くかと思われましたが、そこからは上昇傾向に転じて、2019年には再び10,000件を超えるまでに回復しています。
この背景にあるのは、近年のIoTやAI技術の進歩と、スマートフォンとそれに関連するアプリケーション開発の拡大だと考えられます。特にECやマーケティング、管理・経営、金融などの分野では、ここ数年でビジネスモデル特許の出願件数が急激に伸びています。
ビジネスモデル特許の認定要件
今後も社会構造の変化により、ビジネスモデル特許の出願が増加すると予測できますが、ビジネスモデル特許として認定されるためには、一般的な特許に加えて特別な要件が必要です。特に、これから挙げる三つの要件をクリアすることが重要なポイントになるでしょう。
●自然法則を利用した発明であること
特許法において特許権とは、自然法則を利用した発明であることと明記されています。そのため、単にバーチャル空間で動作するだけのソフトウェアでは、ビジネスモデル特許としては認められません。つまり、現実的にハードウェアのような資源を介して動作する発明であることが必要なのです。
●新規性があること
特許の対象としては当然ですが、同様の発明がすでに出願されている場合は承認が難しくなるでしょう。また、ソフトウェアのようなケースでは、リリース前に発明の内容が一部でも公開されてしまうと、新規性が失われたと判断される場合があります。
●進歩性があること
新規の発明に該当する場合でも、すでに広く普及した発明などをベースにしたものは、ビジネスモデル特許の対象から外れる可能性が高いでしょう。ほかに、別な分野の発明を参考にしたり、いくつかの既存の発明を組み合わせたりした場合も、進歩性なしと判断される確率が高くなります。
今後のビジネスモデル特許の展望
過去にさかのぼると、特許を取得してヒット商品を開発すれば、業界で一躍トップに躍り出ることも可能でした。しかし現在のビジネスモデル特許に関しては、それだけでビジネスを独占できるほどの武器にはなり得ません。
もう一つ注意すべき点は、ビジネスモデル特許の発明者と、その所属する企業との間でトラブルが生じる可能性です。ノーベル賞級の発明でも過去に事例があったように、発明者が正当な報酬を求めて、雇用先の企業と対立するケースがあるのです。今後は企業内でも、ビジネスモデル特許に関わる規定を明確にする必要があるでしょう。
まとめ
企業が独自に発明した技術は、特許権という形でその価値が厳重に保護されてきました。ただし、近年はビジネスの形態が変化したことにより、特許権も今までとは異なる対象に適用されるケースが増えています。
ビジネスモデル特許が、今後のビジネス界で重要な役目を果たすことは間違いないでしょう。しかし、それは過去の特許のように、市場に大きな影響力を与えるものにはならないかもしれません。企業としての独自性・独創性を保証し、ほかの企業との差別化を図るための手段、それがビジネスモデル特許の新たな可能性と言えるのではないでしょうか。
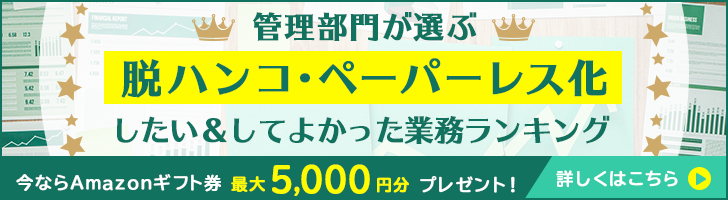
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

若手社員の早期離職を防止するためにできること
おすすめ資料 -
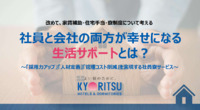
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -
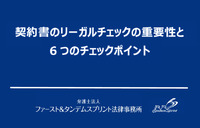
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -
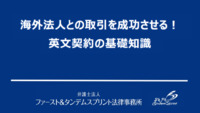
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -
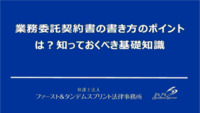
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -
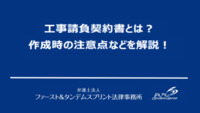
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース -

若い世代が職場で直面する差別や偏見とは?
ニュース -

電車通勤のメリットとデメリット 株式会社ビズヒッツ調べ
ニュース