公開日 /-create_datetime-/

ここ数年、住民生活や企業活動に支障をきたすような大きな自然災害が頻発している。しかし、被害を最小限に食い止めるためには、日ごろからハザードマップや避難場所の確認など、防災への備えをしておかなければならない。
いつ、襲ってくるからわからない自然災害から身を守るためには、住民同士が助け合う必要もある。つまり「自助・共助」という防災対策意識である。
そのためには住民一人ひとりが地域コミュニティに主体的にかかわることが大切だ。しかし、防災意識は住民によって大きな差があることが、日本損害保険協会が実施した「ハザードマップ等に関する住民意識調査」で明らかになった。
調査概要
調査目的:自助・共助にかかる住民意識を把握し、その結果を踏まえ、住民の防災・減災意識向上に繋げる施策に活かすこと
調査期間:2021年12月23日~2021年12月31日
調査方法:インターネット調査
調査対象:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
回答数 :4,011名
台風や地震などの自然災害には、ハザードマップでリスクの高いエリアや避難場所を確認しておく必要があるが、調査結果では「自宅周辺のハザードマップを見たことがあり、被害リスクを認識している」のは41.5%だった。
「別居の家族の自宅」や「勤務先等(日中過ごす地域)」の被害リスクをハザードマップで認識しているのは約17%と、自宅周辺に比べると大幅に低くなっている。
ハザードマップを見たことがない理由のトップは「どこで見ればいいか分からない」が39.5%で、ハザードマップをどこで確認すればいいのか分からないのが約4割にものぼる。
また、ハザードマップを見たことはあるものの、「情報量が多すぎる」「自分の地域は安全だと思う」「内容は忘れてしまった」など、被害リスクまでは認識していない割合がそれぞれ約30%となっている。
ところで、もし自治体から「避難指示」出た場合の行動は、ハザードマップの認知度が大きく影響していることもわかった。「ハザードマップの存在を知らない」人の半数以上は、「避難指示」が出た場合の行動を決めていないという。
さて、自分が居住する地域より、大幅に低いのが勤務地周辺のハザードマップの認知度だ。新社会人も入社してくる新年度を迎え、企業の防災担当者は、ハザードマップの確認や自然災害に襲われたときの社員の行動を、全社員にわかりやすく伝えておく必要がありそうだ。
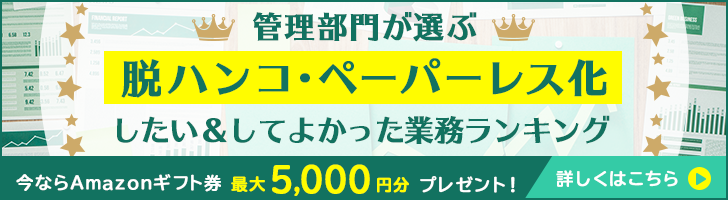
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

電子署名の適法性 ~日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性~
おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -

若手社員の早期離職を防止するためにできること
おすすめ資料 -
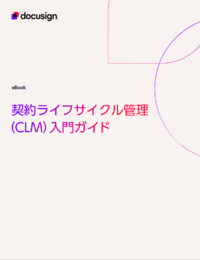
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -
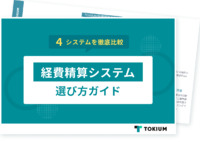
失敗しない!法対応と業務効率化を実現する経費精算システム選び方ガイド【4社の比較表付き】
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
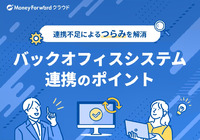
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -
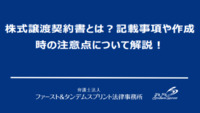
株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース
















