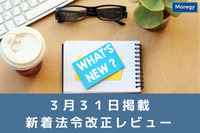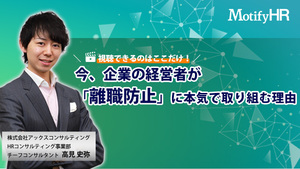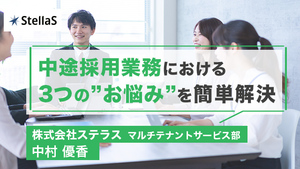公開日 /-create_datetime-/
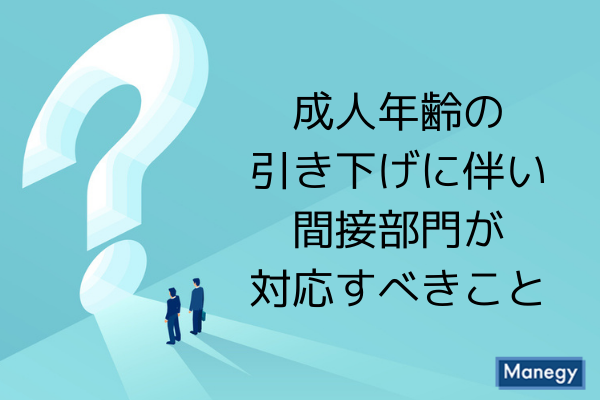
2022年4月1日、成人年齢が18歳に引き下げられます。18歳は成人として単独で契約行為が可能となるなど、重要な変更点があるのはご存知の通りです。
では、人事・労務担当者はどのような対応が必要となるのでしょうか?
今回は成人年齢18歳への引き下げに伴い、間接部門として対応すべき事項を整理します。
目次【本記事の内容】
労働基準法に関する影響
労働基準法における年齢の線引きには「年少者」と「未成年」の2種類があります。年少者はもともと18歳未満の者を指していたため、成人年齢が18歳に引き下げられても影響はありません。
一方で、未成年に相当する年齢が20歳未満から18歳未満へと変わることで、次に挙げる3つの影響が及ぶことになります。
●自己判断で労働契約を結べるようになる
これまで20歳未満の労働者を雇い入れる場合、親権者による同意を得る必要がありました。アルバイトスタッフを雇用する際、保護者が記載した「同意書」の提出を促すケースが典型です。
成人年齢が18歳に引き下げられることにより、18歳以上の者は保護者の同意を得ることなく自己判断で労働契約を結べるようになります。したがって、2022年4月1日以降は18歳以上であれば原則として同意書の提出を求める必要はありません。
●親権者・後見人による労働契約解除ができなくなる
未成年者は親権者や後見人といった保護者の監督下にあるため、労働契約が未成年者にとって不利と認められる場合は保護者による労働契約の解除が認められています。たとえば、子どもの就業先で労働条件が劣悪であるなどの理由により、親が労働契約解除を申し出ることができるのです。
2022年4月1日以降、未成年者は18歳未満となります。よって、18歳以上20歳未満の者は保護者が労働契約を解除できません。前述の通り、労働契約は労働者自身の意思で締結したことになるため、労働契約解除も本人の意思で行う必要があります。
●有給休暇の最低付与日数が12日から10日に
年次有給休暇の最低付与日数は10日ですが、未成年者に対してはこれを12日とする必要があります。未成年者を成人よりも手厚く保護するのが労働基準法の趣旨です。
成人年齢が18歳に引き下げられることで、18歳以上20歳未満の労働者も成人と見なされるようになります。つまり、年次有給休暇の最低付与日数も成人と同様10日となるのです。施行日以降に18歳以上20歳未満の労働者を雇用する場合は注意しましょう。
税金・年末調整に関する影響
税金・年末調整に関する影響として、源泉徴収票の「未成年者」欄への記入有無が挙げられます。従来、対象者が20歳未満であれば未成年者欄に〇印を記載していました。しかし、成人年齢が18歳に引き下げられることに伴い、対象者は18歳未満へと変更されます。
源泉徴収票をシステムで作成している場合は、未成年者の対象年齢が変更されているか確認を忘れないようにしましょう。とくに買い切り型のパッケージソフトを導入している場合、システムがアップデートされない可能性があるため注意が必要です。
民事訴訟法・労働審判に関する影響
訴訟能力については、民事訴訟法31条にて「未成年及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない」と規定されています。成人年齢が18歳に引き下げられることに伴い、今後特段の措置がなされない限り18歳から訴訟能力を有することになるのです。
よって、解雇や給料不払いなどのトラブルに伴う労働審判手続きの申し立てについても、18歳以上の労働者であれば可能となります。前述の通り18歳から労働契約を単独で結べるようになることと関連して、18歳以上20歳未満の労働者を独立した労働者として扱う必要があるのです。
その他の注意事項
ここまでに挙げてきたものは、間接部門として主に法令関連で対応が必要な事柄です。しかし、人事・総務部門の担当者としては従業員や新規採用者に対して他にも配慮しておくべき事柄があります。法令に関わる事柄以外に、間接部門として注意が必要な点を確認しておきましょう。
労働契約の当事者となることへの自覚を促す
18歳の労働者には高校生や大学生、専門学校生なども含まれます。従来は保護者による同意書の提出を促すことにより、保護者の監督下にある者として雇用していたはずです。しかし、成人年齢が18歳に引き下げられることにより、労働契約は労働者自身の判断で締結することとなります。
18歳以上20歳未満の新規採用者に対しては、労働契約の当事者となることへの自覚を促す必要があるでしょう。労働者自身が「まだ学生なので」といった意識で就業することのないよう、労働者としての自覚と責任をもつよう促すことが大切です。
飲酒・喫煙が可能な年齢は20歳以上であることに注意
成人年齢が18歳に引き下げられてからも、飲酒・喫煙が可能な年齢は従来通り20歳以上のままです。労働者本人だけでなく、周囲の従業員にも20歳未満は飲酒・喫煙が禁じられていることを周知徹底しておく必要があります。
とくに新規採用者の歓迎会をはじめ、会社行事を開催する際には注意が必要です。「18歳は成人」と誤解して飲酒を勧めるようなことがないよう、すべての従業員に注意を促しましょう。
まとめ
民法の改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられるのはおよそ140年ぶりのことです。法令上の規定に留まらず、長く続いてきた慣習の面においても当初は混乱することが予想されます。
今回紹介してきた各方面への影響に対して理解を深め、間接部門として適切に対処できるよう準備を整えていきましょう。
↓22年の法改正をまとめて確認できるのはこちら↓
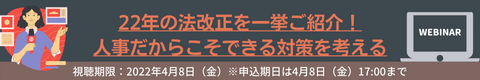
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -
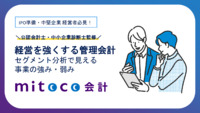
経営を強くする管理会計 セグメント分析で見える事業の強み・弱み
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -
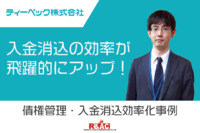
債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

三菱総研DCSが取り組む「ダイバーシティー経営」への第一歩
おすすめ資料 -
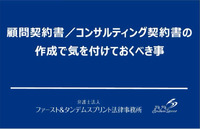
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -
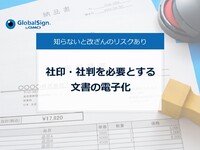
社印・社判を必要とする文書の電子化
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース