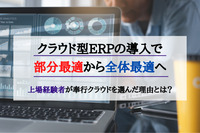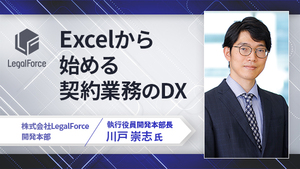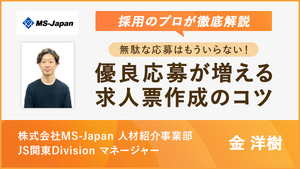公開日 /-create_datetime-/

新型コロナウィルスの感染拡大を受け、政府は2月15日に「まん延防止等重点措置」の調整をしました。具体的には北海道や福島、茨城、栃木、鹿児島の5道県の期限を延長する方向です。
他にも静岡や京都、大阪、兵庫はすでに延長の方針が固まっています。「まん延防止等重点措置」とは一体何なのでしょうか。また、国民や企業はどのようなことに気をつければよいのでしょうか。
目次【本記事の内容】
「まん延防止等重点措置」とは?
そもそも「まん延防止等重点措置って何?」と疑問に思っている人も多いでしょう。ここでは、まん延防止等重点措置の概要を解説します。
まん延防止等重点措置とは、その名前の通り、新型コロナウィルスのまん延を抑えるための取り組みです。デルタ株に代わって猛威を振るうオミクロン株の存在もあり、政府はよりいっそう感染防止の取り組みに力を入れているのです。
このような新しい変異株の流行や、生活様式の変化に対応できるよう、医療体制の強化やワクチン接種の促進が進められています。最近では以下のような実施期間、実施区域が指定されています。
・令和4年1月9日から令和4年2月20日まで:広島県、山口県、沖縄県
・令和4年1月21日から令和4年3月6日まで:群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県
・令和4年1月27日から令和4年2月20日まで:北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県
・令和4年2月5日から令和4年2月27日まで:和歌山県
・令和4年2月12日から令和4年3月6日まで:高知県
上記の期間や区域で、まん延防止等重点措置が実施されています。(感染状況により変更の可能性あり)
どうして「まん延防止等重点措置」が必要なの?
「そもそも何でウィルス感染を防止しなければならないの?」と考える人もいるかもしれません。
なぜ新型コロナウィルス感染症拡大を防止しなければならないかというと、緊急時の病床数を確保するためです。
2022年2月15日時点、東京都の病床使用率は、58.8%となっています。病床使用率とは、「新型コロナウィルスに感染した患者のための病床がどれだけ埋まっているか」を指します。
つまり病床使用率が高ければ高いほど、医療が逼迫している状態・「医療崩壊」のリスクが高い状態です。入院患者全体と重傷者の病床使用率が50%を超えた場合、緊急事態宣言発令の目安となる「ステージ4」となります。緊急事態宣言が発令されれば、国民の行動に強い制限を加えることになります。
新型コロナウィルス感染症に対する国民の意識が低ければ、感染が次々に広まっていき、いざという時に十分な医療を提供できません。まん延防止等重点措置を実施し、国民全体で感染拡大を抑える取り組みをすることで、緊急時の病床の確保につながります。
「まん延防止等重点措置」で実施されること①飲食店への要請
コロナ対策と言えば飲食店を思い浮かべる人も多いでしょう。飲食店ではマスクを外して食事をするため、感染リスクが非常に高いことで知られています。そのため、まん延防止等重点措置の実施では、飲食店にいくつかの要請をしているのです。
まん延防止等重点措置に指定された区域では、飲食店に対する営業時間の短縮、および酒類を提供しない旨の要請が実施されます。厳密には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項にもとづいたもので、都道府県知事の判断です。
また同法第24条第9項にもとづいて、「同一グループ・同一テーブルでの5人以上の会食」を避けるよう要請されます。
「まん延防止等重点措置」で実施されること②施設・イベントの制限
商業施設に行くと、「店内では必ずマスクを着用してください」などの掲示やアナウンスがよく見られます。まん延防止等重点措置では、飲食店への要請だけでなく、施設の管理も実施されます。具体的には以下の項目です。
・施設への入場制限
・入場をする人に対するマスク着用の周知
・感染防止対策をしない人に対する入場の禁止
・飛沫による感染防止対策(具体的には飛沫を遮るアクリル板の設置など)
こちらも飲食店の制限と同じく、都道府県知事の判断によって実施されます。
また施設だけでなくイベントの開催制限も重要です。たとえばサッカーの試合では、大きく入場が制限されており、「人と人との距離を確保する」よう呼びかけてられています。感染状況がひどい場合は、イベント中止や無観客で実施される場合もあります。
「まん延防止等重点措置」で実施されること③国民の生活への要請
国民の外出や移動、職場への出勤についても、いくつかの要請が実施されています。たとえば措置区域では、「営業時間の変更を要請した時間以降、みだりに飲食店に入るのは避けるのが望ましい」とされています。また飲食店だけでなく、混雑した場所や感染リスクが高い場所は、なるべく利用しないようがよいでしょう。
職場への出勤についても、時差出勤やテレワークなど、感染を抑えるための試みが推奨されています。とくにテレワークは、新型コロナウィルス感染拡大を契機に、広く普及しつつあります。
まとめ
まん延防止等重点措置は、新型コロナウィルス感染症拡大を抑えるための柱です。ただし強制力が高いわけではないため、国民一人ひとりが自覚を持って行動する必要があります。
自らの習慣を見直し、感染リスクを抑えるための生活を模索してみてはいかがでしょうか。

おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

経理BPO業務事例のご紹介
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
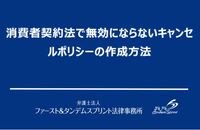
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

誰もが悩む5つの組織課題をサーベイ導入で解決するヒントとは?
おすすめ資料 -
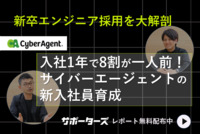
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -

電子署名の適法性 ~日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性~
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース