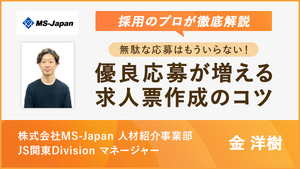公開日 /-create_datetime-/
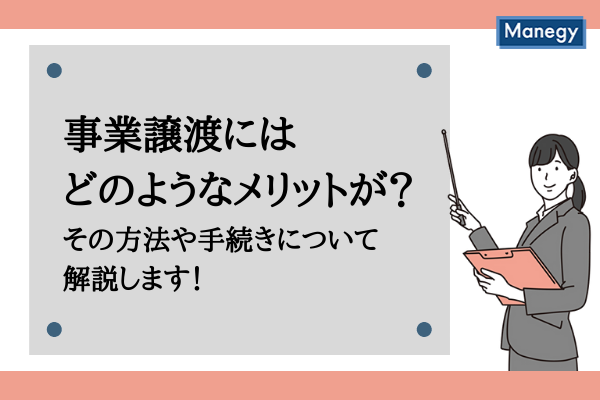
先日セブン&アイ・ホールディングス(以下、セブン&アイ)が、傘下の百貨店事業会社を売却する方向で最終調整に入ったと報道で取り上げられました。
この百貨店事業会社は「そごう」や「西武百貨店」を運営しており、2006年にセブン&アイの傘下に入っています。
せっかく取得した事業会社を、なぜ売却するのでしょうか?
また事業譲渡にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
今回は事業譲渡の概要や方法、メリットとデメリット、その進め方などについて解説します。
目次【本記事の内容】
事業譲渡とは?
事業譲渡とは、企業がある事業の全部または一部を、別の企業もしくは関連企業に譲り渡すことをいいます。
●事業譲渡と株式譲渡
事業譲渡と似ている意味合いに捉えられがちなのが、株式譲渡です。株式譲渡とは、売却対象企業の株主がもつ株式を、買収を希望する企業に譲渡し企業を売買することをいいます。事業譲渡との違いは、株式譲渡による売買は基本的に企業の全部、事業譲渡の場合は全部か一部を選べることです。M&Aの代表的な手法が事業譲渡、M&Aの中でも中小企業のM&Aでは株式譲渡がよく使われます。
●セブン&アイがそごうと西武を手放す理由
企業は、なぜ事業譲渡を行うのでしょうか?セブン&アイは2006年にそごうと西武を傘下に収めました。当時そごうと西武で運営していた全国28の百貨店が、近年では10店舗(そごう4店舗、西武6店舗)まで減少していました。セブン&アイは伸び悩む百貨店事業を整理し、主力であるコンビニエンスストア事業に経営資源を集中するために、そごうと西武(百貨店事業会社)を売却する予定だといわれています。
事業譲渡のメリット・デメリット
先述のように事業譲渡には、企業の全部か一部かを選択できる特徴があります。この特徴は株式譲渡や会社分割、合併などとは違ったメリットを事業譲渡に生み出すのです。ここでは事業譲渡のメリットとデメリットについて、売る側と買う側に分けて説明していきます。
●売る側のメリット
・売りたい事業を指定して売ることができる
企業全体ではなく譲渡したい事業だけを売ることができます。
・企業(全体)に負債がある場合でも譲渡の交渉がしやすい
企業自体に負債がある場合、株式譲渡などでは買い手が見つけにくくなります。事業譲渡であれば譲渡交渉がしやすくなります。
・事業を売却しても企業(全体)としては事業を継続できる
一つの事業を譲渡しても、他に事業があれば企業を存続していくことができます。
●売る側のデメリット
・売却益に法人税が発生する
事業譲渡で代金を受け取った場合には、法人税、住民税等の税金が発生します。繰越欠損金などがあれば損金として計上できます。しかし、譲渡金額すべてを受け取れるわけではないことは認識しておきましょう。
・譲渡完了まで時間がかかる
株式譲渡などに比べ、事業譲渡は完了までに時間がかかります。その理由は、事業譲渡の承諾を得るべき関係者が多いことです。
・債権者や株主、従業員に承諾を得る必要がある
事業譲渡を行う場合には、債権者や株主、取引先などに加え、従業員にも契約上の承諾を得る必要があります。
・競業避止義務が発生する
会社法21条の定めにより、売り手側は20年間、同一の市町村、隣接する市町村の区域内で譲渡した事業と同じ事業を行うことができません。これを競業避止義務といいます。
事業譲渡の進め方
最後に、事業譲渡の一般的な進め方(売る側)について解説しておきましょう。必ずしもこの流れに沿わなくてはならないというものではありません。しかし、現実の事業譲渡ではM&A専門の仲介会社などに相談することが多いので、ほとんどのケースではこのような流れで進むのだと覚えておきましょう。
●事業譲渡の検討開始
なんらかの理由によって事業譲渡の検討を開始します。この時点でM&A専門の仲介会社と秘密保持契約を結び、相談を開始します。
●ノンネームシート開示
ノンネームシートは企業を特定されない範囲の情報を簡易的にまとめたもので、契約した仲介会社が譲渡を受ける企業を探すために使われます。この時点で決算書の準備(三期分)も行っておきます。
●秘密保持契約書締結
相手が決定した時点で秘密保持契約を締結します。譲渡の詳細条件を相手に提示するためです。
●案件概要書(IM)の提示
IM(Information Memorandum)とは、譲渡する事業の情報が詳細に記載された資料です。相手企業はIMを元に、次のステップに進むべきか詳細検討を行います。
●トップ面談・基本合意書の締結
双方のトップが面談し、基本合意書の締結を行います。ただしまだこの時点では、譲渡決定ではありません。
●デューデリジェンスの実施
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、譲渡を受けるに当たってその事業の内容を精査し、価値の見極めや隠れたリスクがないか調査することをいいます。
●株主や関係者との合意
デューデリジェンスが終わり譲渡に問題がないと相手が判断すれば、売る側では株主や従業員など、関係者との合意を進めます。
●事業譲渡契約締結
双方とすべての関係者の合意が得られれば、事業譲渡契約を結びます。ここではじめて事業譲渡は決定となります。
●事業譲渡の実施
契約条件に従った譲渡金額の授受と、譲渡プロセスが開始されます。
まとめ
事業譲渡は、売る側の都合だけでは進みません。事業譲渡を受ける側にとって、その事業が魅力的であることが何よりも大切です。事業譲渡の際には、自社の事業を第三者的な目で精査し、判断(譲渡)のタイミングを間違えないことが肝要です。
経理担当者におすすめのセッションがたくさん!

おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -
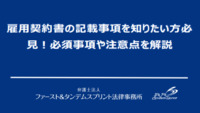
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

三菱総研DCSが取り組む「ダイバーシティー経営」への第一歩
おすすめ資料 -
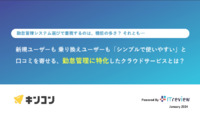
新規ユーザーも 乗り換えユーザーも「シンプルで使いやすい」と 口コミを寄せる、勤怠管理に特化したクラウドサービスとは?
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -
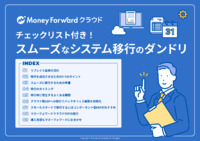
チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ
おすすめ資料 -

経理BPO業務事例のご紹介
おすすめ資料 -
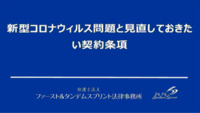
新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -
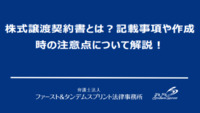
株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -
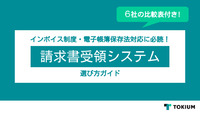
失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】
おすすめ資料 -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース -

若い世代が職場で直面する差別や偏見とは?
ニュース -

電車通勤のメリットとデメリット 株式会社ビズヒッツ調べ
ニュース -
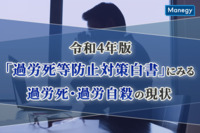
「令和4年版 過労死等防止対策白書」にみる過労死・過労自殺の現状
ニュース