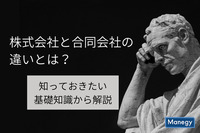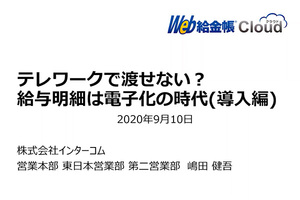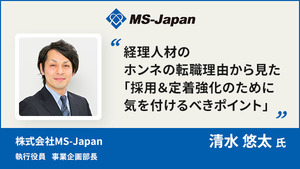公開日 /-create_datetime-/

現金給付か、現金+クーポンでの給付かで迷走を続けた新型コロナウイルスの18歳以下への支援策は、最終的に自治体の判断に任されることになりましたが、現金+クーポンを選択したのは、わずか7自治体だったことが明らかになりました。
莫大な事務費用がかかるクーポン給付
本来なら歓迎されるべき「10万円相当の給付」ですが、政府が示したのはまず現金で5万円を給付し、残りの5万円分を入学・進学シーズンの春にクーポンで配布するというものでした。
そもそも、この「10万円相当の給付」の目的は、コロナ禍の影響を受けた困窮世帯や学生、子育て世帯への支援でしたが、さらに消費喚起にもつなげたいという思惑が働いたようです。
ところが、クーポンを発行するためには967億円もの事務費用がかかることが明らかになったことと、所得制限を設けたことによる不公平感もあり物議を醸しました。
全国1,741自治体のうちわずか7自治体がクーポンを選択
最終的に、現金一括給付、5万円+5万円の現金給付、現金5万円+5万円分クーポン給付の3通りの給付方法を認め、自治体が給付方法を選択できるようになりました。
給付は昨年末から始まりましたが、1月14日の山際大志郎経済再生担当相の記者会見で、政府が当初示した「現金5万円+5万円相当のクーポン」給付を選択したのは、全国1,741自治体のうちわずか7自治体しかなかったことが明らかになりました。
ちなみに、全国自治体のおよそ8割にあたる1,402自治体が現金での一括給付を選択し、現金2回給付を選択したのは332自治体でした。
クーポン給付をするためには、印刷代をはじめ郵送費、問い合わせのためのコールセンターの設置など、現金一括給付よりもコストがかさみます。民間の事業会社であれば、現金一括給付にかかる事務費用約280億円と、クーポン給付にかかる事務費用967億円のどちらを選択するかは明らかではないでしょうか。
二兎負うものは一兎も得ず
なぜ、現金とクーポンでの給付にこだわったのでしょうか。その背景には、昨年の“1人一律10万円の現金給付”が、消費に回ったのはわずか3割程度で、多くが貯金に回ってしまい経済効果になかなかつながらなかったということがあるようです。
入学・進学シーズンの春に、文房具などをクーポンで購入できるようにしたかったようですが、そのために数倍の事務費用が余計にかかるのであれば、費用対効果から考えても疑問が生じてしまいます。
本来は支援策として打ち出されたものの、そこに経済対策を盛り込もうとしたことで混乱に拍車をかけることになりました。まさに“二兎負うものは一兎も得ず”のことわざが表すとおりになってしまいました。
まとめ
今回の10万円相当給付については、かなり事態は混乱したものの、結果的に7自治体のみが「現金+クーポン」を採用することになりました。自治体が、現金一括給付、現金+クーポン給付のどちらを採用するにしても、この政策を実行することによって、コロナ禍の影響を受けた困窮世帯や学生、子育て世帯への支援につながってほしいものです。
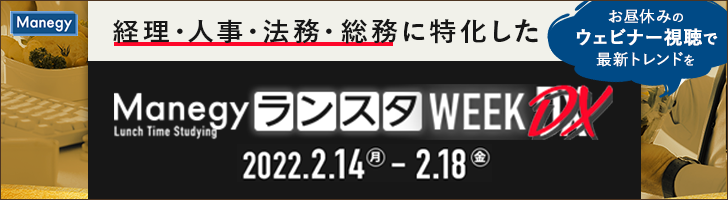
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

コロナで変わった人事現場の実態 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -

BillOneの導入で請求書業務はこう変わる
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース