公開日 /-create_datetime-/
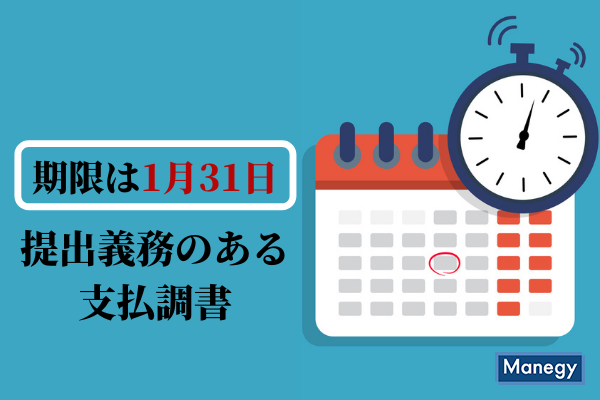
年明け早々、経理担当者が取り組むべき業務の一つが「支払調書」の作成と税務署への提出です。
提出期限は原則として1月31日ですので、すぐにでも取りかかる必要があります。ここであらためて支払調書についておさらいしておきましょう。
法律で提出が義務付けられた法定調書
企業には、法律で提出が義務付けられているさまざまな法定調書があります。その中の代表的な書類が、「給与所得の源泉徴収票」と、今回取り上げる支払調書になります。
源泉徴収票とは、従業員に支払った1年間の給与額を示す書類です。支払調書は企業が個人事業主やフリーランスへ支払った外部委託費額を示すものになります。
つまり、税務署が確定申告をする個人事業主やフリーランスの所得額を、正確に把握するために必要となる書類です。そこに記載されているのは、企業が法人や個人へ支払った外部委託費の額と、その内容になります。また、所得額に応じた所得税を、算出するために必要になります。
国税庁のホームページから書式がダウンロードできる
ここで、支払調書にはどのような記載項目があるのかを、あらためて確認しておきましょう。「支払を受ける者」「区分」「細目」「支払金額」「源泉徴収税額」「摘要」「支払者」の項目があります。
支払いを受ける者は、報酬(支払)を受け取った人のことで、そこには住所、氏名(名称)、個人番号(法人番号)を記入します。次に区分の項目を見ていきましょう。ここには、何の業務に、いくらの報酬を支払ったのかがわかるように記入します。
区分の項目に該当するのは弁護士報酬や税理士報酬、原稿料、翻訳料、講演料などです。たとえば顧問料以外に発生した弁護士報酬については、弁護士が関与した事件名も記入する必要がありますので注意しましょう。
また、「支払金額」の欄には、1月1日から12月31日の1年の間に支払いが確定した金額を記入します。
ここで注意すべき点が、実際に支払った金額だけではなく、支払日の関係でまだ支払われていないものの支払うことが確定している報酬額や、控除額以下のために源泉徴収を行わなかったものも含めて記入しなければなりません。
その場合、上段に未払額、下段に年度内の支払金額合計(消費税込)を記入します。支払調書の作成には、細かなルールもありますので、国税庁のホームページから、書式をダウンロードして活用することをおすすめします。
まとめ
支払調書を税務署へ提出する方法は、国税電子申告・納税システムのe-taxがあります。それを利用する際には、あらかじめ所轄の税務署に申請し承認を受ける必要があります。税務署まで足を運ばなくても提出できるので、経理担当者の業務負担を軽減するためにもデジタル化にチャレンジしてはいかがでしょうか。
支払調書を出し終わったら、2月は学びの時間を作ってみては?
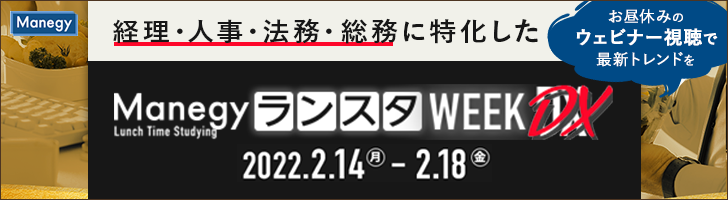
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

コロナで変わった人事現場の実態 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -
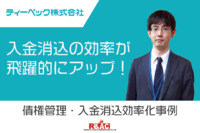
債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖
おすすめ資料 -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

経理は転職サイトを利用すべき?経理人材の転職市場での価値を解説!
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース
















