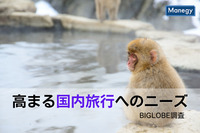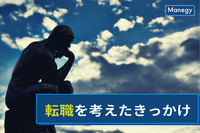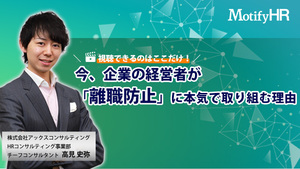公開日 /-create_datetime-/

記事転載元:ぱられる/株式会社コーナー
「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」
株式会社コーナーが運営する人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチング支援サービス。採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。
就職活動のスタンダードとなっているインターンシップ。しかし、2020年からの新型コロナウイルスの影響やテクノロジーの進化を受けて、インターンシップも従来の対面のみを前提とした手法から、オンラインなどを組み込んだ手法へと大きく変化してきている状態です。そのような中、各社工夫を重ねていますが、中には残念ながら思ったような成果につながっていない企業も少なくないようです。
そこで今回は大手人材サービス企業で新卒採用企画を経験し、人事制度やHRリスクマネジメントにも知見があるパラレルワーカーの方に、「オンラインインターンシップ」の現状や活用方法について話を伺いました。
新卒で大手人材サービス企業に入社、新卒採用部門に配属後、母集団形成~入社までの各選考プロセスにおける企画に従事。現在は別会社へ転籍し、人事企画部門にて人事制度の改定やHRリスクマネジメントの企画を担当。
▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次【本記事の内容】
「オンラインインターンシップ」とは
リモートワークの拡大に合わせて「オンラインインターンシップ」を取り入れる企業も増えてきました。改めてこの「オンラインインターンシップ」とはどういったものなのでしょうか?
「オンラインインターンシップ」を説明するために、まず従来実施されていたオフラインのインターンシップついて説明します。大きく分けると以下の2種類があります。
■(1)長期型:就業型インターンシップ
数か月~数年の長期間にわたってその会社に就業し、実在する業務を体験するインターンシップです。基本的には給与が支払われ、実際に入社した際とほぼ同じような実務経験を積むことができます。そのため企業側は学生の能力を把握しやすく、学生側も組織風土や仕事内容に対する理解が高まりやすいため、その後の採用/入社に繋がった際、マッチング精度が高まりやすいという特徴があります。
■(2)短期型:会社説明会・ワークショップ複合型インターンシップ
数日~長くても数週間の短期間で行われるインターンシップです。会社説明、業務の疑似体験ができるワークショップ、事業戦略を考え会社理解を進めるワークショップなど>が実施されます。給与支給の有無は企業や内容によってまちまちです。その期間の短さから、企業側・学生側ともに多くの人数と接点を持ちやすく、互いに相対比較をしやすいという特徴があります。
次に、従来のオフラインインターンシップをアップデートしてできた「オンラインインターンシップ」について説明します。
「オンラインインターンシップ」とは出社せず、リモートワークで行うインターンシップ全般を指します。新型コロナウイルス流行による外出自粛要請などを受けて、企業側が工夫をして生みだしたものです。基本的には前述した2種類のインターンシップをオンライン・非対面へと舞台を移したものを指します。
■(1)長期型:就業型オンラインインターンシップ
長期型は従来出社して行っていたインターンシップをリモートで対応するなどオンライン化したものです。自社の業務そのものを「オフライン・対面」から「オンライン・非対面」に素早く移行できた会社は、就業型インターンシップのオンライン化も容易に行うことができました。
しかしながら業務特性上できなかった企業などは、やむなく取りやめとなった企業もあるようです。スムーズにオンライン化できた企業であっても「従来の対面時より社員とのつながりが感じづらい」などの課題が新しく出てきたと聞きます。それらを解消するためによりオンライン上での接点回数や方法を工夫するなど、各社対策を取っている状況です。
■ (2)短期型:会社説明会・ワークショップ複合型オンラインインターンシップ
基本的な取り組み内容はそのままに、オンライン化にあたってさまざまなマイナーチェンジが行われました。例えば、会社説明会パートに「オンラインオフィスツアー」が導入されたり、自宅に会社ロゴやイメージキャラクターがプリントされたノベルティが届いたりなど、オンライン化によって企業理解度が下がることを見越してあらゆる工夫が多方面で見られました。
また、ワークショップパートはオンライン化することで参加者の理解や管理が難しくなり、オフライン時よりも緻密なプログラム設計が求められるようになりました。その影響もあって最近ではオンラインイベントに強い会社へ外注する企業も増えてきたようです。
「オンラインインターンシップ」が増えたもう1つの理由
──「オンラインインターンシップ」が増えたのは新型コロナウイルスの影響が大きいと思いますが、他にも理由はありますか?また今後はどのようになっていくと考えているかも合わせて教えてください。
新型コロナウイルスの影響は言わずもがなでしょう。インターンシップのみならず、面接なども大半がオンラインに切り替わりました。ただ、「オンラインインターンシップ」が拡大したのは新型コロナウイルスの影響だけではなく、応募者の移動負担の軽減も大きく影響していると考えています。経験した方であればご理解いただけると思うのですが、従来の就職活動は工数もお金もかかるものでした。地方に住む学生が足しげく何社もオフラインで説明会に通った結果、移動費や宿泊代だけで何十万円も掛かった、なんて話もよく聞きます。
しかし「オンラインインターンシップ」であれば、在住エリアに関係なく全国の企業と接点を持つことができるようになります。企業側からしてもエリアを限定せずに優秀な人材に出会えるチャンスが増えるため、互いに新しい可能性が生まれているのです。また、それを実行できるオンラインミーティングツールやネットワークなどのテクノロジーの進化も後押しをした一因でしょう。
特に私が印象的だったのは、新卒採用担当時に「このご時世にオフラインを希望する会社には絶対に行かない」と学生の応募者に言われたことでした。昨今の学生は企業のスタンスや考え方を重視する傾向が強いため、インターンシップに関わらずオフラインで何かを行うだけで、「社会的感覚が乏しい会社」という印象になってしまうリスクさえあるのです。
こういった背景から、現在の新卒採用市場においてはインターンシップのオンライン化は必須の状況になっています。そのため今後は「オンラインインターンシップ」を基本として、世の中の状況に合わせて「オフラインをいかに効果的に織り交ぜていくか」<が、より重要になってくると考えています。
「オンラインインターンシップ」をどう活用するべきか
──今後、企業は「オンラインインターンシップ」をどう活用していくべきでしょうか。目的やシーン、方法論などについて教えてください。
ここまでの話を整理するためにも、「オンラインインターンシップ」のメリット・デメリットを企業側・学生側に分けて記載します。
■企業側
・メリット:地方や海外の学生に対してリーチできる
・デメリット:企業の魅力を伝えるのが難しい、オンライン実施時の管理が難しい
■学生側
・メリット:移動負担が少ない(気軽に受けられる)、企業の評価や相対比較がしやすい
・デメリット:企業の魅力がわかりづらい
このようにお互いに「接点を増やせる」点が大きいメリットであるため、基本的にはオフラインのインターンシップと同じく「母集団形成」を目的に活用するのが引き続き効果的だと考えます。
その中でも、中小企業では就業型、大企業では会社説明会・ワークショップ複合型の「オンラインインターンシップ」を採用するケースが多くなるでしょう。理由はそれぞれの組織規模感との相性です。
大企業では組織体制が高度化しており、会社内での職務要件や役割は明確なところが多く、そのためインターンシップ生に裁量を持たせることが難しくなる傾向があります。しかし中小企業であれば柔軟にインターンシップ生に対しても比較的高い裁量を与えることができるため、就業型との相性も良いと言えます。
また、中小企業では経営層との距離感も近く、そういった環境で働く経験を積めることを魅力に感じるインターンシップ生は成長意欲も高いため、中小企業がより優秀な人材を獲得する手段としても有効です。就業型インターンシップに参加して会社や経営層を好きになり、そのまま一社単願で就職した、というケースもよく耳にします。
「オンラインインターンシップ」での成功事例
──「オンラインインターンシップ」を導入・活用している企業の中で、特に成果を出している事例について教えてください。
私が在籍していた企業の事例を紹介します。そこでは採用する部門ごとに異なる手法の「オンラインインターンシップ」を実施して成果を挙げていました。
■新規事業部門採用
組織の形が定まっていない新規事業部門では「就業型オンラインインターンシップ」を軸に採用活動を設計しました。その際にデメリットとして挙げた「管理の難しさ」を解消するために、人事側で2週間に1度「モニタリング」を実施。就業してくれているインターンシップ生と1on1を行ってメンタル状況の確認をしたり、マネジメント担当者へも懸念や問題がないかを確認するなどして、とにかくリスク管理に奔走しました。
インターンシップ期間終了後は、その部門への配属を確約した上で内定出しを行いました。就業型インターンシップを実施していない他社と比較して当初はインターンシップ生が悩まれる場面もありましたが、最終的には当社に決断いただけることに。事業責任者やその他社員との距離感の近さ、働くイメージが固まっていたことが入社の決め手<になったようです。
■総合職部門採用
採用人数が比較的多かった総合職部門では、「会社説明会・ワークショップ複合型オンラインインターンシップ」を軸に採用活動を設計しました。それ以前からオフラインでは実施しておりましたが、オンライン化に伴いワークショップのタイムスケジュールを緻密に設計したり、Zoomでのグループ分けタイミングを運営側で何度もリハーサルしたりするなど、オフライン時よりも準備に相当時間と手間を掛けました。
また、これは私が在籍していた企業ではありませんが、あるベンチャー企業では就業型オンラインインターンシップで一度に100名近く採用して事業を1つ任せるほどの裁量権を与えていたところがありました。特に就業型で満足度が高まると学生間でも評判になることが多く、次から次へと意欲の高い学生がその会社へと入社されていくのを目の当たりにしました。
編集後記
オンラインインターンシップへの取り組み方次第では、知名度や待遇面などで不利と言われる中小・ベンチャー企業でも学生に広く・強く訴求することができるようになるのだと、今回のお話を聞いて感じました。
今後インターンはもちろん、そのオンライン化はもっと「当たり前」になっていくはずです。そうなれば、中身をどこまで魅力あるものに仕立てることができるかが採用のカギとなるかもしれません。それだけの強い意識を持って取り組む必要がある領域なのではないでしょうか。
人事の困りごとはプロフェッショナルへ頼む時代です
コンサルを雇うよりも安く、派遣社員を雇うより専門的で、 正社員を雇うよりもノーリスクで、貴社の悩みや課題を解決できます。こんなこと困っていませんか??
・採用がうまくいかない
・採用に割ける時間がない
・繁忙期だけ即戦力が欲しい
corner inc.は、手を動かす人事コンサルです。cornerには人事・採用関連の豊富な経験とノウハウを持った頼もしいパートナーが多数登録しています。またcornerのメンバーも人事・採用業務をよく知るものばかり。パートナーを紹介して終わりではなく、実際のプロジェクトにも積極的に関与し、 パートナーとともに課題解決に努めます。お悩みや困りごとをまずはお気軽にご相談ください。
人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチングを支援する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」。
「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」
株式会社コーナーが運営する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」は、採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。
コーナーは1,500名を超える即戦力のプロフェッショナルが登録をし、プロフェッショナルによる課題解決を実働支援型で行います。週1日から必要な業務内容・業務量だけプロフェッショナルの経験を活用できることで、多様化してきている人事・採用課題を効果的に解決します。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -
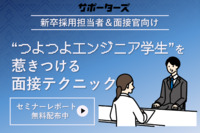
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -
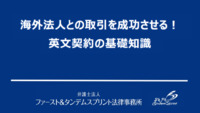
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -
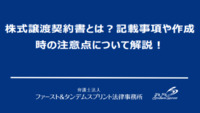
株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -
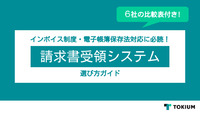
失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】
おすすめ資料 -
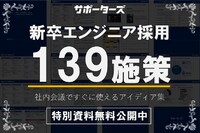
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース