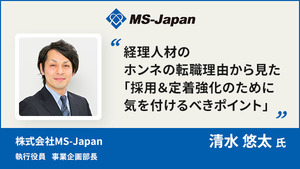公開日 /-create_datetime-/

近年、国内では地震や台風といった自然災害が頻発しており、今年(2018年)に入ってからも、各地で大規模な地震や台風の被害が数多く報告されています。
BCP(事業継続計画)は、こうした大規模な自然災害や火災などが発生した場合に、企業が事業における損害を最小限にとどめつつ、事業の継続や早期復旧を目指せるように、平常時に定めておく「緊急事態を視野に入れた事業計画」といえます。
ここではBCPの内容や、BCPの策定が企業に与えるメリットなどについて解説していきます。
大企業の6割強がBCPを策定している
政府が行った調査によると、2017年度にBCPを策定していた企業の割合は、資本金が10億円以上で従業員が50人以上という大企業では6割を超えていたとのことです。これが資本金10億円未満、従業員50人以下の中堅企業になると、その割合は3割強にまで減少します。しかし、企業の規模が小さいほど災害や緊急事態で深刻なダメージを受ける可能性が高いため、むしろ中小企業こそBCPを策定しておくべきという指摘もあります。
また、BCPを策定している割合がもっとも高い業種は、電気・ガス・熱供給業および水道業となっていますが、こうしたライフラインに関わる企業や、運輸・郵便・通信などの関連企業、あるいは病院や薬局といった医療関係の事業者は、その性質上、災害時でも早期の復旧が望まれるため、特に BCPの策定が必要な業種といえるでしょう。
BCPの具体的な内容は?
今のところ、企業にBCPの策定を義務づける法律や条令はないため、BCPについては各企業が独自に策定を行っているのが現状であり、中小企業庁が実施した調査では、多くの企業が業界団体の発行する冊子や、中小企業庁が公表しているBCP策定の運用指針、内閣府が発行している冊子などを参考にしてBCPを策定していることも報告されています。
また政府や自治体では、企業のBCP策定に対するさまざまな支援や助成の制度を実施していますが、なかにはこうした制度の一環として、国際規格(ISO22301)に準拠したBCPの策定を支援するプログラムを行っている自治体もあります。
なお、BCPは具体的には緊急時に対応するための「マニュアル」として文書化されますが、ここでいう緊急時には、地震や津波といった自然災害だけでなく、火災やテロ、取引先の倒産といった事業の存続に関わるあらゆる重大な事態が発生したケースが含まれます。
その一方で、上記の政府調査では、BCPの内容に記載されている項目としてもっとも多かったのが「従業員の安全確保」であり(BCPを策定している企業の9割以上が記載)、以下「災害対応チーム創設」「水、食料等の備蓄」と続いていることも報告されており、国内では多くの企業がおもに自然災害を想定したBCPを策定しているのも現状といえます。
BCPを策定するメリットは?
政府の調査では、BCPに記載した項目のうち役に立ったものとして、「従業員の安全確保」「災害対応チーム創設」「水、食料等の備蓄」などをあげている企業が多いことも報告されています。また同調査では、半数近くの企業が役に立った項目として、「サプライチェーン(※)維持のための方策」をあげていましたが、これは製造や流通に多くの工程を持つ企業であれば、緊急時に備えて講じておきたい対策といえるでしょう。
※サプライチェーン…原料の段階から、製品やサービスが消費者の手に届くまでの全プロセスのつながり。
また、BCPの策定は上記のような災害時の対応に有効なだけでなく、平常時にはBCPのマニュアルを作成することが事業における重要事項や問題点を浮き彫りにするため、業務の改善に役立つという指摘もあります。さらにBCPの策定は、「リスクへの備えを行っている」ということで取引先や株主に対する信用度や安心感の向上にも影響を与えるといわれています。
上にも述べたように、BCPはさまざまな緊急時を想定した事業計画であり、防災対策はその一部ということができますが、自然災害が頻発している現在においては、「災害時にいかに安全を確保し、事業を継続するか」という取り組みが、あらゆる事業者に求められているといえます。
しかし、いざ緊急事態が発生した場合、こうしたマニュアルをただ策定しただけではスムーズな運用が難しいのも実情です。
(株)東京商工リサーチの調査では、東日本大震災の発生から丸7年を経た2018年の時点で、この震災に関連して倒産した企業が1857件に達したことが報告されていますが、このうちの約9割は、取引先や仕入先が被災したことによる販路の縮小や受注キャンセルなどが影響して倒産したといわれています。
こうしたデータからは、BCPには自社の対応だけでなく、取引先など自社に関連のある企業も視野に入れた方策が必要とされていることがわかりますが、BCPを策定した後も常に内容のチェックをおこない、すぐにBCPを活用できるような体制づくりを行っておくことは、自然災害が多発する時代を企業が生き抜いていく秘訣なのかもしれませんね。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

コロナで変わった人事現場の実態 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -
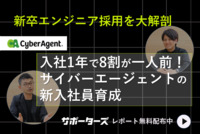
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -
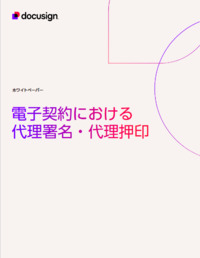
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -
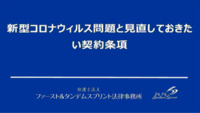
新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -
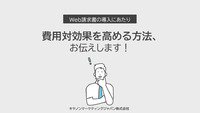
Web請求書の導入にあたり費用対効果を高める方法、お伝えします!
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース -

若い世代が職場で直面する差別や偏見とは?
ニュース -

電車通勤のメリットとデメリット 株式会社ビズヒッツ調べ
ニュース -
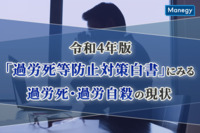
「令和4年版 過労死等防止対策白書」にみる過労死・過労自殺の現状
ニュース