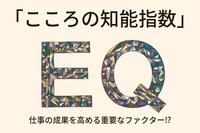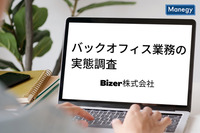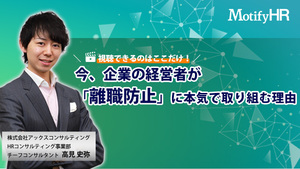公開日 /-create_datetime-/

改正育児・介護休業法が2021年9月21日に閣議決定され、「男性版産休制度」とも呼ばれる出生時育児休業制度が2022年10月1日から始まります。
企業への義務化項目も盛り込まれており、2022年4月1日から施行されます。
今回は、取得促進が期待される男性版産休制度について、概要および企業へ義務付けられた内容について紹介します。
目次【本記事の内容】
男性版産休とは
男性版産休とは「出生時育児休業」のことで、子の出生後8週間以内に、最大4週間の育休を父親が取得できる新制度です。
出生時育児休業の申請は、2022年10月1日から可能となります。
厚生労働省は、2020年度に12.65%だった育児休業取得率を、2025年度には30%までの引き上げを目指しています。
なお、育児休業給付金は現行と同じく賃金の67%が支給されます。
法改正の目的
今回の改正の目的として、大きく次の3点が挙げられます。
- 出産や育児による労働者の離職を防ぐ
- 男女が交替しながら育児休業できる仕組みを作り、育児と仕事の両立を可能とする
- 男性の育児休業取得促進を図る
現状では男性の育児休業取得は大変少なく、女性のみが育児休業を取得してキャリアの中断を余儀なくされています。
また、産後の精神的・肉体的な負担を抱えた状態で、妻のみが育児や家事を担当することにもなっています。
これらのことは、社会への男女平等参画の観点や、健康的で円満な家庭生活を送るうえでも問題とされていました。
新設された男性版産休制度により、育児取得希望率の向上、性別による育児休業の取得格差の打破、性別による担当業務の制限撤廃、仕事と子育てが両立できる社会につながることが期待されます。
より柔軟な仕組みで家庭をサポート
男性版産休制度は、現行の育児休業制度よりも柔軟な仕組みとなっています。
新制度内容の特徴は、「申出期限」「対象期間・取得可能期間」「分割取得」「休業中の就業」の4点です。
●申出期限
現行の育児休業制度は1カ月前までに会社に申請する必要がありましたが、男性版産休制度では原則2週間前までに申請すればよいことになりました。
これにより、出産予定日がずれた場合でも申請が可能となり、出産直後の母体ケアや育児に夫が積極的に関われるようになります。
●対象期間・取得可能期間
現行の育児休業制度の対象期間・取得可能期間は、原則子どもが1歳(最長2歳)になるまでに1回の取得が可能でした。
それに対して男性版産休制度では、子どもが生まれた直後8週間以内に4週間まで取得可能です。
次項目の分割取得と現行の育児休業との組み合わせにより、子どもが生まれた直後から臨機応変に夫の育児休業が可能となります。
●分割取得
現行の育児休業制度では原則として分割取得できませんでしたが、男性版産休制度では、出生後8週間以内に2回の分割取得が可能です。
さらに、2022年10月1日から現行の育児休業も2回の分割取得が可能となるため、あわせて4回に分けて休みを取得できるようになります。
家庭ごとに出産の事情や育児状況が異なるので、分割取得の自由度が高まるのは大きなメリットとなるでしょう。
たとえば、妻の出産時に取得して里帰り中は通常勤務に戻る、妻の職場復帰にあわせて夫が休業するなど、家庭の事情に応じて活用できます。
●休業中の就業
現行の育児休業制度では育児休業中の仕事はできませんでしたが、男性版産休制度では、休業中の就業が可能となります。
労働者の意に反したものとならないよう労使協定を締結し、労働者と事業者の個別合意した範囲内で就業できます。
育児休業給付金の支給要件に合わせて、上限を「休業期間中の労働日・所定労働時間の半分」とする予定です。
企業への義務付け内容
男性版育児休業制度の実施にあたり、従業員が育児休業を申請・取得しやすいよう、企業に対しては、雇用環境面での整備や育児休業取得状況の公表など、主に次のような義務化が設けられ、2022年4月1日から段階的に施行されます。
●制度周知と意向確認の義務化
自身や配偶者の妊娠・出産を申し出た従業員に対して、育児休業制度の内容を知らせたうえで、取得の意向を確認することが義務化されました。
●申請の円滑化を目的とした措置の義務化
現実的に育児休業申請を円滑に行えるよう、育児休業に関する相談窓口設置、研修などの選択肢からいずれかを選択し、措置するよう義務付けられています。
●育児休業取得状況の公表義務化
従業員が1,000人超の企業に対しては、2023年4月1日から育児休業の取得状況についての公表が義務付けられました。
●有期雇用労働者の取得要件の緩和
現行では、契約社員や嘱託社員などの有期雇用労働者の場合、継続雇用期間が1年以上なければ育児休業を取得できませんでした。
改正により、継続雇用期間が1年未満の有期雇用労働者も、原則として育児休業の取得が可能となります。
ただし、労使協定で1年未満の従業員を育児休業の対象外とする場合は、企業はその義務を負いません。
まとめ
男性版産休制度が始まる前に企業への義務化が施行されます。企業としては、複数回の育児休業取得を想定した準備に取り掛かる必要があります。義務化項目への対応だけでなく、誰がどのタイミングであっても取得しやすいよう、属人化業務の改善や就業規則の改訂などをしておきましょう。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -
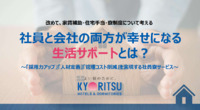
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -
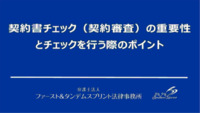
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -
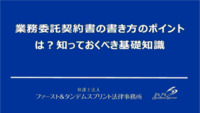
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース