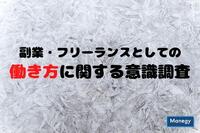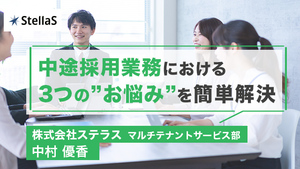公開日 /-create_datetime-/

新型コロナウイルス対策として2020年から一気に広まっているテレワーク。一般社会に定着しつつある一方で、従業員によって向き不向きがあるなどメリット・デメリットの両面があり、いまだ多くの企業が手探りで体制づくりや実施を進めています。
テレワークのデメリットとしてよく指摘されるのが、ストレスです。テレワークによるメンタルヘルス不調は従業員の健康を害する心配がありますが、従業員の不調は同時に企業の損失にもつながります。
そこで今回は、テレワークによるメンタルヘルス不調と会社の生産性との関係性について考えてみました。
目次【本記事の内容】
テレワークがメンタルヘルスに与える影響
2020年4月に新型コロナウイルス対策として1回目の緊急事態宣言が発出され、多くの企業でテレワークが実施されました。急激な労働環境の変化に加え、この時期は全国の小中学校が休校しており、家庭のある人は自宅で仕事をするにも子どもがうるさくて集中できないといったストレスを感じるケースが多かったようです。
総務専門誌『月刊総務』を発行する株式会社月刊総務が、2020年9月に全国の総務担当者を対象に行ったアンケート調査によると、総務担当者の50%以上がテレワークの推進によってストレスが増えたと回答しています(「とても増えた」10.6%、「やや増えた44.0%」)。
また、「新型コロナウイルスの感染拡大以降において、従業員のメンタル不調の要因が何だと思いますか」という問いに対しては、「テレワークによるコミュニケーション不足・孤独感」が60.0%と最も多く、「外出しないことによる閉塞感」が56.5%と続きました。さらに「オンとオフの切り替えの難しさ」52.5%、「運動不足」48.6%、「家族のいる場で仕事をするストレス」36.9%と続き、30%を超えている上位6つの項目のうち、テレワークに関わるストレス要因が5つ挙げられていました。

画像出典:『月刊総務』
1回目の緊急事態宣言を受けてテレワークを実施した企業の中には、急ごしらえの体制で踏み切ったところも少なくないでしょう。準備の整っていない状況下でのテレワーク決行は、従業員にとっても非常に大きなストレスになったはずです。
あれから1年以上経過しました。学校が長期間休校することはなくなり、テレワークにも慣れてきたころでしょう。テレワークは週1~2日だけという企業も多いようです。
しかし、コミュニケーション不足・孤独感、閉塞感、オン・オフの切り替えの難しさなど、テレワークに起因するストレス要因が解決されたわけではありません。慣れによって気にならなくなる従業員も中にはいるかもしれませんが、自宅の環境や業務内容などによりストレスを感じる度合いは人それぞれです。今後もテレワークに起因する従業員のメンタルヘルス不調に対応していく必要がありそうです。
従業員のメンタルヘルス不調は企業の生産性低下に
従業員のメンタルヘルス対策は、従業員にとっての健康福祉・福利厚生のためだけに行うのではありません。企業の生産性低下を防ぐためでもあります。
ある研究では、メンタルヘルス不調により休職した従業員の多い企業は、2年程度のタイムラグを伴って売上高利益率が低下する傾向にあると指摘しています。休職者の増加がただちに企業の業績を悪化させるとは限りませんが、一部従業員に休職させるような労働環境は他の従業員にも精神的に大きな負荷を負わせていると考えられ、生産性の低下にもつながっている可能性があります。
従業員のメンタルヘルス不調が会社の生産性にどのように影響を及ぼすのかについて、具体的には次のようなことが考えられます。
- 集中力が低下し、作業がはかどらなくなる
- 遅刻、早退、欠勤が増える
- 他の従業員の業務負担が増え、メンタルヘルス不調が周囲に広がる
- 休職者の退職により新規採用のコストがかかる
- 休職者の労災認定により休業補償の負担がかかる
メンタルヘルス不調により休職する従業員は全体のごく一部かもしれませんが、休職までには至っていないが危うい状況にあるという従業員が多数いることも考えられます。他の従業員へ影響する危険もあり、じわじわと企業を圧迫しかねないため、早めに対策を講じる必要があるでしょう。
最大91%が在宅勤務になった大手企業のメンタルヘルス対策
前掲『月間総務』によるアンケート調査では、従業員のメンタルケアとして実施している施策についても質問しています。最も多かった回答は「相談窓口の設置」で34.1%であり、次いで「朝礼・夕礼等の実施」26.7%、「アンケートや聞き取りの実施」22.0%、「ストレスチェックの強化」20.8%でした。
日清食品グループでは、即席麺事業を担う会社で最大91%が在宅勤務になり、2020年4月にいち早く「テレワークうつ予防チーム」を発足しました。日清食品ホールディングスでは、メンタル不調が続出して対症療法を行う前の段階で、予防策として活動を開始しました。
同社が実施したのは、在宅勤務者へのアンケート調査と面談です。アンケート調査の結果に基づいて、自律神経測定で疲労ストレスを可視化し、数値の思わしくない従業員に面談を推奨しました。しかし数値で引っかかった従業員が必ずしも自身のストレスに自覚的ではないため、同社は「おせっかいな予防」をテーマに「押しかけ面談」という積極的に声がけをして面談を行う活動を進めました。
同社担当者は、ストレスに無自覚だった従業員も、ストレスについて意識するようになったり、日常生活の改善を心がけるようになったりするなど、ヘルスリテラシーの向上が見られたと言います。
メンタルヘルス対策は企業主導で先手を打つことがポイント
従業員のメンタルヘルス対策は、従業員の体調不良や相談があって初めて企業が動くのではなく、企業が率先して先手を打つことが重要です。
OECD [2012]は、メンタルヘルスの不健康度指標が上位5%にある人のうち、58%の人が就労を続けており、そうした無理に働く労働者が2005年から2010年にかけて増加傾向にあることを指摘しています。
メンタルヘルスに対する社会の意識が高まっている一方で、精神疾患のレッテル貼りは依然として従業員と企業双方に根強く、「本人に原因がある」という考えの下、医療機関を受診せずに無理をして働く従業員がまだまだ多いようです。
身体症状として現れる他の病気やケガと比べ、精神疾患は症状が現れにくく、本人や周囲がおかしいと感じた時点ですでに病状が深刻になっていることも少なくありません。過重なストレスがかかっている環境は、すでに一部従業員にとっては病状が進行しているものと考えて、人知れず悩んでいるような従業員を企業全体で拾い上げできるシステムを作ることが重要と言えるでしょう。

おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

<人的資本開示 実践編 > 人的資本と組織サーベイ
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -
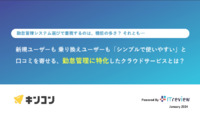
新規ユーザーも 乗り換えユーザーも「シンプルで使いやすい」と 口コミを寄せる、勤怠管理に特化したクラウドサービスとは?
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

三菱総研DCSが取り組む「ダイバーシティー経営」への第一歩
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -
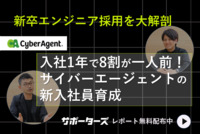
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース