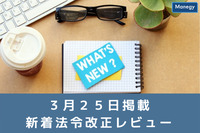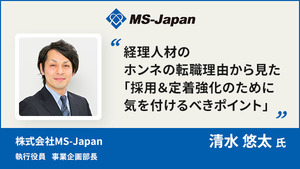公開日 /-create_datetime-/

財務省広報誌「ファイナンス」に、財務総合政策研究所上席客員研究員(愛知学院大学/三好向洋氏)の論文「労働分配率の低下に関するサーベイ」が掲載されています。労働分配率は、企業が生み出した付加価値に、人件費がどのくらいの割合を占めているのかを示す経営指標の一つです。大企業は空前の高収益をあげていますが、労働分配率はなかなかあがっていないのが実状です。
そこで、労働分配率をおさらいしておきましょう。
2000年代以降低下傾向の労働分配率
財務省が行っている法人企業統計調査(10~12月期)によると、資本金10億円以上の大企業の労働分配率は43.9%です。
世界各国で、労働分配率は低下傾向を示していますが、日本では2000年代以降、低下傾向を示し、なかなかあがっていないのが現状です。
政府は、賃上げを経済界に要請していますが、最高益を記録する企業が多数出現しているにもかかわらず、賃上げの勢いは鈍く、労働分配率を押しあげるまでには至っていません。
労働分配率は高い方がいいのか低い方がいいのか
では、労働分配率は高ければよいのか、それとも低い方がよいのでしょうか。
労働分配率が低いということは、会社にとっては収益を効率よく確保できます。逆に労働分配率が高ければ、収益に対して人件費への配分が多く、従業員にとってはプラスですが、会社にとってはマイナスとなります。
しかし、従業員の給与水準が低く抑えられているということは、従業員のモチベーションの低下につながることから、長い目でみると、企業にとってもマイナスになると予想することができます。
労働分配率は「労働分配率(%) = 人件費 ÷ 付加価値 × 100」で、計算することができます。ただし、論文では、正確な測定は困難であることと、そしてその理由として以下の点を指摘しています。
- 労働への分配を受けるものに誰までを含めるべきかが不明。
- オーナー社長や自営業者の報酬は、所有する資本に対しての分配も含み、労働者として考えてよいのか。
- 労働への分配としてどこまでを含むべきか不明。
いずれにしても、労働分配率の低下は、所得の一極集中につながり、格差社会を促進させることにもなりかねません。それだけに、なぜ労働分配率の低下が起こるのか、それがいつ止まるのかに、世界中の研究者が関心を寄せているそうです。
別のデータでもやはり低下傾向
こういった点を考慮に入れ、日本の労働分配率を以下の5通りで定義、その推移を示したデータもあります。
- 雇用者報酬/国民所得、
- 1人あたり雇用者報酬/就業者1人あたり国民所得、
- 雇用者報酬/(雇用者報酬+法人企業所得)、
- 雇用者報酬/(国民所得-個人企業所得)
- 1人あたり雇用者報酬/就業者1人あたり国内総生産
それによると、どれも90年代は上昇傾向をみせていたものの、2000年代に入ってから低下傾向をみせています。例えば、「1人あたり雇用者報酬/就業者1人あたり国内総生産」では、2000年には65%ほどあったものが、2006年には60%ほどまで低下しています。
自社の労働分配率の把握と他社との比較
一般的には、労働分配率は40~50%なら「良」とされています。ですから、43.9%という労働分配率の数字は、決して悲観するような数字ではありません。
「労働経済白書」によると、日本の企業の労働分配率は、40%から70%に集中していますが、40%を切るような企業は、収益体質が「良好」ということになり、70%を超えるような企業は「要注意」という見方もできます。
もちろん業種によっても、労働分配率の数字は大きく異なります。労働集約型のサービス産業などは労働分配率が高く、資本集約型の製造業などは低いといった傾向もみられます。
産業別の労働分配率は、経済産業省のサイトで確認することができますので、自社の労働分配率が、どの程度なのかを把握しておくことはもちろん、業界の全体の水準や、ライバル企業との比較も、必要となるのではないでしょうか。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

電子署名の適法性 ~日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性~
おすすめ資料 -

誰もが悩む5つの組織課題をサーベイ導入で解決するヒントとは?
おすすめ資料 -

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -
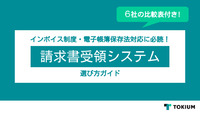
失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】
おすすめ資料 -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -
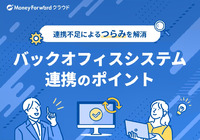
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -
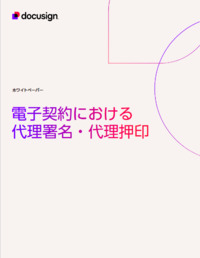
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -
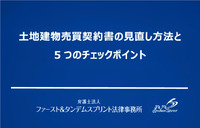
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース