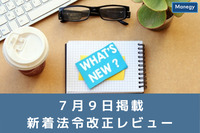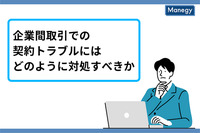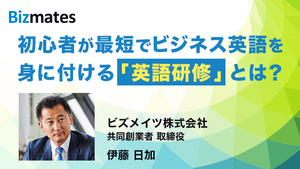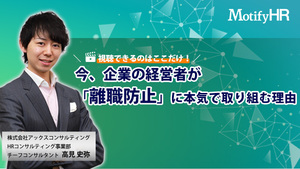公開日 /-create_datetime-/

昨年からの新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの企業でテレワークの導入が進められました。しかし当初は緊急措置的な施策として注目を集めたテレワークでしたが、コロナ禍が長引いているために、各企業は恒常施策としてテレワークを整備する必要性も生じています。
そこで今回は、テレワークを将来にわたって継続して導入する上で必要なことは何か、という点について詳しく解説しましょう。
テレワークを継続的な施策として導入する上で必要なこと
企業が自社にテレワークを導入する場合、導入の目的・方針の設定、社内における合意・ルールの形成、ICT環境整備が不可欠です。
導入の目的・方針の設定とは、テレワークをどの部署に導入するのか、いつまで導入するのか、といった具体的な計画を策定することを指します。そして社内の合意・ルール形成とは、テレワークを導入するに当たって従業員側と話し合い、導入することについて納得してもらった上で、就業規則や労務管理体制を適宜変更することです。
また、テレワークを導入するには、物理的な条件としてICT環境を整えることも不可欠といえます。ICTシステム・ツールを事前に整えていなければ、当然ですがテレワークの導入は行えません。
しかし、テレワークを一時的・短期的に導入するのではなく、継続的な施策として実施する場合、上記のような体制構築に加えて、さらなる導入プロセスを経ることが必要となってきます。それがセキュリティ対策の強化と、テレワークによる就労形態に対応できる従業員の育成です。
テレワークを継続する上で必要なセキュリティ対策
コロナ禍による政府の緊急事態宣言等に合わせ、急いでテレワーク導入を進めるという場合、緊急措置としての対応であるためにセキュリティ対策に十分な時間をかけられません。
マルウェアのような悪意あるソフトウェアへの感染、外部からの不正なアクセス、端末紛失等による個人情報漏えいのリスクは、テレワークをしている従業員が直面する可能性が常にあります。例えば、テレワークをしている従業員が個人情報を含む端末をどこかに置き忘れたという事態が起これば、それだけで重大な個人情報漏えいの危機が生じるわけです。
もし長期的、継続的にテレワークを自社に導入する計画を立てるのであれば、時間をかけてセキュリティ対策をきちんと行い、そのようなリスクを減らす努力を行うことが必要です。なおこの場合のセキュリティ対策とは、技術面とルール面の2種類があります。技術面としては、会社の端末へのアクセス管理・制限の設定、ハードディスク等の暗号化・情報漏えい対策付きのUSBメモリの活用、電子データの原本保存などを挙げられるでしょう。そしてルール面としては、セキュリティに関するガイドラインや情報管理規則の策定、および従業員への周知などがあります。
テレワークを継続できる従業員の育成
緊急措置として短期的にのみテレワークを導入するという場合、手探りかつ場当たり的な対応で何とか乗り越えられるということもあり得るかもしれません。しかし、将来にわたって継続的にテレワークを導入するのであれば、従業員がテレワークという働き方に長く対応できるように、研修等を通して教育する必要があるでしょう。例えば、テレワーク時における勤務時間の管理方法、業務中の計画立案・報告・連絡のやり方、業務プロセスのあり方などは、テレワークという就労形態を継続する上で理解しておくことが求められます。
この点は国としても対策を進めています。コロナ禍が長期化する中、厚生労働省委託事業のテレワーク相談センターは「テレワーク導入にあたっての教育研修」、「テレワークの適切な導入及び推進のためのガイドライン」などを作成・開示しました。これは企業がテレワーク導入にあたってどのような教育研修を行えばよいのか、という点についての指針を提示したものです。これからテレワークに関する研修を行うという場合、テレワーク相談センターが公表しているこれらの資料を活用するとよいでしょう。
なおコロナ禍という状況やテレワークという働き方を踏まえると、テレワークに関する教育・研修は集合研修中心ではなく、離れた場所にいても行えるeラーニングを活用する形で実施されるのが望ましいといえます。この点は厚生労働省のガイドラインの中でも指摘されています。
まとめ
企業がテレワークを導入する場合、導入目的・方針の設定や社内の合意・ルール形成、ICT環境の整備などが必要です。しかし、緊急措置的・短期的な対応ではなく将来にわたって長期的にテレワークを継続する場合は、セキュリティ対策、従業員への教育・研修をきちんと行うことが求められます。
セキュリティ対策としてはガイドラインや情報管理規則などを定めて周知するルール面、アクセス管理・制限やデータの暗号化などの対策を行う技術面の2種類があり、どちらも実施することが大事です。教育・研修はテレワークという就業形態に対応できる従業員を育てることが目的で、厚生労働省がガイドラインも策定しています。
緊急的に導入したテレワークを今後も継続して行っていくという場合、長期的な運用に耐えられるだけの体制作りが必要です。きちんとした対策を取らないまま継続していると、個人情報・企業データの漏えい、人的資源を活かしきれないなどの問題が生じる恐れもあるので注意しましょう。
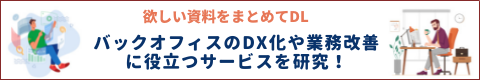
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -
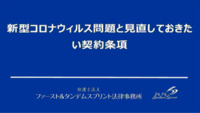
新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -
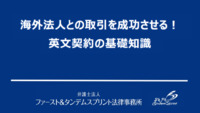
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
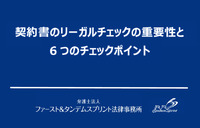
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -
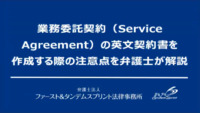
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

請求書受領サービスの 失敗しない選び方
おすすめ資料 -
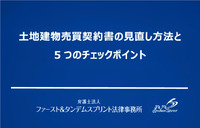
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -
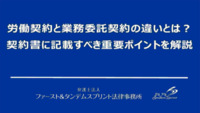
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース