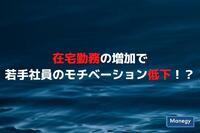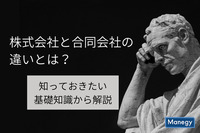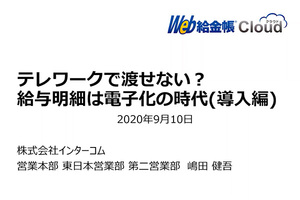公開日 /-create_datetime-/

「執行役員制度」を導入し「執行役員」という役職を設置している会社も多いことでしょう。
しかし執行役員とはどのような立場でどのような仕事を担うのか、理解できていない人も少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では、執行役員・執行役員制度について解説します。社内での立場や権限、制度導入のメリットなどを理解し、執行役員制度について理解しましょう。
目次【本記事の内容】
執行役員とは
執行役員とは、事業運営の責任者として業務の執行を担う人物を指します。もともと代表取締役をはじめとする経営幹部が担っていた業務の監督機能と執行機能を分離する目的で設置されている役職です。
執行役員の名称には「役員」の単語が付いていますが、会社法で規定されている役員ではありません。取締役のように経営に関わる意思決定の権限はなく、あくまでも個々の会社において任意で設置する役職です。
雇用型と委任型
執行役員となる人物は、会社と雇用契約もしくは委任契約を結びます。
雇用型の形態では、執行役員は従業員の一人として会社に所属するため、給与や待遇などは会社の規定に即したものになります。安定した条件で働けるとのメリットがある一方で、他の従業員との線引きがあいまいになりうまく機能しなくなる懸念もあるでしょう。
もう一つの委任型では、執行役員は会社と委任契約を締結します。取締役も委任契約であるため、執行役員は取締役と同等の責任を負う必要が出てきます。その一方、取締役がコントロールしやすい雇用型よりも委任型のほうが判断の自由度が高くなるので、スピーディな業務執行が可能になります。
執行役員制度とは
執行役員制度とは、執行役員という役職を設置して社内の業務執行を強化する制度です。あくまでも任意で設置する制度のため、人数や報酬などは個々の会社によって異なります。
執行役員の役割は業務を執り行うことであり、経営に関する重要な意思決定はできません。そのため、取締役が決定した重要事項や経営方針に従って、業務の実行を専門的に行う役職となります。
- 執行役員制度導入のメリット・効果
執行役員制度を導入することで、取締役の業務が分業されて生産性の向上が期待できます。
執行役員制度を導入していない企業では、取締役が経営に関する判断や業務の監督、さらには業務の執行の責任までを負います。しかし、その場合には取締役はそれぞれの業務に専念できず、判断が鈍ってしまったり遅くなってしまったりすることもあるでしょう。変化が激しいビジネスの世界では、迅速な対応をしなければチャンスを逃してしまうこともあり得ます。
そこで執行役員制度を導入することにより、意思決定や監督機能は取締役が担当し、業務の執行については執行役員が担うことが可能になるのです。自分がやるべき業務に専念できるため、パフォーマンスが向上して会社としての生産性がアップすることが期待できます。
- 執行役員制度のデメリット・注意点
執行役員制度にはメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあります。
事業の効率化のために導入される執行役員制度ですが、時として非効率になってしまう場合もあるのです。
たとえば執行役員が自分で判断して実行してもいい業務と、取締役に判断をあおいでから実行しなければいけない業務を分けている場合、情報共有がスムーズにいかずに意思決定が遅くなってしまうことがあります。取締役の意思がうまく伝わらずに成果を出すことができなければ、執行役員という立場の意義もなくなりかねません。
また、法律上、明確に規定された役職ではないため、他の従業員が混乱してしまうことも懸念されます。事業部長や部長の業務内容との線引きが曖昧だと、執行役員が機能せずに形骸化してしまうこともあるでしょう。
執行役員制度を導入する際には、これらの点に注意が必要です。
執行役員と役員・執行役との違い
執行役員と混同されやすい役職に「役員」や「執行役」があります。これらの役職と執行役員の明確な違いは、法律で規定されているかどうかです。
先述の通り、執行役員は会社法で定められている役職ではありません。しかし役員や執行役は会社法で規定された役職のため、立場や役割に大きな違いがあります。
- 会社法で定められる「役員」との違い
会社法の第329条では、取締役・会計参与・監査役が「役員」として規定されています。これらの役員は株主総会で選出され、会社とは委任の関係になります。
取締役は取締役会において会社の経営に関する重要事項を決定ができる人物であり、執行役員はその意思に従って業務を執行する立場となります。
- 会社法で定められる「執行役」との違い
執行役員とは一文字違いの「執行役」ですが、執行役員とは性質が大きく異なっています。
会社法の第402条では、執行役は取締役会で選出される役職と定められており、指名委員会等設置会社に設置する義務があるとしています。執行役は法律上設置が定められた機関であるのに対し、執行役員は任意で設置する役職である点が異なるポイントでしょう。
ちなみに指名委員会等設置会社とは、取締役会の中に指名委員会・監査委員会・報酬委員会を設置している会社のことを指しています。
まとめ
執行役員とは、取締役会が決定した事項に沿って業務執行の役割を担います。分業により業務の効率化が見込めますが、情報共有や業務フローを明確にしておかなければ混乱を招きかねないので注意が必要となってきます。
執行役員の業務や権限の線引きを明確にし、他の従業員に執行役員の意義を浸透させることで、執行役員による生産性向上につなげましょう。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

「人事部の実態と業務効率化」に関するサーベイ結果調査レポート【MURC&DCS共同制作】
おすすめ資料 -
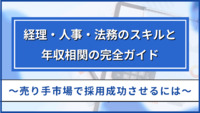
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -
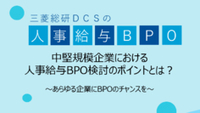
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
おすすめ資料 -
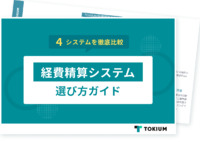
失敗しない!法対応と業務効率化を実現する経費精算システム選び方ガイド【4社の比較表付き】
おすすめ資料 -

若手社員の早期離職を防止するためにできること
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -
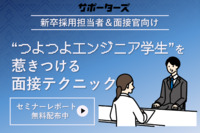
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -
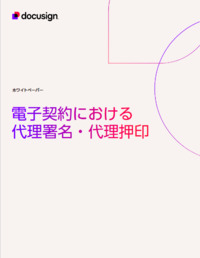
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -

三菱総研DCSが取り組む「ダイバーシティー経営」への第一歩
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース