公開日 /-create_datetime-/
自社理解も外部知見もある即戦力としての「アルムナイ採用」。導入・運用のポイント
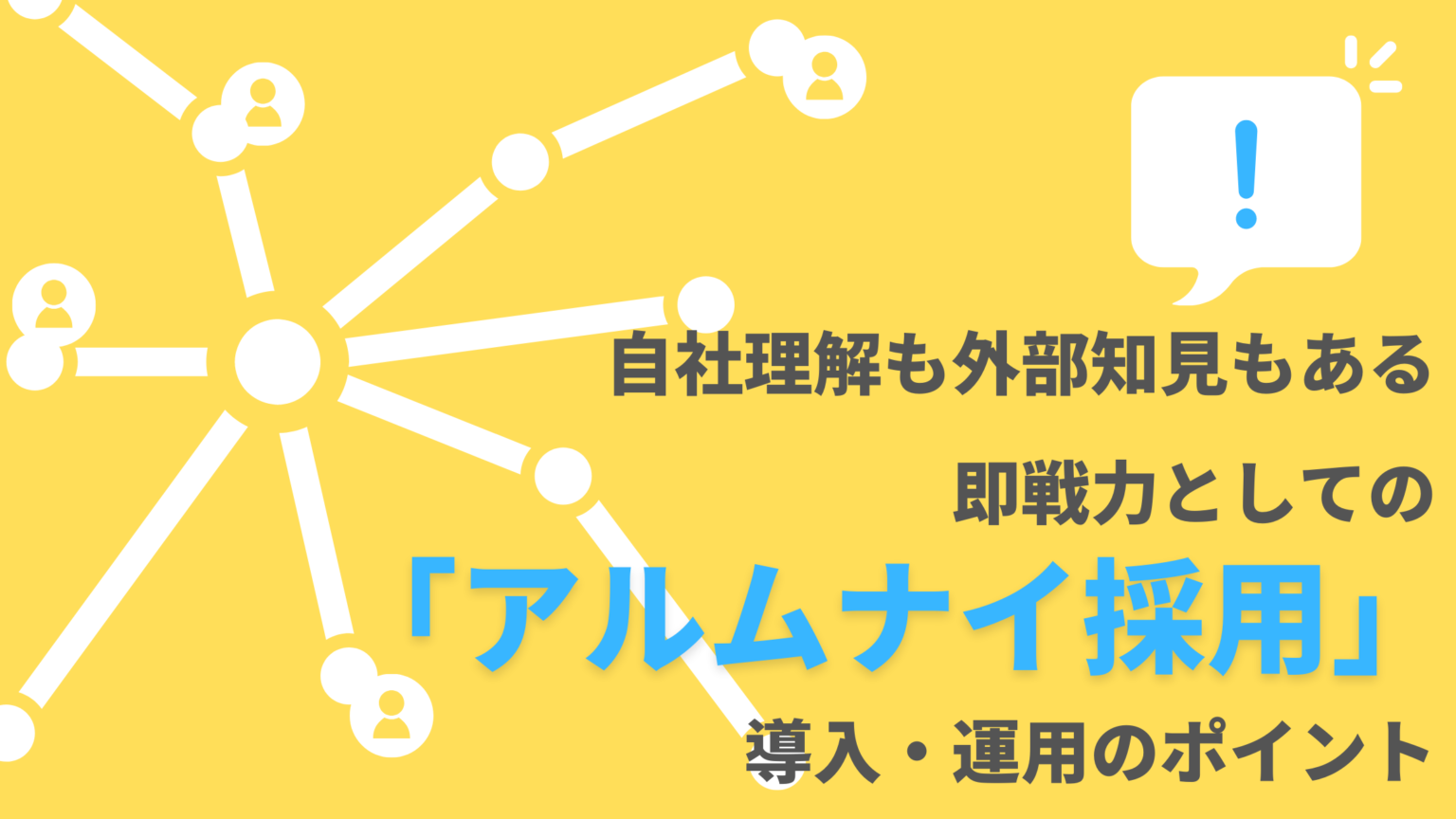
記事転載元:パラれる / 株式会社コーナー
「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」
株式会社コーナーが運営する人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチング支援サービス。採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。企業の“卒業生”との関係性を離職・退職後も保っておくことで、一度退職したメンバーを再び雇用する「アルムナイ採用」。
日本でも終身雇用の崩壊や人材不足などのの背景から、徐々に取り組む企業が増えてきました。
日本にも“出戻り採用”という言葉が昔からありますが、それとアルムナイ採用は何が違うのでしょうか。採用における利点は何なのでしょうか。
今回は人事領域シンクタンク/コンサルティングファームにてアルムナイ採用を含めた様々な領域を研究され、ご自身もアルムナイ採用制度を使って再就業したご経験を持つパラレルワーカーの方に、アルムナイ採用の概念や導入・運用におけるポイント、具体的な事例などについてお聞きしました。
目次【本記事の内容】
アルムナイ採用とは
──「アルムナイ採用」の定義について教えてください。
アルムナイ(almuni)は「卒業生、同窓生」という意味の英単語です。
そこから転じて、かつて在籍・退職した元社員を卒業生に見立て、再び社員として採用することを「アルムナイ採用」と呼んでいます。
外資系コンサルティングファームなど人材の流動性が高い業種では、古くから活用されている採用手法です。
似たものに“ジョブリターン制度”と“出戻り採用”がありますが、アルムナイ採用とは「対象」「企業の姿勢」「採用時の待遇」が異なります。
■ジョブリターン制度
主にやむを得ず退職した方(出産・育児、配偶者の転勤、介護、その他家庭事情など)を対象とした制度です。
退職事由が解消された方の復職を円滑にしたり、新卒採用においても「社員に優しい制度を整備しています」とPRできたりする点から、採用に寄与する制度と言えます。
企業は採用サイトなどでジョブリターン制度を広報し門戸を開く形が一般的で、元社員に対して個々に直接連絡を取るようなことはしません。
また復職後の待遇は退職前と同程度、もしくは新たに就く業務内容に応じて多少の増減があります。
■出戻り採用
転職により退職した方が、再び同じ企業・職場で採用されることを指します。
この場合も、あくまで採用する企業は「待ち」であり、積極的な取り組みは見られません。
「去る者は追わず、来る者は拒まず」といった受動的な姿勢と言えます。
出戻り後の待遇はケースバイケースで、同じ職場で同じ仕事をする場合は「退職前と同程度」が一般的です。
■アルムナイ採用
特徴は以下2つです。
(1)アルムナイネットワーク
「学校の同窓会」をイメージしてもらえると分かりやすいでしょう。
1度目の退職と同時にメーリングリストに登録され、定期的に企業から情報が発信されます。
さらに年1回程度「アルムナイパーティ」と称した懇親会や著名人による講演会などのイベントが開催されることもあります。
(2)武者修行を加味した待遇
卒業後の修行経験を加味して、戻ってきた後の業務内容と待遇をお互いの相談によって決めます。
多くの場合、卒業後の経験がプラス要素となり、相応の職位へ任用したり、年収が増額されたりします。
つまりアルムナイ採用は、「戻れるポストがありますよ」という受身なジョブリターン制度や出戻り採用と違い、「成長したあなたに、ぜひまた当社で働いてほしい」と働きかける自発的な採用手法なのです。
アルムナイ採用のメリット・デメリット
──導入企業側のメリット・デメリットは、どんなものがあるのでしょうか。
まず、メリットは大きく3つあります。
■外部知見を効率的に収集できる
外部知見を取り入れるという点では、一般的な経験者(キャリア)採用も同様です。
しかしアルムナイ採用では、アルムナイが「この知見は活かせる」と算段した上で戻ってくるため、外で吸収した知見が活用されやすいというメリットがあります。
■採用コストの低減
企業とアルムナイの直接的なやり取りが基本のため、採用費(人材紹介手数料・求人広告費など)は掛かりません。
特にアルムナイ採用の対象者はマネジャークラス以上であることが多く、年収と比例する紹介手数料の高さは看過できません。
■教育コストの低減
元々の在籍企業であるため、企業理念などの基礎教育が必要ありません。
また組織風土へも一定の理解があり、コミュニケーションコストを大きく減らすことができます。
一方、デメリットとしては「運用コストの多大さ」があります。
前述の通り、アルムナイ採用を行うためにはアルムナイネットワークを作り、定期的な連絡・イベントなどの実施が必要です。しかも、これらも「ただやればいい」というわけにはいきません。
アルムナイが「このネットワークに所属していて良かった」と感じ、将来の就業場所として魅力的な選択肢の1つとして考えられるような有意義なコンテンツを提供し続けることが欠かせないからです。
採用・教育のコストを低減できる代わりに、こういった社内での運用コストが発生することは認識しておくべきです。
とはいえ、パーティやイベントの規模感や、昨今はオンライン開催も増えたことを考えれば、コストを抑えて運営することもできるはずです。
そのため調査・企画・実行する人材の人件費がコストの大半を占めることになります。
しかし、定期的な対応が必要なものの常にフル稼働する業務量ではなく、簡単にマンパワーを割ける状況ではない中で専属の人材を要する必要はそこまでなく、人事担当者などが兼任で行うのが一般的。
その担当者の1/4~1/3程度の工数をアルムナイ採用関連として見立てるのが現実的だと思います。
アルムナイ採用を組織に定着させるための導入・運用ポイント
──アルムナイ採用を導入する際の方法と、仕組みを形骸化させないためのポイントを教えてください。
アルムナイ採用の実務は、大きく分けて以下4つがあります。
■退職時の良好な関係性の醸成
1度入社した会社を退職する以上、少なからず何かしらの不満はあるもの。
それを企業は認識した上で、「当社の現状はあなたの希望に合わなかったのかもしれない。そのことは真摯に受け止めている。状況が改善され、あなたが再び当社に魅力を感じてくれたならば、もう一度一緒に働きたい」といったメッセージを上司や人事担当者から伝えることが大切です。
■退職者データベースの作成・管理
現社員とは別でデータベースを作成・メンテナンスしていきます。
登録内容としては連絡先や次のキャリアなどが中心となりますが、個人情報にあたるものが多いため必ず同意書にサインをもらってから情報収集・登録を進めるようにしましょう。
■事業状況の定期的な情報発信
「ここで働くと楽しそうだ」とアルムナイの興味を惹きつけることが目的です。
ここで重要なのは、発信するのは「事業」であり「製品」ではないということ。
特に事業範囲の拡大、新事業の立ち上げ、新しい組織機能、外部提携など、未来志向性の高い情報はアルムナイの関心も高く有効です。
定期的な情報発信は、気をつけなければ事務的なものになりがちです。
淡々と行うのではなく、「アルムナイの成長を促す」くらいの感覚でコンテンツ作成に取り組むことが求められます。
コンテンツは、情報発信担当の方ご自身が興味のある内容を選ぶことが重要です。
ある意味インフォーマルな情報発信のため、一定の自由度があると良いと思います。
■採用時のマッチング面談
戻ることに興味を持ったアルムナイと「今戻ってくれたら、どんな可能性があるか」をカジュアルに話す場を設定します。
この際、つい自社の良い面を強調しがちですが、誇張しすぎると採用後の不満につながる可能性もあるため、ありのままを伝えるのが良いでしょう。
また、面談者は元上司以外が望ましいです。
知った顔の方が安心できる側面もありますが、どうしても昔話に終始してしまうもの。
アルムナイとしては心機一転したい気持ちが強くあるため、「当社は変わった」という点を示す上でもあえて在籍時の上司とは違う方が対応するのがベターです。
この4つの実務の中で、制度を形骸化させないために最も重要なのは「事業状況の定期的な情報発信」です。
この情報発信がアルムナイネットワークの質を決めると言っても過言ではありません。
質の高い情報を得られると、アルムナイはネットワークへの関わりを強く持ちたいと思い、その関心が高まった先に「戻ってみよう」という動機が生まれます。
一方で、発信される情報がただの新製品紹介や自己満足のような経営層メッセージばかりだと、アルムナイの関心は離れていきます。
アルムナイのニーズを理解し、その好奇心をくすぐるような情報発信ができるかどうか。それがアルムナイ採用の成否を分けます。
運用者によって成果は大きく変わる?運用適任者の選び方
──ここまでのお話から、アルムナイ採用担当者は単なる作業者ではなく、企画力やコーディネート力が求められるように感じました。実際にはどういった方が適任だと思いますか。
適任者を選ぶ上で、前提として抑えておくべきポイントは、以下2つです。
■事業ラインの役員の参加
重要なのは「アルムナイ採用を人事で閉じない」ということです。
具体的には事業ライン、例えば営業の役員クラスの方に責任者として入ってもらうのが良いと思います。
そもそもアルムナイネットワークは採用のためだけのものではありません。
言わば「社外のファン」であり、「お客様候補」でもあるのです。
そう考えると、人事目線よりも営業目線で情報発信やイベントなどを企画・実行する方が効果的だというのは理解してもらいやすいでしょう。
現にアルムナイ向けパーティは「同窓会」であると同時に「商談の場」でもあります。
そのような機会を最大限活かすためにも、その場には営業の役員が責任者としていることが望ましいです。
■社外視点に基づく自社変化の発信
前述した通り、質の低い情報発信をしてしまうと「以前と何も変わっていない」という印象をアルムナイに与えかねません。
アルムナイが興味を持つ情報をどう収集・発信するか。
この観点は、通常の人材採用とは異なる視点であり、むしろ投資家・株主へ「当社はこれからこのように変わります」と発信することに近いものです。
アルムナイ採用は採用業務・退職者管理の一環であるため、人事・採用担当者が主担当者になるのが現実的ではありますが、上述の様に事業ラインの役員クラスや、その他にも広報・PR担当者にも参加してもらうとより効果を出しやすくなるでしょう。
運営失敗しやすい2つのポイント
──アルムナイ採用を導入後、運営上で注意するべきポイントや課題があれば教えてください。
アルムナイ採用を導入し、実際に運営する上で重要なのは以下2つです。
■活躍できるポジションの設置
アルムナイに「戻ってきて良かった」と思ってもらえるようなポジション(卒業後の武者修行で培った知見を活用できる職場・役職など)を用意する必要があります。
冒頭でご紹介した通り、ジョブリターン制度や出戻り採用とは違い、アルムナイ採用では武者修行を加味した待遇提示をします。
しかし、仮に給与が上がったとしても退職前と同じ業務内容やミッションで配属されたらどう感じるでしょうか。
1度辞めた職場・仕事ですから、モチベーションを保つことは難しいですよね。
また退職前と同じ同僚がいるケースにも注意が必要です。
元同僚からすると、「自分はずっとこの会社で頑張ってきたのに、どうして1度辞めた人間の方が優遇されるのか」と不満に思うことも十分に考えられます。
そうなるとアルムナイ採用で戻った当人だけでなく、その職場の雰囲気自体が悪くなり、マネジメントも大変難しくなってしまいます。
それらも踏まえると、アルムナイ採用では新事業開発や新サービス立ち上げなど、「武者修行経験を活かせる、退職前とは異なるポジション」という“出島”のようなポジションを用意することが望ましいでしょう。
■ゆるやかなKPIの設定
一定のコストを掛けてアルムナイ採用を実施する以上、何らかの成果を経営側からは求められます。
一方で、アルムナイ採用で成果目標を厳格に追及するのは避けるべきです。
例えば「アルムナイ採用数」を目標として立てたとします。「縁あって何名か戻ってくれると良い」くらいの感覚なら健全だと思いますが、「今年はアルムナイ採用で10名確保厳守」とすることは好ましくありません。
基本的にアルムナイ採用は「そろそろ戻ってみようか」「今なら前より貢献できるかも」とアルムナイの方から自発的に応募するものです。
採用目標を厳格化してしまうと、運営側からアルムナイ1人ひとりに連絡を取って復職を働きかけるなどの取り組みをしてしまいがちです。
するとアルムナイの自発性に関係なく応募されてしまい、その結果、復職後も違和感があり再退職ということが発生しやすくなります。
前述したとおり、アルムナイネットワークの効果は採用だけでなく、ファンづくりやビジネス機会の醸成でもあります。
そのため「採用目標などKPIを厳格化しなくても、十分コストに見合うものだ」と経営陣に理解を促すことも必要に応じて人事から働きかけましょう。
アルムナイ採用をうまく活用する外資系企業の事例
──ここまでご紹介いただいたポイントも踏まえて、アルムナイ採用をうまく導入・運営している事例があれば教えてください。
人材流動性が高い外資系企業、特に戦略コンサルティングファームではアルムナイ採用を古くから活用し、その方法がすでに確立されています。
体制として、アルムナイネットワークを管掌する執行役員と専属スタッフがおり、週2回程度のメール情報発信と超一流ホテルでのアルムナイパーティを実施するなど、非常に大きなコストをかけて運営しています。
私自身も外資系戦略コンサルティングファームに在籍していましたが、退職から10年以上経った今でも毎週2回はメールが届きます。
その内容は経営に影響の大きい社会動向に関する独自の分析、昨今のリーダーシップに関する考察など。
まさに「アルムナイが退職後にどのようなポジションで活躍しているか」を十分に考慮された有用な情報ばかりです。
これだけ質の高い情報を頻度高く受け取ると、メールを開封したくなることはもちろん、「自分はこんなに素晴らしい企業に在籍していたのだ」という自己肯定感にもつながります。
その心境の中でパーティやイベントの案内があると「久しぶりに行ってみようか」という気持ちになりやすく、企業への愛着は増すばかりです。
また、退職者データベースのメンテナンスや活用も極めて丁寧にされていました(戦略コンサルティングファームならではの特性もありますが)。
ある時、現在籍者の後輩コンサルタントからメールがあり、プロジェクトでの調査に関する相談を受けました。それは私の退職後の業務知識に関連するものであり、的確なアドバイスを返すことができたのです。
自分の知見が後輩たちに役立ったという経験は、「もしかすると今戻っても役に立てるかもしれない」という気持ちにつながります。「袖振り合うも他生の縁」とはいうことわざがありますが、外資系戦略コンサルティングファームがそれを体現しているのは大変興味深いものですね。
編集後記
外的変化が激しく、採用においても即戦力がより求められている流れからも、自社理解も外部知見もあるアルムナイ採用はさらに注目されることは間違いありません。
その導入方法や運用ポイントを学んでおくことは、人事担当者として避けては通れないでしょう。
一方で、こういった手法や運用面だけに注目するのではなく、「いかに企業が社員や社外関係者にとって魅力的であり続けるか」といった本質的な部分を考え行動していくこと──それがこれからの時代に人事に求められる力だと、今回のお話を受けて感じました。
人事の困りごとはプロフェッショナルへ頼む時代です
コンサルを雇うよりも安く、派遣社員を雇うより専門的で、 正社員を雇うよりもノーリスクで、貴社の悩みや課題を解決できます。こんなこと困っていませんか??
・採用がうまくいかない
・採用に割ける時間がない
・繁忙期だけ即戦力が欲しい
corner inc.は、手を動かす人事コンサルです。cornerには人事・採用関連の豊富な経験とノウハウを持った頼もしいパートナーが多数登録しています。またcornerのメンバーも人事・採用業務をよく知るものばかり。パートナーを紹介して終わりではなく、実際のプロジェクトにも積極的に関与し、 パートナーとともに課題解決に努めます。お悩みや困りごとをまずはお気軽にご相談ください。
人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチングを支援する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」。
記事提供元

「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」
株式会社コーナーが運営する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」は、採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。
コーナーは1,500名を超える即戦力のプロフェッショナルが登録をし、プロフェッショナルによる課題解決を実働支援型で行います。週1日から必要な業務内容・業務量だけプロフェッショナルの経験を活用できることで、多様化してきている人事・採用課題を効果的に解決します。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
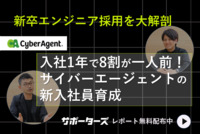
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -

請求書受領サービスの 失敗しない選び方
おすすめ資料 -
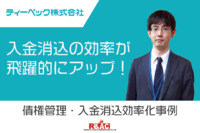
債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -
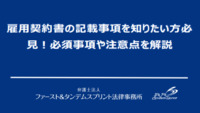
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
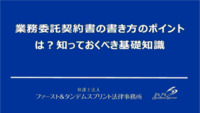
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -
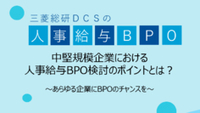
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -
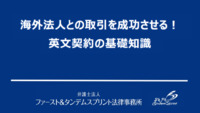
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -
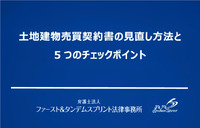
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース
















