公開日 /-create_datetime-/
労務行政研究所が「職場におけるハラスメント」に関する調査研究結果を発表
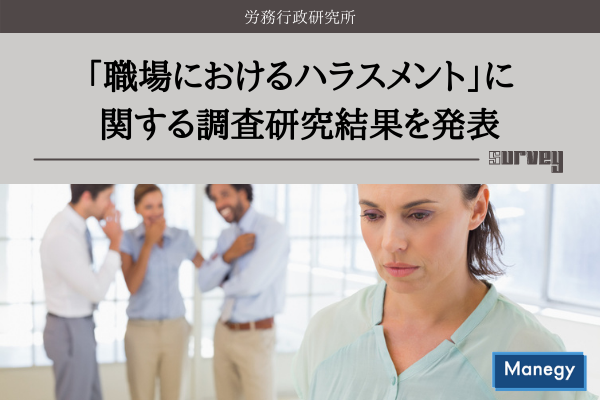
2020年施行のパワハラ防止法によって、職場内でのハラスメント防止に向けた対策がますます重要となってきているが、ハラスメントの実態はどうなっているのだろうか。
民間調査機関の一般財団法人労務行政研究所が、筑波大学・働く人への心理支援開発研究センターの学術指導を受け、職場でのハラスメントの調査研究結果を発表している。
調査は、「被害認識」「加害認識」の観点から実施したが、周囲からの被害行為の認識は31.9%に対し、当人による加害行為の認識は22.2%にとどまっている。つまり、被害者と加害者の間には認識上のギャップがあり、それがハラスメントをより深刻にしているようだ。
約3人に1人がハラスメント被害を受けていると感じているが、「ハラスメント言動」で多いのが「相手が嫌がるような皮肉や冗談を言う」(36.2%)、「陰口を言ったり、悪い噂を広めたりする」(35.5%)などである。
一方、自分自身がハラスメント言動を行ったことがあると認識しているのは4~5人に1人で、「陰口を言ったり、悪い噂を広めたりする」(25.7%)、「相手が嫌がるような皮肉や冗談を言う」(24.7%)である。
「被害認識」と「加害認識」のギャップは、企業規模や職種、職場の人数などによって大きくなる場合もあるようで、被害認識が最も高い年代は30代前半(41.5%)、30代前半より若い層では被害認識・加害認識がともに高く、45歳以降では当人の加害認識が低くなる傾向があることもわかった。
また、周囲のハラスメントへの認識を職位別に見ると、主任・係長、課長相当職が34%台とやや高く、部長相当職が30.4%、役員相当職が19.9%と、役職があがるほど周囲のハラスメントへの認識は低くなっている。
一方、本人が自覚しているかどうかについて、最も高かったのが主任・係長相当職の27.1%で、課長相当職以降の職位では20%台前半で推移している。
主任・係長相当職は、周囲のハラスメントへの認識が高く、また自分がハラスメント言動を行ったという認識も高くなっているが、部長相当職以降は、自分のハラスメント言動への自覚はあるものの、周囲のハラスメントに対して認識しづらくなっていることが考えられる。
職場でのハラスメント防止には、ハラスメントにつながる言動を発しないことはもちろんだが、「自分がハラスメントを行っているのではないか」という意識を、持つことが重要になりそうだ。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
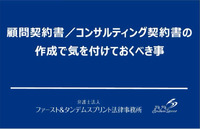
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -
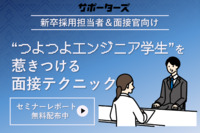
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -
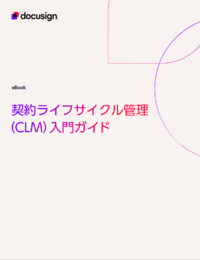
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
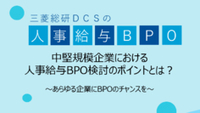
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
おすすめ資料 -
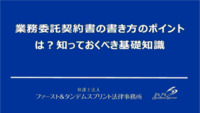
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -
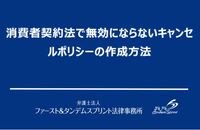
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース
















