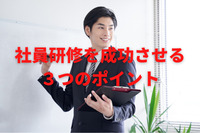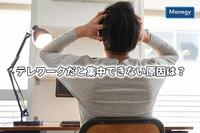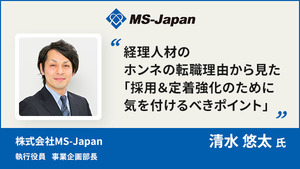公開日 /-create_datetime-/
待ったなしの働き方改革!業務の完全リモート化はこうして実現できた - 株式会社キャスター【特集 2023年に必要とされる人事】
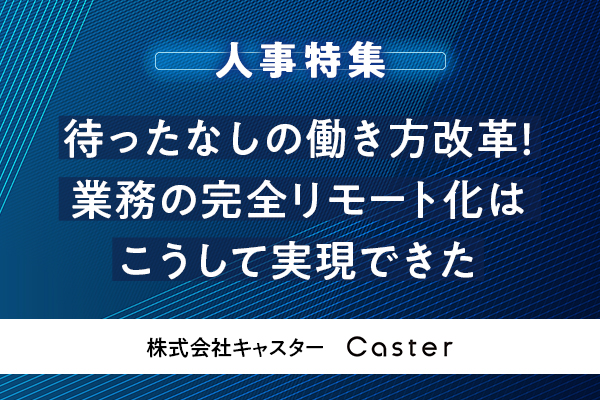
「働き方改革」や新型コロナウイルスの影響により、準備無く「リモートワーク」を余儀なくされた今、バックオフィス業務の在り方そのものが企業基盤の強弱を分けています。
中でも企業基盤である経理や人事労務といった業務が、不測の事態でままならなくなることだけは、どの企業も避けたいはずです。
事実、このコロナ禍でヒヤっとした担当者は多く、更に2023年に実施される「残業60時間」問題も迫っています。弊社ではあらゆる人事労務業務を支援するサービス「CASTER BIZ HR」を運営しており、そのチームで様々なツールを紹介するウェビナーを開催しておりますが、ウェビナー参加者は格段に増えています。
しかも定員を割ることなく出席率も90%を超えているところを見ると、企業にとってリモート化を含む働き方改革は喫緊の課題であることがみてとれます。
なぜ、営業部のような社内外のやり取りが多い部署は、比較的リモートワークへの移行がスムーズに進む一方で、従業員の給与計算や会社のお金を扱う人事・経理といった部署は、部分的な移行にとどまり、完全なリモート化が出来ないのでしょうか。正確には「重要な業務をリモート化することへの壁が壊せないのか」という疑問です。
弊社は2014年の創業時から今に至るまで、経理部も人事部も含め全ての部署がリモートで勤務しています。
前置きが長くなってしまいましたが、今日は、フルリモートを実現するキャスターが、自社の体制をもとに「今後必要な人事とは何か」をお伝えします。
ーキャスターの人事部とはー
簡単に言えば「実在するものをクラウドツールに置き換えて実現した」だけです。クラウドツールに置き換えるうえで必要な対策があるとすれば次の通りです。
・部署配置
例えばオフィスに関していえば、実在するオフィスには、部署やチームごとに部屋やエリアが分かれていますが、それをそのままチャットルームという形で実現しています。上長からメンバーへの周知案内は、チャットルームから全員あてにメッセージが投稿され、メンバーはそのメッセージを受け取ります。
デスクをはさんで会話していることは、このチャット内でやりとりされ、チャット内にいる他のメンバー「誰が」「今何に取り組んでいるか」「何に困っているのか」「どんなプロジェクトが進んでいるのか」が一目瞭然です。このチャットルームは、休憩室や喫煙所といった従業員が息抜きをする場所さえも用意しています。
こういった息抜きをする場所で部署間の交流ができ、業務連携することも珍しくありません。
・機密性の確保
弊社では、あらゆるコミュニケーションをチャットツールを使って行っているため、目的に応じて、オープン・クローズどちらの環境も作ることができます。
部署組織内の情報共有ができるチャット:組織に所属する全員が参加する場所
特定の個人と情報共有するチャット:個人とのダイレクトチャット
・ルールと透明性の確保
チャットツールは先述の通り機密性がもてるゆえに、ともすると共有が行き届かない場所を作ることにもなりかねません。弊社では、入社時から「どんなメッセージも個人的な情報以外はすべてオープンなチャットで投稿すること」を徹底しています。
これが当たり前になると、チャット上での言動を上長がキャッチし、早期にフォローやサポートにとりかかることが可能です。また、すべてのやり取りがチャット上に残るため、自分が発信する言葉にも気を配るようになります。加えて、過去のやりとりがナレッジとして蓄積され、育成機能としても効果を発揮することは、チャットコミュニケーションの副産物でもあります。
ーキャスターの労務管理ー
メンバーの全行動をチャット経由で把握するには、正直なところ限界があります。
一人ひとりが発信したテキストを全部見て回るのはとてつもない時間と労力が必要になるうえに、果てしなくきりがないからです。
弊社では、複数のクラウドツールを組み合わせることで労務管理を行っています。
例えばクラウド型のタスク管理ツールや勤怠管理ツールを使い、「誰が」「どのタスクに」「どれくらいの時間をかけ」「所定終業時間で退勤できているか」「必要な報・連・相ができているか」を把握し、必要な業務改善やフォローを行っています。
特に残業時間管理は、労務管理における大きな課題になる部分で、残業時間から見える業務改善の余地をタイムリーにキャッチして改善に向けた行動を行うのが、人事部にとって大きなカギとなっています。
このように、労務管理がクラウドでできることで、勤怠管理から給与計算といった労務の基幹業務もおのずとクラウドで完結できることは言うまでもありません。
ーキャスターの採用とはー
リモートで労務管理を行う上で大切なことは、メンバー一人一人がTPOに応じた自発的な情報発信ができるかどうかです。
自発的な情報発信ができるかどうかが求められるということは、採用においてこれまで求めてきた「人物像」にも違いが出てきます。その違いとは「基礎的な教育が不要」であるという意味での「即戦力」です。
採用後にどれくらい教育が必要であるか、逆を言えば「いかに教育に掛けるハードルを低く、成果を出せるか」です。
これまでの対面型就労では、業務に必要なスキルがあれば、あとは周りの人がカバー出来る環境にあったため、スキルや実務経験に重点を置いた採用が一般的でした。
これに対し、スキルや実務経験はもとより、自発的な情報発信ができることや、目標に向かって自ら行動する主体性があるかが重点となることから、当社での採用時には「主体性」や「コミュニケーション力」を選考時には重視しています。
ーキャスターの人事評価とはー
弊社では、業務上必要なツールは全てクラウドツールを使っており、人事評価ツールもクラウドツールを使用していますが、多くの企業でお悩みのポイントは「何をどういう基準で評価するのか」でしょう。
これに関してはとてもシンプルで、「数字」です。
「個人の頑張り」という、一見数値化できそうになり項目であっても、「達成率」として数値化することで測ることができると弊社は考えます。定性・定量それぞれ数値化された目標を掲げ、それに向かって行動し、結果が数値になって反映される仕組みです。
この仕組みは労務管理にも紐づき効果が表れます。
数値化することにより、一人ひとりのやるべきこと、目標が明確になり、集中して取り組むことができるため、セルフマネジメントが身につくのです。そうすると終業時間内でいかに効率よく仕事に取り組むかをおのずと考えるようになり、恒久的な残業は存在しなくなります。
ーフルリモートを目指す企業の壁を「ジェンガ方式」で壊すー
弊社がBPOとして人事労務業務をサービス展開している中で、サービスが定着する企業と、そうでない企業の違いが現れるポイントは「業務をクラウドツールに寄せられるか」どうかです。
ここまで、弊社がどのように人事体制を築き、どのように人を採用し評価しているかについてご紹介してきましたが、弊社と他社の違いはまさにこのポイントで「クラウドツールという道具の特性を基準に業務を構築している」という点に尽きます。
裏を返せば、クラウドツールを基準にした業務運用を築くことができれば、どの企業も業務のリモート化は実現できるのです。
ではなぜツールも方法も整っているのに多くの企業が実現できないのでしょうか。それは「古き慣習をとっぱらう」ことが大きな壁になっているからであると考えられます。
この壁にはいろんな小さな壁から成り立っており「費用の壁」「変化への壁」「役員の壁」「社内から起こるハレーションの壁」などなど企業によっていくつもあることでしょう。
こういった壁を担当者・当事者部署だけで解決するのは難しいという現実を、いくつも目の当たりにしてきました。
弊社サービスを検討される企業には、小さな壁を少しずつ壊すために弊社のサービスを利用することをオススメしています。
大きな壁は所詮小さな壁の集まりです。
その小さな壁を少しずつ取り除き、その過程で耐性を持たせることで変化に対するハードルを下げ、最終的に完全クラウド化を目指すといった、まるで「ジェンガ」のような作戦なのです。
ーリモートワークを当たり前にするにはー
新型コロナウイルスの影響でリモートワークを導入する企業は増えているものの、未だに通勤を余儀なくされる人が全く減らない現状があります。
ここ数カ月の採用をみても「コロナの影響をうけ、より家族に近い場所で仕事をしたい」という働く側のニーズが急激に増えています。大手企業で着実にキャリアを積んでいるのに「リモートワークができない」というだけで、優秀な人材が転職を検討しているのです。
2020年はたまたま新型コロナウイルスが働き方を見直す大きなきっかけになりましたが、これまでも大きな自然災害を受けるたび、基幹業務のリスクヘッジに頭を悩ませる企業が増えてきました。
これからの時代には、日本のどこかで災害やその他の要因でオフィス機能がストップしても、業務自体に影響しない体制づくりが必要不可欠になり、こういった体制が整備されている企業こそ、顧客からも働く側からも選ばれるのです。
一過性のリモートワークは、社員へ一過性の変化を強いるにとどまるが、これを機に業務全体を見直し、妥協やリスクなく安定した業務のリモート化が浸透することを切に願っています。
【執筆】

株式会社キャスター
CASTER BIZ accounting/HR事業部
マネージャー 宮川美穂
事業会社や会計事務所で経理・労務の経験を20数年間培い、「この経験を企業の経営基盤強化に役立てられないか」と考えてキャスターに入社。オンラインで経理業務・人事労務業務をサポートするサービスを構築・展開し、日々クライアントを支援している。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

「人事部の実態と業務効率化」に関するサーベイ結果調査レポート【MURC&DCS共同制作】
おすすめ資料 -
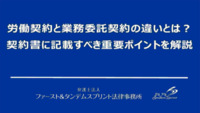
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

「人事給与アウトソーシング(BPO)サービス」導⼊事例集【三菱総研DCS】
おすすめ資料 -
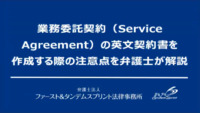
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -
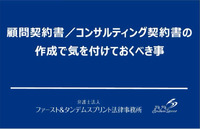
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド
おすすめ資料 -

<人的資本開示 実践編 > 人的資本と組織サーベイ
おすすめ資料 -

BillOneの導入で請求書業務はこう変わる
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース