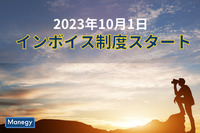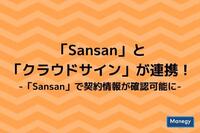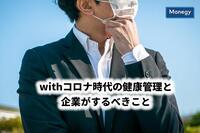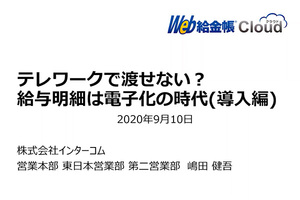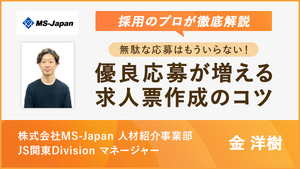公開日 /-create_datetime-/

企業にとって新たに採用した人材が根付かず、早期に退職してしまうことは大きな損失です。それを防ぐために行われてきたさまざまな取り組みが、今「オン・ボーディング」と題して統一的に実践されています。
日本ではなじみのない言葉ですが、その中身は以前から国内企業が取り組んできたことです。それをオン・ボーディングとして進めることに、どのような意味があるのか、ここで改めて分析・検証してみましょう。
目次【本記事の内容】
オン・ボーディングが生まれた背景
まずはアメリカでの事例ですが、アメリカ合衆国労働省労働統計局の調査によると、アメリカの一般的なビジネスパーソンの生涯転職回数は、20年ほど前まで5~6回程度だったものが、現在は10~11回程度に増加しているそうです。
また同局の別の調査では、従業員の退職による追加的なコストは、従業員の年間給与の25~50%にも上るという結果が出ています。こうした状況に危機感を募らせた企業は、1度採用した人材が早く快適に職場環境になじめるような、一貫した取り組みを構築するようになりました。これがオン・ボーディング(onboarding)の始まりと言われています。
日本でも広がりを見せるオン・ボーディングとは?
欧米におけるオン・ボーディングの定義は、一連のプロセスとしての人材育成・教育プログラムです。具体的には、新しく入社した人材が職場でコミュニケーションをとりながら、十分に能力を発揮できるように組織全体でサポートすることです。
日本でも新入社員または中途採用社員に対して、新人研修やOJTによる育成サポートが行われてきました。しかしオン・ボーディングは、より幅広い枠組みの中で長期的なプロセスにより実践されるものです。
その中には新人研修やOJTなどの人材育成以外に、部門内および部門を越えたコミュニケーション向上の取り組みとしての、ミーティングや懇親会なども含まれます。さらに、こうした取り組みに必要な情報提供や社内SNSの構築など、必要なものすべてを包含したシステムがオン・ボーディングなのです。
オン・ボーディングを実践する企業のメリット
企業にとっては、オン・ボーディングの目的そのものがメリットになるでしょう。1つは従業員の定着を促し、離職率を下げることです。これは将来にわたって、その企業を支えてくれる人材を確保すると同時に、採用~教育にかかるコストを抑える意味でも非常に重要です。
また、新たに入社した人材が早期に、しかも長期的に能力を発揮してくれれば、企業にとっては業績アップにもつながります。新しく入ってきた従業員の能力をフルに活用でき、定着率を高められることは、極めて大きなメリットと言えるでしょう。
従業員にとってのオン・ボーディングのメリット
新しい職場では誰もが不安になるものですが、オン・ボーディングの仕組みによって周囲からのサポートが受けられれば、その不安はすぐに安心感に変わるでしょう。自分が期待され大切にされているという思いは、従業員のモチベーション・アップにもつながります。
さらにオン・ボーディングのプロセスにより、従業員はその企業内の情報を迅速に手に入れることができ、通常よりも速いペースで業務になじむことができます。縦と横のコミュニケーションが緊密に取れることも、大きなメリットになるでしょう。
オン・ボーディング実践の注意点
オン・ボーディングをより効果的に実践するためには、何よりも段階的なプロセスを重視することがポイントです。まず企業として注意すべきは、新しい従業員の受け入れ態勢が整っていること。つまりオン・ボーディングが準備万端に整備されていることです。一例として、ここで主な準備事項を挙げてみましょう。
- 研修~教育に至る環境が整備されている。
- 直属の上司、人事部門とのコミュニケーションが構築されている。
- 職場の同僚など周囲のフォロー体制が整っている。
- 必要な情報にアクセスできる環境が整備されている。
- 場合によってはメンター制度(または相談できる窓口)を整える。
こうした準備のもと新たな人材を受け入れてからは、最初にオン・ボーディングの目標設定を行うことが重要です。目標に対してはステップごとにゴールを設け、必要なフォローとフィードバックを行うようにします。
このステップをベースに実施プランを立て、研修やOJTとも連動させながら、長期的なオン・ボーディング計画として継続するとよいでしょう。また、時には食事会や懇親会を開くなど、人の体温を感じられる息抜きの時間も設定しましょう。
専用ソフトを使ったオン・ボーディング
現在はオン・ボーディングを、一体化したシステムとして管理するソフトも登場しています。多くの従業員が関わる手続きを簡略化すると同時に、新規従業員の育成を一貫したプロセスでサポートしてくれるソフトです。
育成に携わる担当者とのマッチングから、その他の従業員とのコミュニケーション構築まで可能で、関係者に必要な情報も一元的に管理できます。企業の規模にもよりますが、将来性を考慮すれば導入を検討してもよいかもしれません。
まとめ
日本人は伝統的に、組織の「和」を大切にしてきました。それはビジネスの世界でも同様で、我々にとって職場での人間関係とコミュニケーションの構築は、業務の遂行と同じくらいに重要な要素です。
オン・ボーディングとは、こうした日本の職場環境に極めてよくマッチする取り組みかもしれません。新規従業員の育成プログラムを、職場のさまざまな人材がサポートするオン・ボーディングの仕組みは、今後日本でも多くの業界に広がりを見せるのではないでしょうか。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

経理BPO業務事例のご紹介
おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
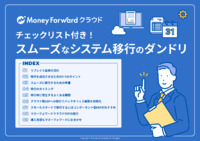
チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ
おすすめ資料 -

「人事給与アウトソーシング(BPO)サービス」導⼊事例集【三菱総研DCS】
おすすめ資料 -

「人事部の実態と業務効率化」に関するサーベイ結果調査レポート【MURC&DCS共同制作】
おすすめ資料 -
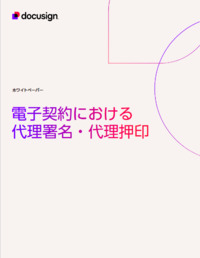
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース