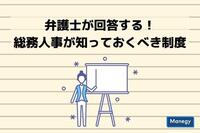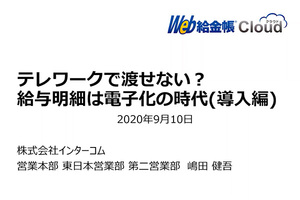公開日 /-create_datetime-/

長期化するコロナ禍で、国が推奨していることも重なってテレワークを導入する企業が増えています。しかし、会社が定めている就業規則の多くは、従業員が出社して働くことを想定したものです。
実際にテレワークを導入する場合に、既存の規則の変更、もしくは新たな規則の設定は必要なのでしょうか。
今回は、テレワーク導入時の規則について詳しく解説します。
テレワークの勤務形態は主に3種類
テレワークとは、「離れたところで」という意味を持つ「テレ(tele)」と「働く」を意味する「ワーク(work)」をつなげた造語です。かつては会社のデスクから離れて仕事をすることは困難でした。しかし現在は社会の情報化が進み、ICT(情報通信技術)を利用することで、本来働く場所から離れて自宅などでも働けるようになりました。
テレワークの就労形態は、主として以下の3種類です。
① 在宅勤務
オフィスに出勤せず、自宅を就業場所とする働き方です。一日に行うべき業務をすべて在宅のまま行うので、通勤・帰宅に要する時間や負担が発生しません。
② サテライトオフィス勤務
本来所属しているオフィスではないオフィス、あるいは遠隔勤務用の施設などを就業場所とする勤務形態です。例えば、本当は本社勤務だが自宅の近くに別のオフィスがあるので、そちらにテレワーク用の作業スペースを設けて就労する、といった働き方が該当します。
③ モバイル勤務
ノートパソコンなどを利用して、交通機関での移動中、もしくはカフェなどで働くことです。営業など外出の多い部署で働く場合、出先でも効率的に仕事を行える環境・設備を整えれば、従業員の生産性向上につながります。
現在のコロナ禍の中では、できるだけ外出を減らすことが推奨されているため、特に普及が促進されているのは①の在宅勤務です。
テレワーク導入時に定めるべき3つの規則
厚生労働省が作成した「テレワークモデル就業規則」によれば、テレワーク勤務を社内に導入する際、就業規則には以下の3点を規定する必要があるとしています。
① テレワーク勤務を命じることに関係する規定
既存の就業規則にテレワークという働き方に対する言及がない場合、新たに「従業員に対し、就業場所および従事する業務の変更を命じる場合がある」といった規定を盛り込む必要があります。もし、テレワーク用の規則を別途設ける場合は、「従業員を在宅勤務させる際の労働条件は、本就業規則および別途定める在宅勤務規定に基づく」などの条項も必要です。
② テレワーク勤務用の労働時間を新たに設定する場合、その労働時間についての規定
テレワークを導入する際、利用しやすい制度としてはフレックスタイム制があります。フレックスタイム制とは、従業員の希望に合わせて、始業時刻と終業時刻を自由に調整できるという制度です。例えば在宅勤務の場合、自宅で働く時間を自由に決定できるようにすることで、働きやすい環境が整います。
ただし、テレワークを導入しても労働時間のあり方を変更しないときは、就業規則を変える必要はありません。
③ 通信費などの負担に関係する規定
従業員がテレワークを行う場合、会社外で電話やインターネットを多用するため、別途通信費が発生します。この費用を会社側、従業員側のどちらが負担するのかを規則として明記することが必要です。
また、在宅勤務の場合だと、もし会社に出勤していたら発生しないであろう水道光熱費などについても、どちらの負担とするのかを規定しておく必要があります。
こうしたテレワークに要する費用を会社・従業員のどちらが負担するのかについては、事前に話し合いの場を設けることも大事です。
テレワーク導入のために就業規則を変更する際の注意点
就業規則は私企業が定めるものですが、決してプライベートなものではありません。内容を変更する場合は、労働基準監督署への届け出を含む適切な手続きを経る必要があります。
就業規則の変更を行うには、まず規則の変更案を作成し、内容について代表取締役などから決裁を受けます。さらに、変更内容について従業員代表から意見書を受け取り、所轄の労働基準監督署に対して「変更後の就業規則」、「就業規則変更届」、「従業員からの意見書」などの提出が必要です。
労働基準法第89条において、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出るべきことが規定されています。そのため、万一就業規則を変更したのに労働基準監督署に届け出をしなかったり、労働者への周知を十分に行わなかったりすると、労働基準法違反となるわけです。
就業規則の作成あるいは変更に伴う届出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金刑に処せられます。
まとめ
テレワークには在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務の3種類があり、コロナ禍の中で普及が進められているのは、外出の必要がない在宅勤務です。実際にテレワークを社内に導入する場合、それに対応した就業規則を定める必要があります。特に、テレワーク勤務を命じることに関する規定、テレワーク用の労働時間に関する規定、通信費などの負担に関する規定などは、最低限定めるべき項目です。
なお、就業規則の内容を変更する場合は、管轄の労働基準監督署への届け出が義務付けられています。怠ると罰則の対象となるので、経営者・担当管理者の方は注意が必要です。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
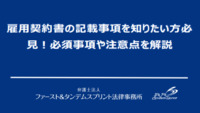
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -
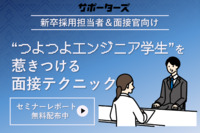
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -
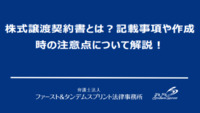
株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -
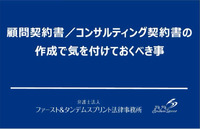
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -
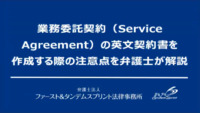
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース