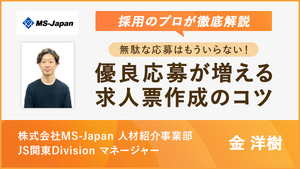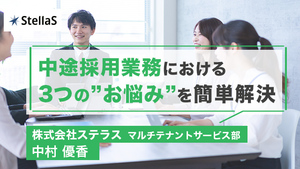公開日 /-create_datetime-/
大掃除って、なぜ年末にするようになったの?
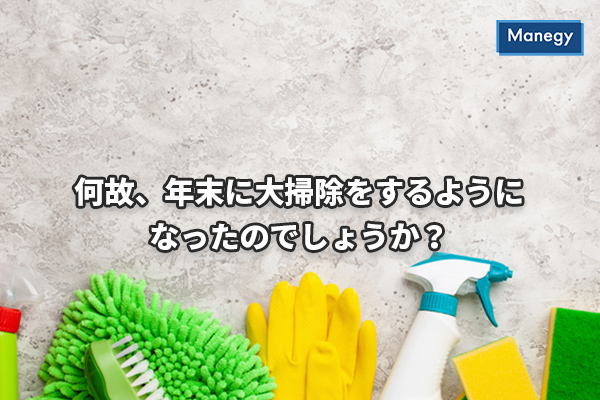
年末になると、やっておかなければならないことが多くありますが、大掃除もその一つでしょう。
なぜ年末なのか考えたことはありますか。ただでさえ忙しく、しかも寒い時期です。暖かい時期に掃除した方が、掃除も捗るような気がします。しかし、実は年末に行うことにはちゃんとした理由があるのです。
年末の大掃除が庶民の間に広まったのは江戸時代
そもそも“掃除”という概念が日本に入ってきたのは飛鳥時代で、中国の仏教思想の影響によるものです。宮中の貴族の間で広まり、それが庶民の間にも浸透するようになったのは平安時代です。
江戸時代になると、徳川幕府が12月13日を「煤納め(すすおさめ)」と定め、江戸城の大掃除が行われるようになりました。庶民も、それにならって自分たちの家の煤払いを行うようになり、それが年末の大掃除という習慣につながっていったようです。
ところで、“煤納め”や“煤払い”といっても、今では神社仏閣などで行う年末の恒例行事でしか、その言葉を耳にすることはないでしょう。
神社仏閣での大掃除は、お正月に訪れる歳神様を気持ちよくお迎えするための神事でもあったわけです。
家も心も清めた状態で歳神様を迎える
さて、昔は、囲炉裏で薪を燃やして暖を取っていました。煙突などがない時代ですから、天井や壁には煤がたまってしまいます。煤を払ってきれいにした家に、歳神様をお迎えしようと、年末の大掃除が定着していったようです。
掃除の“掃”には「払い清める」、“除”には「すべてにわたって」という意味があり、ただ家をきれいにするだけでなく、1年間の厄や穢れを祓う意味合いがあります。
つまり、年末の大掃除には、家も心も清めた状態で歳神様をお迎えするという意味合いが込められているのです。
もちろん、現在の暖房は囲炉裏で薪を燃やしていた時代とは違いますから、煤がたまることはありませんが、埃やゴミは今も昔もたまってしまうものです。
気持ちよく新年を迎えるために、普段よりも大掛かりな掃除をする習慣が、自然に定着していったようです。
6割強が年末大掃除を実施
ところで、年末の大掃除を行っている人はどのくらいいるのでしょうか。ベビーシッター・家事代行サービスの株式会社キッズラインが2020年11月に実施した「大掃除の実態調査」によると、65.8%が「大掃除をする」と回答しています。
ちなみに、実際に昨年大掃除を実施した人は43.8%でしたから、今年は新型コロナウイルスの影響か、大掃除を実施する人が増えているようです。
年末の大掃除というぐらいですから、12月の中旬頃から行うのが一般的ですが、キッズランドの調査では、38.6%が「11月中」と回答しています。昨年の調査では14.5%でしたから、早めに大掃除をしてしまおうという人が増えています。
ここにも、新型コロナウイルスによる新しい生活様式が影響しているのかもしれません。在宅勤務が定着したことで、男性が家にいる時間が増えたこともあるでしょう。また、師走という言葉があるように、12月になれば何かと忙しくなるものです。
それなら、比較的時間的な余裕のある11月から、少しずつ「煤払い」ならぬ念入りな掃除に手をつけていくというのは、合理的な考え方かもしれません。コロナ禍で揺れた今年は、早めに掃除に取りかかり、フレッシュな気持ちで新年を迎えたいものです。
まとめ
年末の大掃除は、単なる1年の汚れを落とすだけでなく、家も心も清めた状態で、歳神様をお迎えする神事だったわけです。そこに込められた意味合いを知って掃除に取りかかると、面倒だと思っていた大掃除も、少し違う視点でとらえることができるのではないでしょうか。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
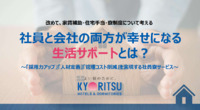
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -
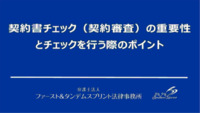
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -
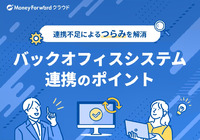
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -
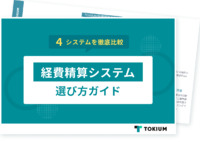
失敗しない!法対応と業務効率化を実現する経費精算システム選び方ガイド【4社の比較表付き】
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
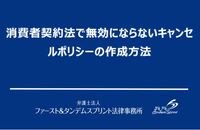
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -
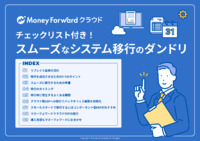
チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ
おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

<人的資本開示 実践編 > 人的資本と組織サーベイ
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース