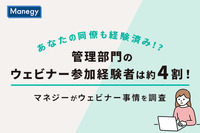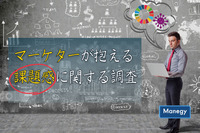公開日 /-create_datetime-/
お歳暮に関して

日本には決まった時期に贈り物をするという、恒例の伝統的な習慣があります。それがお中元とお歳暮です。毎年年の瀬を迎える頃にお世話になった相手にお届けするお歳暮は、ビジネス上での儀礼でもあります。
そのお歳暮にも変化が生まれ、贈る相手や贈り物の内容も変わりつつあります。この記事では、お歳暮のシーズンを迎える前に、上手な贈り物の選び方と、近年広がりつつある「虚礼廃止」の動きについても紹介します。
目次【本記事の内容】
お歳暮の歴史
お歳暮の起源は、日本古来の神様への捧げ物にあると考えられています。それが中国の道教と結びつき、室町時代から江戸時代にかけて武家の間に広まったようです。最初のお歳暮は、武士が自分たちの上司に対して直接届けていたのかもしれません。
その後お歳暮は、江戸時代の商人社会でも広まりました。当時は年に1度か2度に分けて掛け売りの清算があったため、そのときのお届け物として、お歳暮の習慣が根付いたといわれています。
現在のように会社の上司やお世話になった知人、親戚などにお歳暮を贈るようになったのは、明治時代に入ってからのことです。それが今では上下関係にこだわらず、友人や知人に贈り物をする気軽な行事にも変わってきているようです。
お歳暮を贈る意味とは?
一般的には、年賀状やお中元と同様に、お歳暮も普段からお世話になっている相手に、感謝の気持ちを込めて贈るものといわれています。地域によっても意味合いに違いがあり、贈るものもさまざまです。
ではビジネスの視点からお歳暮を見てみると、これも年賀状と同様にリストを作成し、主要な取引先に届けるという習慣が長く根付いています。また仕事上の上司に贈るといった習慣も日本独自の社会的な習慣として定着していました。
お歳暮は日頃の感謝の表現であり、また贈り手のセンスを問われるものでもあるので、ビジネスにおけるお歳暮は、十分に考慮した上で選ぶ必要があるでしょう。
お歳暮ワンポイント(贈る時期)
お歳暮を贈る時期は地方によって違いがあるものの、一般的には11月下旬から12月いっぱいと考えればよいでしょう。正月用の生鮮食品であれば、正月前のタイミングで届けるのもよいですが、日持ちのする食品や食品以外であれば、忙しくなる年の瀬の前、25日頃までには相手に届くように手配しましょう。
お歳暮の選び方
お歳暮選びは、相手によって値段をランク分けするケースがほとんどです。常識的な相場では3~5千円が基本で、特にお世話になっている相手に対しては、5千円~1万円が目安となるでしょう。
何よりも悩むのが贈り物の内容ですが、事前に相手の好みをリサーチできればベストです。それが分からないときには、相手の年齢や家族構成を考慮して、役に立つもので相手が困らないものを選びましょう。
仕事でお世話になっている相手には、普段使いではない高品質な商品から選ぶことも一つの方法です。ただし毎年同じレベルのお歳暮を贈るということも忘れないでください。どうしても決められない場合は、カタログギフトも選択肢の一つです。
お歳暮ワンポイント(贈ってはいけないもの)
お歳暮を贈る上でのマナーとして、贈ってはいけないと決められているものもあります。靴下や肌着類、刃物、金券や現金は相手に対して極めて失礼に当たるので、絶対に選んではいけない商品です。
また相手が公務員の場合や、贈り物の受け取りを断っている場合は、お歳暮を贈ることは避けましょう。相手が喪中の場合は、熨斗(のし)の色を変えるなどすれば贈っても問題ありません。
2020年人気のお歳暮は?
お歳暮には大きな流行の変化はありません。また、毎年違ったものを選ぶという配慮も必要ないでしょう。最も需要が多いのは、肉類やハムなどの詰め合わせ、カニやシャケなどの缶詰、和洋菓子のセットなどです。
ほかには、相手に合わせる必要がありますが、お酒類も人気が高く、生鮮品では季節の果物も喜ばれます。正月が近いこともあり、全般的に高級感が漂う食料品が多いようです。また最近では、好きな商品を選べることから、カタログギフトの需要も増えています。
お歳暮ワンポイント(お礼・お返し)
ここまでは贈る側の立場から考えてきましたが、反対にお歳暮を受け取った場合には、お礼やお返しは必要あるのでしょうか?
この点、ほかの贈り物と違って、お歳暮にはお返しの必要がありません。ただし必ずお礼はしておきましょう。親しい間柄であれば、電話やメールだけでも十分です。重要な取引先などに対しては、礼状を送ることをおすすめします。
どうしてもお返しをしておきたいときには、少し日にちを空けてから、「お年賀」や「寒中お見舞い」などの名目で、受け取ったお歳暮の半額程度の商品を贈ればよいでしょう。
広がる虚礼廃止の動き
伝統的に続いてきたお歳暮という習慣ですが、最近では「虚礼廃止」として、形式だけになった儀礼を見直す動きから、ビジネスでも個人でも廃止する動きが広がっています。これはお中元や年賀状でも同様です。
廃止するとはいえ複雑な手続きを要することではなく、虚礼廃止する旨の丁寧な案内状を相手に送り、同時に受け取る場合の贈り物も辞退することを伝えれば問題ありません。ビジネスでは業務効率化とコスト削減につながるメリットもあります。
まとめ
お歳暮とはお祝いの儀礼ではなく、日本で独自に発展してきた贈り物の習慣です。何を贈るのかは自由ですが、やはり相手が喜ぶ品物を選びたいものです。またビジネス関係では、贈り物選びのセンスが問われる可能性もあります。
とはいえお歳暮の根底にあるものは、相手に対する感謝の心です。相手のことを考えながら選ぶ気持ちがあれば、きっとよいお歳暮が贈れるでしょう。またこの機会に、形だけになった儀礼を見直してみるのもよいかもしれません。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
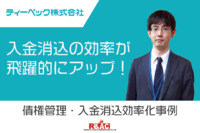
債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -
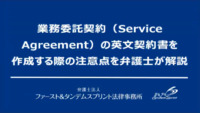
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -
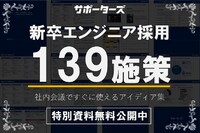
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -

若手社員の早期離職を防止するためにできること
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース