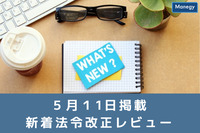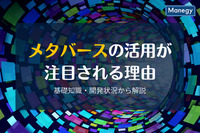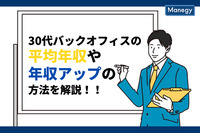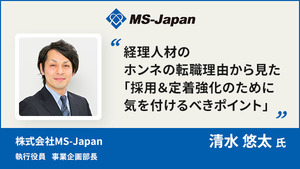公開日 /-create_datetime-/

従業員を公平に評価することは、企業経営の中でも難しい問題の1つです。さらに慢性的な人材不足が続く現在においては、従業員のモチベーションを高め離職率を抑える上で、人事評価の重要性がますます高まっています。
そこで今回のテーマでは、従業員が人事評価に対して普段から感じている不満と、そこから生じるさまざまな問題を分析し、今後の人事評価にどうやって生かすべきかを解説します。
人事評価に対する一般的な意識
日本国内の一般企業を対象に行われた、2015年と2018年の人事評価に関する調査結果を見てみると、企業が抱える問題点がはっきりと浮かび上ってきます。
これらの調査は別々の機関が行ったもので、直接的な比較は難しいのですが、2015年の調査では人事評価に不満を持っている人の割合は3割以上という結果でした。対する2018年の調査では、実に6割以上の人が不満を感じているという結果になっています。
不満を感じる割合には差があるものの、不満を感じる理由については、ほぼ同じような意見が上位を占めています。最も大きな理由は、「評価基準が不明確」ということです。
その他にも評価者の価値観によって人事評価が左右されることや、自分が考えている評価に比べて、実際の評価が低すぎることが主な不満の理由になっています。いずれにせよ、評価基準のあいまいさに対する不満が最大の問題だと言えるでしょう。
この点は評価する側の上司を対象にした調査結果にも表れており、数値化しにくい業務の場合、評価者の多くが評価に難しさを感じているようです。これらの結果をまとめると、適切な評価基準を設けることが、公正な人事評価を行うカギを握っているのかもしれません。
不適切な人事評価で生じる問題点
従業員が人事評価に不満を持つと、その結果は仕事に対するモチベーションの低下として表れます。直接的には業務実績の悪化という形で見えてくる可能性があります。つまり不満を持つ従業員が多いほど、企業の業績そのものが悪化してしまうのです。
また不満が解消されないまま先が見えない状況が続くと、従業員は退職や転職という選択肢を考え始めます。現在は転職斡旋業が活況を呈していることもあり、特に若い世代は転職することに抵抗を感じません。
貴重な人材が流出してしまえば、企業にとってはやはり業績悪化が避けられません。こうした問題点を解決せずに放置しておくことは、企業の存続に関わる重大事なのです。
どのように適切な人事評価を行うべきか?
人事評価に関する調査結果を参考にすると、最も必要なことは明確な評価基準に従って人事評価を行うことでしょう。そのために必要な主な対策をまとめてみます。
従業員に評価基準を公表する
従業員が具体的な評価基準を知っていれば、客観的に自分自身を見直すことができます。定期的に評価基準を説明し、従業員がいつでも確認できるシステムがあれば、不満の解消につながるかもしれません。
評価者の基準を統一する
評価者ごとに基準のバラつきがあると、適正な人事評価を行うことができません。管理職に対する研修などを定期的に実施して、評価基準を統一することが重要です。
評価ごとにフィードバックを行う
従業員は評価の理由がはっきり示されないと不満を感じます。どのような点を今後改善すべきかを正確に伝えることと、高評価だった点についても理由を説明したほうがよいでしょう。
評価者と従業員がコミュニケーションをとる
普段から評価する側とされる側、つまり上司と部下がコミュニケーションを密にとっていれば、不満が蓄積して大きな問題に発展することはありません。やはり普段からの人間関係が重要なのです。
一般企業とは環境が違いますが、国家公務員の人事評価基準の一例を紹介します。公務員では年1回の能力評価と、年2回の業績評価が行われます。
どちらも10月1日を期首として、最初に評価者と被評価者とで面談を行い、被評価者は年間の達成目標を設定します。さらに期末に被評価者は目標達成について自己申告を行います。最終的に人事評価が実施されたあと、再び評価に関する面談が行われます。
一般企業でも、こうした流れを積極的にシステム化することが求められているのでしょう。
人事評価システム導入という選択肢
人事評価の明確化のために、思い切って専用のアプリケーション・システムを導入するという方法もあります。このシステムのメリットは、基準に沿った人事評価を完全に自動化できることです。
さらに従業員の目標設定や評価のフィードバック、評価を具体的な業務に反映することなど、すべての流れを一貫したシステム上で運営できます。そして何よりも、極めて客観的な評価をくだせる点で、人事評価に対する不満を大幅に減らせる可能性があります。
まとめ
人事評価はする側にとっても、される側にとっても難しい問題です。それをスムーズに行うためには、組織としての評価基準を明確にして、開かれたシステムを構築することが重要です。
企業のような組織も、やはり人と人とのつながりで成り立っています。普段から組織内でのコミュニケーションを大切にすることが、不満の少ない人事評価を行うための最大のポイントなのかもしれません。

HRMOS評価は、株式会社ビズリーチが提供する「人事評価システム」です。人事評価プロセスの50%をシステムで代替し、評価業務を効率化します。またリアルタイムフィードバック機能などを備え、評価の運用をサポートします。

人事評価から人材データ活用、 タレントマネジメントまで カンタン・シンプルに戦略的な人事を実現
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
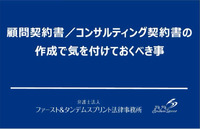
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -
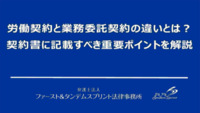
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

「人事給与アウトソーシング(BPO)サービス」導⼊事例集【三菱総研DCS】
おすすめ資料 -
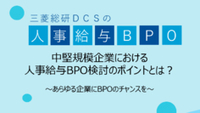
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
おすすめ資料 -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
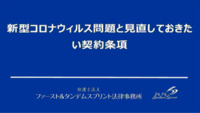
新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -
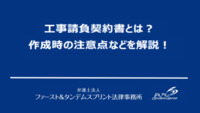
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース