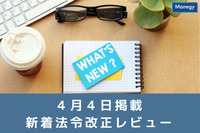公開日 /-create_datetime-/

経営指標の一つとされているのが、「労働分配率」(付加価値に占める人件費の割合)です。簡単にいえば、会社が上げた利益から、どの程度、従業員に還元されているかを示す指標ですが、この労働分配率から何がわかるのでしょうか。
「人件費÷付加価値=労働分配率」
労働分配率は、「人件費÷付加価値=労働分配率」で計算します。「付加価値」とは、事業活動によって企業が生み出した利益から、仕入れや外注費などの経費を引いたもので、粗利や限界利益と表現している企業もあります。
労働分配率、つまり従業員への還元割合が高ければ高いほど、従業員に多く分配しているということになります。しかし、人件費は企業活動を支える源泉ではありますが、企業にとっては、最大のコストでもあります。
労働分配率が高すぎると、利益が少なくなりますし、低すぎると、稼ぎに対する給料が少ないと、従業員の不満が出ることになるでしょう。では、適正な労働分配率とは、どの程度なのでしょうか。
日本企業の労働分配率の平均は47.7%
日本の企業の、平成29年度の労働分配率は、全業種平均で47.7%(平成30年企業活動基本調査速報・経済産業省)です。業種毎に収益構造が異なりますから、労働分配率を一律に論じることはできませんが、50%~60%弱が一般的な目安のようです。
【経済産業省:平成30年企業活動基本調査】
製造業 46.1%
情報通信業 55.4%
卸売業 48.4%
小売業 49.5%
クレジットカード、割賦金融業 29.7%
飲食サービス業 64.0%
全業種合計 47.7%
このデータから、飲食サービス業の労働分配率が高く、金融系事業の労働分配率が低くなっていることがわかります。
飲食サービス業は、対面接客が基本で労働力が売り上げに大きく左右します。一方、システム投資などの負担が大きい金融系事業は、労働力の比重が下がりますから、当然、労働分配率も低くなるようです。
労働分配率が適正にコントロールされているかを確認
総務や経理の担当者は、自社の収益費用構造に合わせた、適正な労働分配率はどの程度なのかを押さえておく必要があるでしょう。そのためには、まず、数年間の損益計算書見比べ、どのような推移になっているかご確認することです。
ここで見極めるポイントとなるのが、人件費が企業の実力に応じた分配になっているか、人件費に応じたパフォーマンスを従業員が出せているか、経営数値に生産性向上の取組みの成果が表れているか、などです。
大切なのは、労働分配率が適正にコントロールされているかどうかです。日本は、労働人口の高齢化、同一労働同一賃金、政府のインフレ政策などにより、1人あたり人件費は上昇傾向にあります。
企業側の立場では、できるだけ人件費を抑え、そのうえで労働生産性を上げることができれば、高収益につながります。しかし、人件費を抑えることは従業員のモチベーション低下につながりますから、労働分配率を適正に保つことが重要となります。
そのためにも、自社の収益費用構造に合わせた適正な労働分配率を、把握しておく必要があるのではないでしょうか。
まとめ
労働分配率は、事業活動で獲得した利益が、従業員にどれだけ分配されているのかを示す重要指標です。労働分配率が高すぎれば経営を圧迫し、低すぎれば従業員の不満となります。会社にとっても従業員にとっても、納得のいく労働分配率を保ち続けることができるなら、その企業の将来性は“明るい”といえるのではないでしょうか。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -
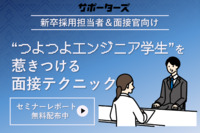
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

食の福利厚生【OFFICE DE YASAI 】
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -
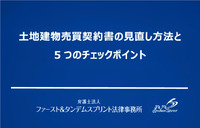
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -
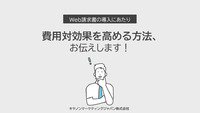
Web請求書の導入にあたり費用対効果を高める方法、お伝えします!
おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース