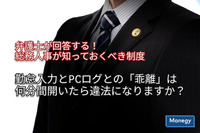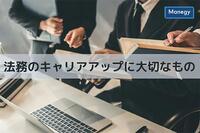公開日 /-create_datetime-/

近年、少子高齢化の進展に伴う労働力人口の減少、経済のグローバル化の進展という2つの要因が合わさって、外国人人材への注目度が高まりつつあります。しかし、実際に企業で外国人を雇用する場合、就労ビザが必要です。
就労ビザの発行には複雑な手続きを要するため、いざ申請するとなるとややわかりにくい面があります。
そこで今回は、企業における外国人採用の現状を紹介した上で、就労ビザとはどのような在留資格なのか、就労ビザを取得するにはどんな手続きを経る必要があるのか、について詳しく紹介しましょう。
増え続ける外国人労働者数
厚生労働省の「外国人の雇用状況」によると、2018年(平成30年)10月末時点において、日本で働く外国人労働者数は約146万人となっており、2012年以降は右肩上がりで増え続けています。特にここ2,3年の増加率は高く、2016年に100万人を突破してから、わずか2年で150万人近くに達しました。
2018年の外国人労働者数を国籍別にみると、最も多いのは中国人の38万9,117人で、全外国人労働者の26.6%を占めています。次に多いのがベトナム人の31万6,840人(同21.7%)、3番目がフィリピン人の16万4,006人(11.2%)です。
外国人を採用するメリットとは?
外国人を雇用することで、企業側が享受できるメリットは数多くあります。
まずは、企業の規模を問わず生じている人材不足を解消できるという点です。特に、最近では能力の高い優秀な若手人材を海外から確保するケースが増えています。
また、将来的に海外進出を考えている企業にとって、進出先の出身者の労働者を雇用すると、文化・慣習の認知や現地の情報収集をしやすいです。
特に各国の慣習・行動傾向については、日本人にはわかりにくい面もあるため、外国人労働者が心強い味方となってくれるでしょう。
さらに、外国人労働者は日本人労働者とは母国語や背景とする文化も異なるので、日本人とは異なる発想、アイデアを思いつきやすいといわれています。新鮮な意見や見方を取り入れることで、それまで気が付かなかった課題やビジネスチャンスを発見しやすくなるわけです。
外国人が日本で働くには就労ビザが必須
就労ビザとは、その国で働くことが認められている在留資格のことです。外国人が日本に滞在することを認められる在留資格には様々な種類がありますが、就労が認められていない資格があります。
例えば、日本文化や日本の格闘技を学ぶために来日する「文化活動」の在留資格では、日本で働くことはできません。あるいは、政府機関や企業の技術訓練を目的に来日した「研修」の在留資格も、就労不可です。
一方、以下の在留資格は働くことができる就労ビザに該当します。
①「活動に基づく在留資格」のうちで就労できる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職1号(人文科学、経済などの分野で法務省令の基準を満たす人)、高度専門職2号(同1号として3年以上勤務)、経営・管理、法律・会計事務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、工業、技能、特定技能1号・2号(法務大臣指定の業務)、技能実習1号・2号・3号(技能実習生)。
なお、外国人の活動には多様性があり、上記の区分にあてはまらないケースも多いです。それらについては、法務大臣が各外国人について個別に指定する「特定活動」の在留資格として扱われます。
特定活動に該当するのは、アマチュアスポーツ選手やインターンシップ生、外交官等の家事使用人、経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者などです。それら特定活動のうち、個々の許可の内容によって、就労できるか(報酬を受け取れるか)どうかが決まります。
②身分又は地位に基づく在留資格・・・就労可
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
これらのうち日本企業が外国人を雇用する場合、取得する在留資格のほとんどは以下の5つのケースです。
・「技術・人文知識・国際業務」・・・理学・工学系、外国人教師や通訳、デザイナー、法律学や経済学などの知識を有する業務に従事。
・「経営・管理」・・・会社の社長・役員、管理者など。
・「技能」・・・調理師や調教師、パイロット、スポーツトレーナーなど。
・「企業内転勤」・・・海外にある日本企業の支店や子会社から、国内の本社などへ転勤。
・「特定活動」・・・特定活動に該当し、内容により就労が認められる場合。
外国人が就労ビザを取得するまでに必要な手続き
実際に外国人が就労ビザを取得して、日本企業で働くために必要な手続きについてご紹介しましょう。通常は以下のような順序で行われます。
①本人が海外でパスポートを取得します。
②雇用する日本企業が、地方入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出します。
③地方入国管理局が審査を行い、特に問題がなければ、申請のあった企業と海外に住む雇用予定の本人に対して在留資格認定証明書が交付・送付されます。
④本人が居住する国の在外公館で査証申請を行い、特に問題がなければ査証が本人に発給されます。
⑤本人が航空機などで来日し、出入国港にて上陸審査を受けます。その際、在留資格・在留期間が決定されます。就労できるのは定められた在留期間(最長でも5年又は3年、技能実習生1号は最長で1年)の間のみです。審査後、在留カードが交付されます。
⑥市町村の窓口に行き、居住地の届け出を行います。
まとめ
人手不足に苦しむ日本企業が多い中、外国人労働者への注目と期待が高まっています。
ただし、実際に外国人が日本企業で働く場合、就労ビザの取得が必要です。就労ビザを得て日本で働くまでの手続きのプロセスには、雇用する企業も「在留資格認定証明書交付申請」などを行うことが求められます。
特に初めて外国人労働者を迎えようとする企業の場合、問題なくスムーズに雇用できるように、採用担当者は事前に制度の理解を深めておきましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
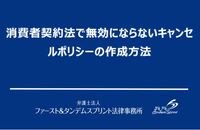
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -
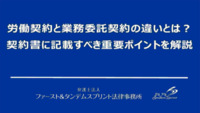
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

食の福利厚生【OFFICE DE YASAI 】
おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース