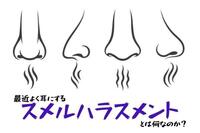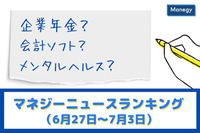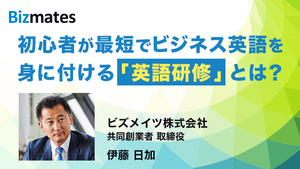公開日 /-create_datetime-/
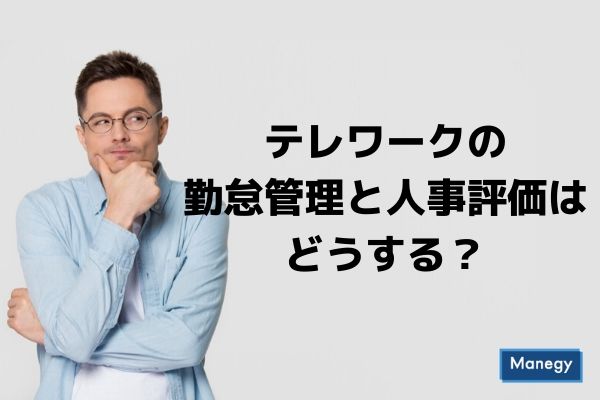
新型コロナウイルス感染症対策で突然テレワークを導入した企業は、今まさにさまざまな課題を抱えています。特に、管理部門が早急に取り組まなければならないのが、テレワーク中の勤怠管理と人事評価の調整です。オフィスで働くときと異なり、テレワークに応じた対応が求められています。
本記事では、テレワークの勤怠管理と人事評価について知っておくべき事柄をまとめました。
テレワーク中の従業員が感じている不安と悩み
テレワーク中の従業員は、上司と部下それぞれの立場で不安と悩みがあるようです。
人事評価クラウドで企業を支援している株式会社あしたのチーム(本社:東京都中央区、代表取締役社長:髙橋恭介氏)は、全国の20~59歳の会社員(直近1か月以内に週1日以上テレワークをした一般社員150人、テレワークをした部下のいる管理職150人、計300人)を対象に、テレワークと人事評価に関するインターネット調査を実施しました(調査期間:2020年3月31日~4月1日)。以下は主な調査結果です。
●テレワーク時の不安
・管理職が部下に対して感じていること
1位「生産性が下がっているのではないか」48.0%、同率2位「報連相をすべき時にできないのではないか」、「仕事をサボっているのではないか」各32.7%
・部下が不安・不便に感じていること
1位「オフィスより仕事がはかどらないこと」38.7%、2位「上司・同僚・部下に相談しにくいこと」28.7%、 3位「サボっていると疑われているのではないか」28.0%、4位「残業申請がしにくいこと」27.3%
→テレワーク中は互いの仕事ぶりが見えないため、管理職は部下の仕事ぶりを、部下は自身の仕事や上司・同僚などとのやり取りを不安・不便に感じていることが判明。
●テレワークの人事評価
・テレワーク時の部下の人事評価について「オフィス出社時と比べて難しい」73.7%
・テレワーク時の人事評価が難しい理由 1位「勤務態度が見えないから」72.6%、2位「成果につながる行動(アクション数、内容等)を細かく把握しづらいから」67.1%、3位「勤務時間を正確に把握しづらいから」45.2%
・テレワークを前提とした人事評価制度、管理職は52.4%が「見直し・改定する必要がある」と回答
・テレワークに適していると思う人事評価制度は「成果(数値結果)をもとにした評価制度」77.0%が最多
→勤務態度や業務プロセスが見えないゆえに、これらを重視した従来の人事評価では判断しづらく、成果で判断する評価制度が必要と考えている人が多い。
上記アンケート結果のとおり、一般社員・管理職のどちらも、テレワーク時の業務管理・人事評価の難しさを感じているのがわかります。
テレワークの勤怠管理・人事評価 国の指針は?
厚生労働省と総務省は、テレワーク導入にあたってのガイドラインなどを公表しています。以下は勤怠管理と人事評価について、厚労・総務両省で示している指針です。
【勤怠管理(労働時間)について】
厚生労働省「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」より一部抜粋
■通常の労働時間制度
・使用者はテレワークを行う労働者の労働時間についても適正に把握する義務を有する。
・テレワークもフレックスタイム制を活用可能。あくまで始業・終業の時刻を労働者に委ねる制度のため、労働時間の把握が必要。
■事業場外みなし労働時間制(指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難なとき)
・勤務状況を把握し、適正な労働時間管理を行う義務を有する。
■裁量労働制
・勤務状況を把握し、適正な労働時間管理を行う義務を有する。
いずれの働き方においても、勤務状況を把握して適正な労働時間管理を行うことが必要です。通常の労働時間制度の場合、例えばパソコンの使用時間を記録するなどの管理方法が当ガイドラインに記載されています。また、厚生労働省は別の手引きで、「在宅勤務者が作成した業務日報をチェック」することもすすめています。
【人事評価について】
総務省「テレワーク運用ガイド(企業のマネージャー向け導入ガイド)」より一部抜粋
・マネージャーとテレワーカーとの間で、テレワークで行う業務内容とその成果について共通の理解を持つ。
・仕事内容、コミュニケーションの方法等により、オフィス勤務のときと同様に評価することも可能だが、「人物評価」重視から「仕事や業績評価」の成果主義重視に移行することも考えられる。
前述のアンケートの紹介部分でも触れましたが、テレワーク中は部下の勤務態度や業務プロセスが上司には見えません。近年の日本では、成果だけでなく仕事への取り組み方も大切にする“プロセス・人物重視”の人事評価を行う企業が増えています。しかし、テレワークはこの方法では正当に評価しづらい働き方であり、最も判断しやすいのは“成果”です。
かと言って、全社で“成果主義”の人事評価にいきなり変えるのもおすすめはできません。特に、同じ企業でテレワークの人とオフィスで働く人がいる場合、それぞれの働き方に合わせてプロセスと成果の両方を踏まえながら評価をするのが望ましいでしょう。テレワークの従業員に対しては、プロセスをきちんと表せる仕組みをつくり、成果と共に見るべきです。
新型コロナウイルス感染症対策で突然テレワークになった職場では、管理職だけでなく一般社員も、業務管理や人事評価に対して不安を持っています。大変な状況ではありますが、社内で積極的にコミュニケーションをとり、各制度をいま一度見直して改良していくよい機会でもあります。
例えば、人事管理システムや人事評価システムなどを導入するのもひとつの手です。提供各社のサービスを比較し、自社に合ったものを選べば、従業員が納得できる体制に整えられるでしょう。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。
【編集部お勧めの関連サービス】
コンプライアンスに強い勤怠管理システム『MINAGINE就業管理』
勤怠管理システム『MINAGINE就業管理』は、人事労務のプロフェッショナル集団が開発したコンプライアンスに強い勤怠管理システムであり、一部上場企業から新興系のベンチャー企業まで「労務管理をしっかりとしたい」「働き方改革関連法に対応させたい」企業に幅広く利用されています。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -
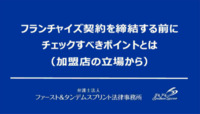
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

<人的資本開示 実践編 > 人的資本と組織サーベイ
おすすめ資料 -

三菱総研DCSが取り組む「ダイバーシティー経営」への第一歩
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -
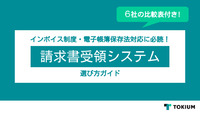
失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】
おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース