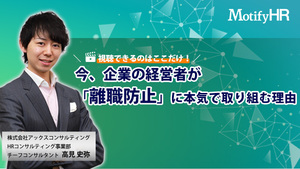公開日 /-create_datetime-/

経済産業省では、わが国企業の経営戦略や産業構造の変化の実態を明らかにする「経済産業省企業活動基本調査」を実施していますが、この度、2019年調査結果(2018年度実績)の速報版が公表されました。
売上高は増加するも利益は減少傾向
経済産業省企業活動基本調査の対象業種に格付けされた企業は28,270社で、1企業当たりの売上高の前年度比はプラス1.3%と2年連続の増加となり、1企業当たりの経常利益の前年度比はマイナス3.2%減と7年ぶりに減少しました。
また、付加価値額は、営業利益の減益などにより減少し、労働分配率は、給与総額が増加し付加価値額が減少したことから上昇しています。
それでは、1企業当たりの売上高と経常利益について、産業別にみていきましょう。
主要産業別の売上高状況と利益の状況
2018年度の1企業当たりの売上高を主要産業別にみると、製造業は228.0億円で前年度比1.3%増、卸売業は420.5億円(前年度比3.7%増)で2年連続増加しています。一方、小売業は246.8億円で前年度比2.9%減となり、2年ぶりの減少となっています。
しかし、営業利益となると、製造業、卸売業は3年ぶり、小売業は2年ぶりに減少に転じ、1企業当たりの経常利益は13.3億円で、前年度比3.2%減と7年ぶりに減少となっています。
主要産業別にみると、製造業は16.6億円(前年度比4.8%減)、卸売業は13.3億円(前年度比1.0%減)、小売業は7.3億円(前年度比4.1%減)となり売上高が増加している産業が多い割には、軒並み利益率は減少傾向にあるということが、この速報版から読み取ることができます。
経常利益の減少が目立つのは、製造業では化学工業、輸送用機械器具製造業、石油製品・石炭製品製造業、卸売業では産業機械器具卸売業、石油・鉱物卸売業、小売業では機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業などです。
付加価値額と労働分配率及び労働生産性の状況
営業利益、給与総額、減価償却費、福利厚生費、動産・不動産賃借料、租税公課を合わせた付加価値額をみていくと、給与総額などは増加しましたが、営業利益が減少したことにより、128兆2,968億円で前年度比0.7%減となりました。
産業別では、製造業が62兆1,399億円(前年度比1.7%減)、小売業が16兆6,765億円(同1.6%減)でしたが、卸売業は営業利益の減少幅が小さかったため、前年度比0.2%増の16兆5,472億円となっています。
付加価値額が減少し、給与総額が増加したことで、労働分配率は、前年度より1.0ポイント増の48.7%となりました。産業別では、製造業47.8%(前年度比1.7ポイント増)、卸売業48.6%(同0.1ポイント増)、小売業49.9%(同0.5ポイント増)です。
一方、日本産業が抱えている課題の労働生産性は、付加価値額が減少し、常時従業者数が増加したことにより、前年度比マイナス1.0%減少の884.2万円です。
産業別では製造業1,170.3万円(前年度比マイナス1.8%減)、小売業497.1万円(同マイナス0.9%減)が減少し、卸売業は1,093.0万円と前年度比プラス1.3%の増加となりました。
まとめ
売上が伸びれば、利益が上がるというほど企業活動は単純なものではありません。また、労働分配率や労働生産性の向上にも取り組んでいく必要があります。経営者はもちろん、企業活動を支える経営戦略の担当者は、わが国の産業構造の変化の実態を把握しておく必要がありそうです。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -
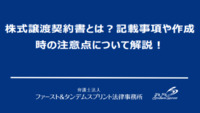
株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

三菱総研DCSが取り組む「ダイバーシティー経営」への第一歩
おすすめ資料 -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント
おすすめ資料 -
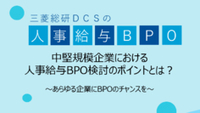
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
おすすめ資料 -

経理BPO業務事例のご紹介
おすすめ資料 -
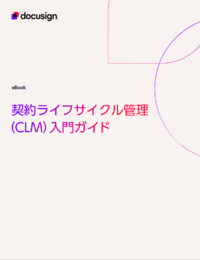
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
ニュース