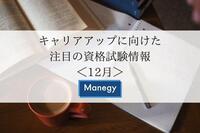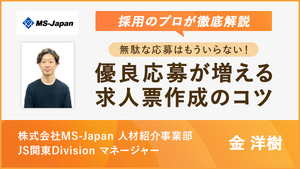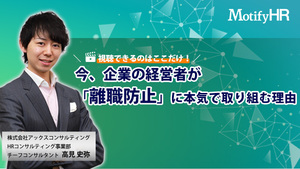公開日 /-create_datetime-/
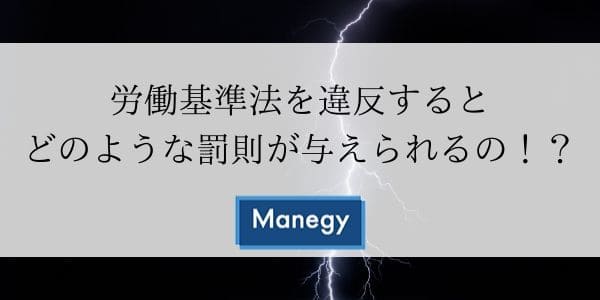
労働基準法違反は、労働環境整備の最低基準を定めた法律です。ところが、管理者が労働基準法に対する認識が甘かった、その他様々な理由で法違反を犯し、労働基準監督署からそれを摘発されるケースが後を絶ちません。もしそれが、送検事案になった場合は社名が公表され、社会信用失墜を招くリスクもあります。労働基準法違反を犯さないために、その関守である総務担当者はどうすれば良いのでしょうか。
そもそも労働基準法とは?
労働基準法とは労働条件の最低基準を定めた法律です。同法は第1条で「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と定めています。
同法は企業の労務管理の羅針盤といっても良いでしょう。
同法は第一章 総則、第二章 労働契約、第三章 賃金、第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇など13章121箇条で構成されており、労働条件の最低基準を詳細に規定しています。
同法は第9条で「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しており、同法は労働者すべてに適用されます。総務担当者は、企業を対象にした業法ではないことを認識しておく必要があります。
同法の規定は多岐にわたりますが、総務担当者が現場を預かる管理者等に、特に周知徹底してきたいのが次の基本的な規定といえます。
(1)労働条件の明示ː第15条
(2)解雇制限ː第19条
(3)賃金の支払いː第24条
(4)労働時間ː第32条
(5)休憩ː第34条
(6)休日ː第35条
(7)時間外及び休日の労働ː第36条
(8)時間外、休日及び深夜の割増賃金ː第37条
(9)年次有給休暇 ː第39条
(10)未成年者の労働契約ː第58条
(11) 危険有害業務の就業制限ː第64条の3
(12)産前産後ː第65・66条
(13)罰則ː第117―121条
労働基準法を違反すると与えられる罰則
労働基準法違反容疑で労働基準監督官が立入調査し、悪質と判断して送検し、有罪判決を受けた場合、罰則を受けるのは「使用者」です。
使用者について、労働基準法は第10条で「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」と定義しています。
すなわち、経営者と管理者はいうに及ばず、「その事業の」実質的な業務権限を持ち、「労働者」の指揮監督を行う者すべてが使用者となります。
したがって、仮に部課長、作業長、店長などの肩書がついていても、実質的な業務権限がない「名ばかり管理者」の場合は罰則の対象になりません。
さらに同法は、第121条で「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する」と、経営者と使用者の両方に罰則を科す「両罰規定」設けています。
同法の罰則は4段階に分かれています。それぞれの罰則とその対象となる主な違反行為は次の通りです。
(1)1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
強制労働の禁止違反
(2)1年以下の懲役または50万円以下の罰金
中間搾取・児童の使用・18歳未満の者の坑内労働禁止違反
(3)6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
均等待遇違反、男女同一賃金の原則違反、労働契約不履行に対する損害賠償額予定契約の禁止違反、前借金相殺の禁止違反、強制貯蓄の禁止違反、解雇制限禁止違反、法定労働時間違反、法定休日付与違反、時間外・休日及び深夜の割増賃金支払い義務違反、年次有給休暇付与義務違反、18歳未満の者の深夜業禁止・危険有害業務就業制限違反、妊産婦の危険有害業務就業制限違反、産前産後休業付与義務違反、妊産婦の法定時間外労働禁止違反、労働災害補償違反
(4)30万円以下の罰金
労働条件の明示義務違反、賃金の通貨支払い義務違反、休業手当支払い義務違反、変形労働時間制の協定届出義務違反、事業場外労働のみなし労働時間労使協定届出義務違反、未成年者に代わる親権者・後見人との労働契約禁止違反、女性労働者の生理休暇取得拒否、就業規則作成・届出義務違反、制裁規定の制限違反、寄宿舎規則作成・届出義務違反、就業規則周知義務違反、労働者名簿作成義務違反、賃金台帳作成義務違反、労働関係書類の法定期間保存義務違反、労働基準監督官等の調査妨害
労働基準法違反となるケース10選
労働基準法違反の大半は、違反行為を受けた労働者本人の労働基準法監督機関への通報や相談により発覚します。
労働基準監督署が労働者基準法違反の通報や告発を受けると、違反行為があったとされる事業所へ労働基準監督官が立入調査(臨検)を行います。その結果、違反行為があったと認定すると是正勧告を行います。それでも違反行為が続く場合、あるいは違反行為が悪質と判断した場合は送検すると共に、厚生労働省がその企業・事業所名・所在地を公表します。
厚生労働省の「平成28年4月から平成29年3月までに実施した監督指導結果」によると、全国の労働基準監督官が立入調査した事業所は2万3915事業所。そのうち労働基準法違反行為があったと認定した事業所は1万5790事業所、立入調査を受けた事業所の66.0%に上っています。労働基準法に対する企業全般の問題意識の低さが背景と見られています。
実際、厚生労働省の『労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成30年9月1日―令和元年8月31日公表分)』を見ると、労働基準関係法令違反容疑で送検された事案には次のようなケースが見られます。
| 1.北海道A社 | 労働基準法第15条違反 | 労働契約の締結に際し、書面を交付する方法により労働条件を明示しなかった。 |
| 2.北海道B社 | 労働基準法第62条違反 | 満18歳に満たない者に、禁止されている足場の組立て作業を行わせた。 |
| 3.宮城県仙台市C社 | 労働基準法第32条違反 | 労働者28名に、36協定を締結せず違法な時間外労働を行わせた。 |
| 4.山形県鶴岡市D社 | 労働基準法第32条違反 | 外国人技能実習生6名に、違法な時間外労働を行わせた。 |
| 5.茨城県古河市E社 | 労働基準法第32条違反 | 労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた。 |
| 6.栃木県日光市F社 | 労働基準法第40条違反 | 労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく違法な時間外労働を行わせた。 |
| 7.群馬県吾妻郡G社 | 労働基準法第32条違反 | 労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた。 |
| 8.埼玉県北足立郡H社 | 労働基準法第32条違反 | 労働者5名に、違法な時間外労働を行わせた。 |
| 9.東京都千代田区I社 | 労働基準法第32条違反 | 労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた。 |
| 10.神奈川県川崎市J社 | 労働基準法第24条違反 | 労働者2名に、1ヵ月分の定期賃金合計80万円を支払わなかった。 |
労働基準法違反が発覚した場合の対応
労働基準法違反の摘発は、労働基準監督官の立入調査➡違反事実の認定➡是正勧告書交付➡是正報告書提出の手続きで行われます。企業にとって、ここまでは行政指導なので、それほどのダメージはありません。しかし、立入調査拒否、是正報告書提出拒否などの「確信犯的」対応をすると「悪質」とみなされ、送検されてしまいます。その企業はブラック企業の烙印を押されたのも同然といえるでしょう。
労働基準法違反事案で多いのが36協定違反、労働条件の明示義務違反、賃金・残業代未払い、法定労働時間違反(長時間労働)、労働災害補償違反(労災隠し)などです。
職場で違反行為に遭った社員の通報などで労働基準監督官が事業所の立入調査を行う際は、当該事業所が労働基準法関連書類を所定のルールに基づき作成・保管しているかを確かめるため、事前に次の書類準備を要求するのが通例とされています。
・就業規則、賃金規程、労働者名簿、労働条件通知書、その他労働関係規定
・36協定届、変形労働時間制労使協定、変形労働時間シフト票
・出勤簿、賃金台帳、有給休暇管理簿
・健康診断個人票、安全・衛生管理体制組織図、安全・衛生管理者・産業医選任報告書、安全・衛生委員会議事録
・その他書類…事業所総従業員数、男女別従業員数、18歳未満従業員数、パートタイマー・アルバイト・派遣社員等有期雇用従業員数、外国人従業員数と在留資格など
そして労働基準監督官が事業所の立入調査において、基本的なこととして入念に調べるのが次の事項とされています。
| (1) 就業規則関連 | 就業規則に労働基準法に定めた所定の記載事項とどのような任意事項が記載されているかの確認 |
| (2) 労働条件通知義務関連 | 労働条件が労働基準法に準拠しているか、労働条件通知義務を果たしているかなどの確認 |
| (3) 最低賃金関連 | 最低賃金法が規定している最低賃金を下回っていないかの確認 |
| (4) 残業代関連 | 出勤簿と賃金台帳の照合による、残業代が適正に支払われているかの確認 |
| (5) 長時間労働関連 | 36協定の延長時間を超える違法な時間外労働をさせていないかの確認 |
| (6) 健康診断関連 | 労働基準法が義務付けている1年に1回の健康診断を実施しているかの確認 |
| (7) 安全・衛生管理体制関連(従業員50名以上の事業所) | 安全・衛生管理者・産業医の確認、長時間労働者に対する医師の面談指導制度有無の確認、ストレスチェック実施の確認、安全衛生管理体制の整備状況確認など |
立入調査の結果、労働基準法違反と認定すると、労働基準監督官は「是正勧告書」を公布し、労働条件改善を勧告します。また、違反と適法の線引きが微妙と判断した際は「指導票」を公布し、労働条件改善を指導します。
労働基準監督署から労働基準監督官立入調査の通告があった際、総務担当者が真っ先に行うべき対応は、立入調査前の自発的改善です。一般には次の点検と改善が重要とされています。
・就業規則の点検と不備があった場合の改善
・36協定の点検と不備があった場合の改善
・雇用契約書の点検と不備があった場合の改善
・残業代未払いの点検と未払いがあった場合の即刻支払い、残業代未払い防止体制の即時整備
・長時間労働の点検とそれがあった場合の防止措置
こうした事前対応をすれば、自社における労働基準法違反は偶発的なものであり、再発防止に努めているとの自社の労働基準法遵守姿勢を労働基準監督官にアピールできます。行政処分は緩やかなレベルで済まされる可能性もあります。
まとめ
労働基準法遵守の基本は、管理者や現場リーダーに対する労働基準法禁止行為の周知徹底といわれます。そのためには、管理者研修などで「具体的にどんな行為をしてはいけないのか」を分かりやすく説明する必要があるでしょう。
また、仮に労働基準監督官の立入調査を受けた場合、総務担当者はそれをネガティブに捉えるのではなく、逆に自社の労務管理改善の好機とポジティブに捉え、立入調査に積極的に協力すると共に、労働基準監督官から労務管理改善のアドバイスも積極的に得るように努めるのが、「賢い対応」といえるでしょう。結果的に自分では気づかなかった不備の発見や、より働きやすい職場環境実現のきっかけになる可能性があるからです。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
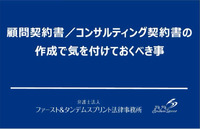
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -
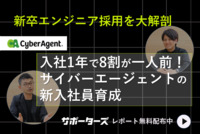
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -
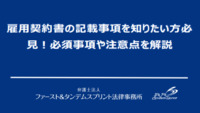
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -

食の福利厚生【OFFICE DE YASAI 】
おすすめ資料 -

中堅大企業のための人事給与BPO導入チェックポイント
おすすめ資料 -
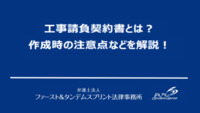
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -
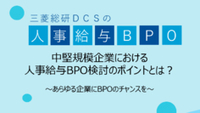
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース