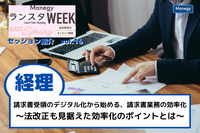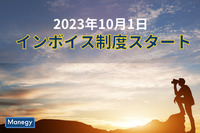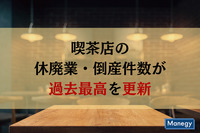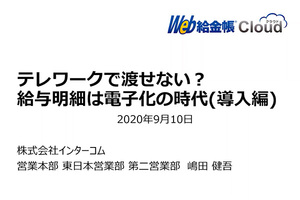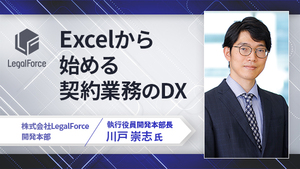公開日 /-create_datetime-/
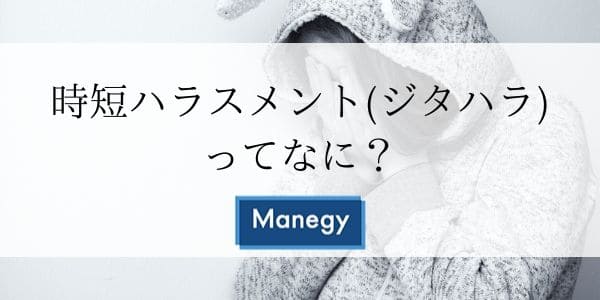
働き方改革が世の中で話題になるにつれ、職場の常識だったさまざまなルールを「おかしいのでは?」とピックアップされることが増えてきました。
その一つが「時短ハラスメント」で、業務時間の短縮を強要するハラスメントを指します。業務量は以前と変わらないのに残業の禁止をされ、残業代は払われないが、結局残った仕事は家に持ち帰って処理しなければならない状況などがあてはまります。
この記事では、最近話題となっている時短ハラスメントの問題点や実例、今後の対策などについてまとめてご紹介します。
目次【本記事の内容】
時短ハラスメントとは労働時間に関する悪習
時短ハラスメントは、セクハラ(性的な違いや話題を持ち出して相手に不快感を与えるハラスメント)やエイハラ(年齢を理由に差別や嫌がらせをするハラスメント)などと並んで、最近話題になる機会が増えているハラスメントのことです。ジタハラとも呼ばれており、まだ一般的ではないかもしれませんが、実は昔から日本の会社ではよく行われていたものです。
時短ハラスメントとは、残業をせざる負えない状況なのに会社側が残業を認めないことにより、残業代未払いにもかかわらず、家に仕事を持ち帰ったりして実際は残業をしなければならない状況などがあてはまります。長時間労働やサービス残業とも関わる問題のため、労働環境の悪化が叫ばれる現代において徐々に表面化してきました。
ブラック企業が社会問題化しているように、働かせ方に問題がある企業は後を絶ちません。企業にとって人件費の増大は経営を圧迫する大きな課題のため、たとえ法律に違反してでも、会社の利益を追求するため社員に無理をさせようとするケースは決して少なくないのです。
時短ハラスメントに当てはまるケース
時短ハラスメントには次のようなものがあります。
・膨大な業務量を一人に押しつけて、就業時間内に終わらせろと強要する
・どんなに仕事が溜まっていても残業を禁止する
・一人では処理しきれない業務があっても、上司から効率よく進めるための指示がない
・担当の仕事はどんなに間に合わないと思われても、他の社員に割り振られず自分で処理するように求められる
・明日に差し支えるほどの残務があっても、定刻通りに退社させられる
このように、残業しなければ業務が終わらないのにもかかわらず、定時を理由にして頑なに帰宅を強要されたり、とても1日では終わらない業務量をこなせないことを個人の能力や意欲の問題にしたりして、残業を禁止する行為が時短ハラスメントなのです。
時短ハラスメントはなぜ急増しているのか
時短ハラスメントは、「労働時間の短縮」という素晴らしい取り組みと表裏一体なのが厄介な点です。企業としては、従業員のために定刻で変えるように促していると主張するかもしれません。しかし、実際には終わらない仕事を社員は家に持ち帰って、残業手当をもらうことなくプライベートの時間に業務をこなさなければならなくなるケースもあります。帰宅後に仕事をするのを前提として業務の割り振りが行われているだけに、社員にとっては就業時間など意味がなくなり、四六時中仕事をし続けなければならないというわけです。
国を挙げて長時間労働を改善しようと取り組んだ結果、業務量は変わらない、もしくは増え続けているのに、人手不足は解消されない。そのため、一人ひとりののしかかる業務量がどんどん増えていってしまった。しかし、企業はそれにともなう残業代はできるだけ出したくない。
こうした理想と現実の間で負のスパイラルに陥ってしまったため、時短ハラスメントが現状にように深刻になってしまったと考えられます。
時短ハラスメントのエピソード例
ここからは、具体的なビジネスシーンで起きているエピソードをいくつかご紹介します。
●不可能な納期やノルマを押しつけられる
「退職者が相次いで、以前は2人で担当して分担しながらやっていた業務を私一人でこなすことになりました。しかも、取引先の都合でこれまでの1週間の納期から2日も早くなったため、私の全体の仕事に影響が出てきています。上司には「早く人手を増やして欲しい」「もうひとり担当をつけてほしい」と交渉しているものの、取り合ってくれません。これまでの倍以上の仕事を短期間で仕上げないといけなくなってプレッシャーもかなりのものです。さらに、1時間以上の残業禁止という暗黙のルールが職場にありますので、残った仕事は毎日家に持ち帰って納期に間に合わせています」
(30代男性)
「会社として取引量が増えているのに加えて、突発的な対応が多い部署で働いています。最近増えているのが、午後から夕方にかけて上司が新たな仕事を持ってきて『これ、明日の午前中までだから』と一言だけで仕事を指示してくること。日常の業務も行いながら、急ぎの仕事も入れ込むのはかなり厳しいので、残業する羽目になります。
ただ、ノー残業デーは定刻になると上司が強制的に部下を帰らせるため、その日はもう帰宅してからほぼ徹夜でやるしかありません。サービス残業なので手当ても出ませんし、心身共にすり減りそうです」
(40代男性)
●業務の指示がなく、ただ割り振りだけされる
「上司にマネジメント能力が皆無といいますか、『このくらいの仕事の納期なら、誰にどのくらいの日数で任せればOK』といった計算ができないんです。そのため、ベテランに仕事を与えるときも、まだ経験の浅い平社員に仕事を割り振るときも、丸投げするように仕事を押しつけるだけ。当然、あまり経験のない社員ほど段取りもわからなくて効率も悪いので、残業になってしまいます。それでも、そういう上司ほど、『お前の要領が悪すぎるだけだから残業は認めない』などと理不尽に叱っているんです」
(40代男性)
時短ハラスメントの実際のシーンを垣間見ると、実際の業務量と会社が認める労働時間がまったく釣り合っていないことが根深い問題だということがお分かりでしょう。
ジタハラ横行の企業に勤める社員はどうすればいいか
時短ハラスメントが日常的になっている職場ですと、上司にかけあったり、ハラスメントの相談窓口で申し出たりしても、うまく解決には結びつかない可能性が大きいはずです。
また、労働組合のない中小企業の場合は、さらに相談する先がなくて一人で抱え込むことも珍しくありません。
そうしたときは、外部の力を借りてみるのがおすすめです。会社の所在地を管轄している労働基準監督署は労働相談のきっかけになります。また、行政をはじめ労働関係の財団法人が労働相談を受け付けていますので、電話や訪問で相談してみましょう。
また、いきなり労働関係の機関に相談しづらいになら、産業カウンセラーや社会保険労務士といった専門職に相談して、アドバイスをもらう方法もあります。
いずれにしても、雇用主と従業員との立場では、時短ハラスメントを一人で解決するのは並大抵のエネルギーでは行えません。プロの専門家から意見や力を借りる方が無難です。
まとめ
時短ハラスメントの問題は、その行為自体が社風になっていることが多く、また上司も当たり前と思っていることが珍しくありません。しかも、そんな上司すらさらに経営陣から「残業させるな」と厳しく釘を刺されていることも。
ブラック企業に典型的な時短ハラスメント。もし自分なりに普段から効率よく仕事を進めるための工夫や職場との連携を図っているつもりでも、仕事が終わらない、サービス残業が続いているといった人は、時短ハラスメントに陥っているのかもしれません。一度、自分の職場を客観的に見つめ直してみて、勤務先の社風が時短ハラスメントを当たり前にしていないか、振り返ってみてはいかがでしょうか。
関連記事:改めて気を付けて!アルハラ
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
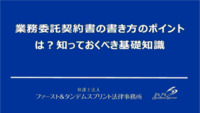
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -
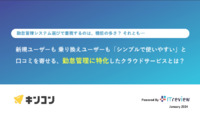
新規ユーザーも 乗り換えユーザーも「シンプルで使いやすい」と 口コミを寄せる、勤怠管理に特化したクラウドサービスとは?
おすすめ資料 -
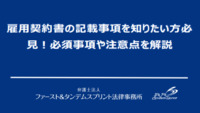
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

若手社員の早期離職を防止するためにできること
おすすめ資料 -
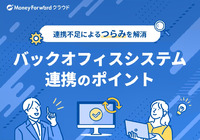
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -
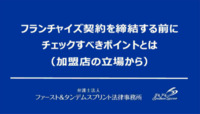
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -

請求書受領サービスの 失敗しない選び方
おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース