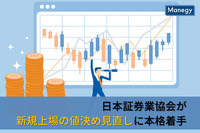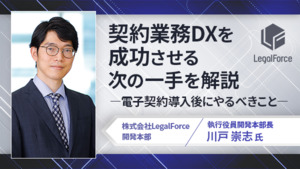公開日 /-create_datetime-/
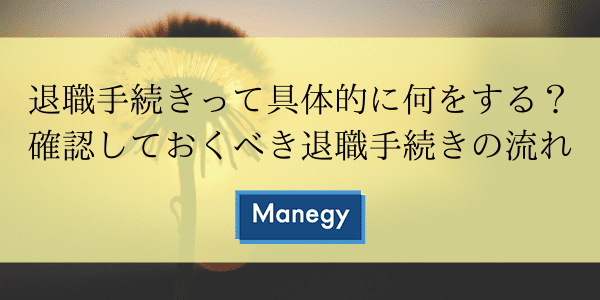
退職する社員が出た時、総務担当者はその社員の退職手続きをしなければなりません。直接的には退職者のために行う手続きですが、社会保険や税金の処理、法定書類保管なども絡んでくるので、会社としても不可欠な手続きになります。退職手続きは多岐にわたるので、いざという時のために総務担当者はその基本的流れとポイントを知っておくと良いでしょう。
退職手続きの流れ
退職手続きは通常、次の流れで行われます。
1.社員が上司へ退職の申し出
退職の申し出は、民法上は退職日の2週間前とされています(民法第627条「雇用は解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する」)。しかし、実際には業務の引継ぎや人員補充の期間などが必要なので、社会通念上は1カ月から2カ月前にこの申し出を受けるのが普通です。
2.退職日の決定
退職希望社員は上司との話し合いで、適切な退職日を決定します。
3.退職願の受理
退職願いは上司を経由し、総務部(課)が受け付けた段階で正式受理になるのが通例です。
4.退職手続き事項の確認と退職手続き書類の作成
総務担当者は退職社員に関する退職手続き事項の確認と退職手続き書類の作成を行います。
5.業務の引継ぎ
総務担当者は退職社員が担当している業務内容・フロー等を記載した「業務引継ぎ書」、作業リスト、業務関係先リストなどの早期作成・提出を退職社員に依頼します。業務引継ぎの効率化と引継ぎ期間短縮に繋がります。
6.退職
社員の退職と同時に退職前の手続きが一応終了します。
7.退職後の処理
労働関連行政機関への各種届出、その他
退職手続きのスケジュール
様々な退職手続きのうち、社会保険、労災保険、税金などに関連する法定手続きにおいては、次のような期限が定められているので、総務担当者はそのスケジュールに注意が必要です。
●「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」
退職日から5日以内に管轄の年金事務所へ提出
添付書類:退職者本人および扶養者の健康保険被保険者証
なお、退職者本人の滅失・毀損等で健康保険被保険者証を回収できない場合は、退職日から5日以内に「健康保険被保険者証回収不能・紛失届」を提出する必要があります。
●健康保険被保険者証回収不能・紛失届
退職日から5日以内に管轄の年金事務所へ提出
●健康保険任意継続被保険者資格取得届
退職日の翌日から20日以内に管轄の健康保険組合または年金事務所へ提出
「健康保険任意継続」は社員が退職後も前職の社会保険を継続利用できる制度です。社員が退職後、国民健康保険に加入する場合、この届は不要になります。したがって総務担当者は社員に「任意継続か国民健康保険加入か」の意思確認を退職前にしておく必要があります。
●「雇用保険被保険者資格喪失届」
退職日の翌々日から10日以内に管轄の年金事務所へ提出
なお、離職票を発行する場合は、次の書類を添付した「離職証明書」の提出が必要です。
1.労働者名簿
2.賃金台帳
3.出勤簿(タイムカードなど出退勤が確認できるもの)
4.退職届(退職願など本人の退職事由を確認できるもの)
●給与支払報告に係る給与所得異動届
退職日を含む月の翌月10日以内に退職社員居住の市区町村または退職社員の再就職先へ提出
これは住民税徴収の変更手続きです。退職日により変更手続きが次のように変わるので、総務担当者は注意が必要です。
◎1月1日から5月31日の間に退職した場合…最終支払給与か退職金から前年分の住民税額を一括特別徴収。
◎6月1日から12月31日の間に退職した場合…退職社員に特別徴収か普通徴収かの意思を事前確認しておきます。その上で特別徴収希望の場合は、最終支払給与か退職金から一括徴収した住民税額を徴収月翌月10日に市区町村へ納付します。また、再就職先で特別徴収を継続したい場合は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を退職社員が再就職先へ提出します。一方、普通徴収希望の場合は「給与支払報告に係る給与所得異動届」の中で特別徴収から普通徴収への切替え手続きをします。
●「労働保険年度更新申告書」
毎年6月1日から7月10日の間に管轄の都道府県労働局または労働基準監督署へ提出
例えば8月1日に退職者が発生した場合、その直後に行わなければならない手続きではありませんが、翌年の6月1日から7月10日の間にこの手続きを行わないと、在籍していない社員の労働保険料を支払わなければならなくなります。
●「給与支払報告に係る給与所得異動届」
退職日を含む月の翌月10日までに退職者が居住している市区町村または再就職先へ提出
●法定手続き以外に忘れてはならない社内手続き
社内情報システムのアクセス権停止…情報セキュリティを確保するため、退職前日など退職希望者の業務が実質的に終了した段階で、直ちにアクセス権停止やアカウント削除の措置を取る必要があります。
退職後に行うこと
退職者の雇用関連書類は、労働基準法を始めとする労働関連法規により次のような法定保存期間が定められています。これらの書類を適切に保管するのも、総務担当者の重要な役割の1つです。
<人事関係書類>
●労働者名簿……………………………退職日から3年
●雇用契約書……………………………退職日から3年
●労働条件通知書………………………退職日から3年
●誓約書…………………………………退職日から3年
●身元保証書……………………………退職日から3年
●履歴書・職務経歴書…………………退職日から3年
●卒業証明書……………………………退職日から3年
●免許・資格関連証明書………………退職日から3年
●タイムカード・残業命令書…………退職日から3年
●賃金台帳………………………………最終記録日から3年
●源泉徴収簿……………………………最終記録日から7年
●給与所得者の扶養控除等申告書……最終作成日から7年
●退職届…………………………………退職日から3年
<社会保険関係書類>
●雇用保険被保険者関連書類…………退職日から4年
●離職証明書事業者控…………………退職日から4年
●健康保険・厚生年金保険関連書類…退職日から2年
●定期健康診断個人票…………………作成日から5年
<その他書類>
●労働災害補償関連書類………………労働災害補償終了日から3年
●労災保険関連書類……………………労災保険請求・徴収等完結日から3年
●障害者手帳・診断書等………………退職日から3年
●企画業務型裁量労働制関連書類……退職日から3年
●労働者派遣の派遣先管理台帳………契約完了日から3年
退職時に返すもの、受け取るもの
社員の退職に伴い、会社には退職者から返却してもらうもの、退職者に返却・交付しなければならないものが様々発生します。このうち、総務担当者がチェックしなければならないのは次の事項です。
<退職社員から返却してもらうチェック事項>
●健康保険被保険者証(扶養者がいる場合はその分も)
退職者が健康保険被保険者証を滅失・毀損している場合は、「健康保険被保険者証回収不能・紛失届」を提出するため、最終出勤日までに退職社員から「健康保険被保険者滅失・毀損報告書」を提出してもらう必要があります。
●社員証・社章
自社社員の証明となる社員証や社章は退職前日までに返却してもらう必要があります。
●退職社員本人と取引先等の名刺
退職社員の名刺と、退職社員が業務を通じて収集した取引先等の名刺は社会通念上、会社の資産とされています。したがって退職社員と取引先等の名刺は退職前日までに返却してもらう必要があります。
●制服・作業着
会社貸与の制服・作業着も同様なので、退職前日までに返却してもらう必要があります。
●会社貸与のパソコン、タブレット、スマートフォンなどの情報端末
これらも退職前日までに返却してもらう必要があります。
●業務資料と取引先の資料
業務上のデータ、各種企画書・提案書・プレゼン資料などは会社資産であり、かつ会社のノウハウが詰まった知的財産です。また、退職社員が業務を通じて収集した取引先等の資料は、会社に善管注意義務があります。したがってこれらの資料も退職前日までに返却してもらう必要があります。
<退職社員に返却・交付しなければならないチェック事項>
●年金手帳
厚生年金保険の加入証明や国民年金の加入に必要な書類なので、会社が保管している場合は退職日までに返却する必要があります。
●雇用保険被保険者証
退職後の失業給付を受ける際や再就職先の雇用保険に加入する際になど必要な書類なので、退職日までに交付する必要があります。
●源泉徴収票
年末調整に必要な書類なので交付する必要があります。ただし源泉徴収票の発行は退職日以降(最終給与の明細発行後)になるので、これは後日郵送することになります。
●離職票
退職日(資格喪失日)以降に発行する書類なので、これも後日郵送することになります。ただし、退職社員の再就職先が決まっている場合や退職社員が離職票発行を望んでいない場合、交付は不要です。
●健康保険被保険者資格喪失確認通知書
退職社員が退職後、国民健康保険へ加入する際に必要な書類なので、退職日(資格喪失日)から5日以内に郵送する必要があります。
●退職証明書、在籍期間証明書
退職社員の円満退職を証明する書類なので、退職社員が発行を望む場合は交付する必要があります。交付日はケースバイケースになります。
まとめ
退職の手続きは入社手続きとの共通部分が多いので、人事担当者は退職手続きを遺漏なく処理するため、その相違点をしっかりと把握しておく必要があります。退職後は退職社員と連絡が取りにくくなるのが一般的なので、手続き処理を1つ誤るだけでその修正に多大な時間を取られる可能性があるからです。
また、退職の理由は人により様々です。しかし、在職中は同じ会社で苦楽を共にした仲間の1人だった事実に変わりはありません。したがって、退職社員の意向に寄り添い、退職日まで親身になってサポートするのが総務担当者の真骨頂といえます。退職後も退職社員から感謝される存在でありたいものです。このことは、間接的に自社の社会的信頼性や好感度の向上に繋がるでしょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため専門家や関連省庁にご確認ください
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
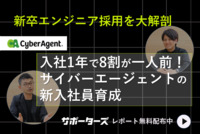
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -

空間共有システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -
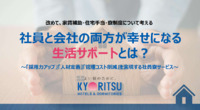
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

働く人の意識を変える定点観測
おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

1月9日公開記事
ニュース -
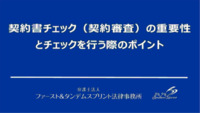
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -
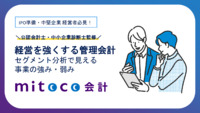
経営を強くする管理会計 セグメント分析で見える事業の強み・弱み
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -
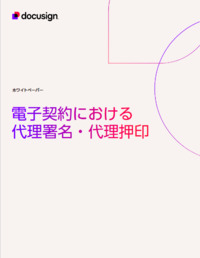
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -

「人事部の実態と業務効率化」に関するサーベイ結果調査レポート【MURC&DCS共同制作】
おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース