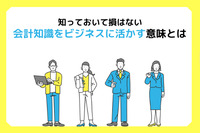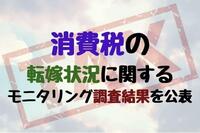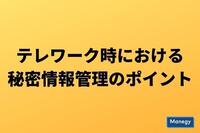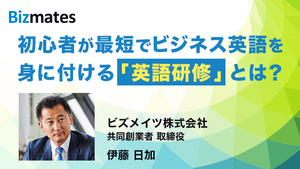公開日 /-create_datetime-/
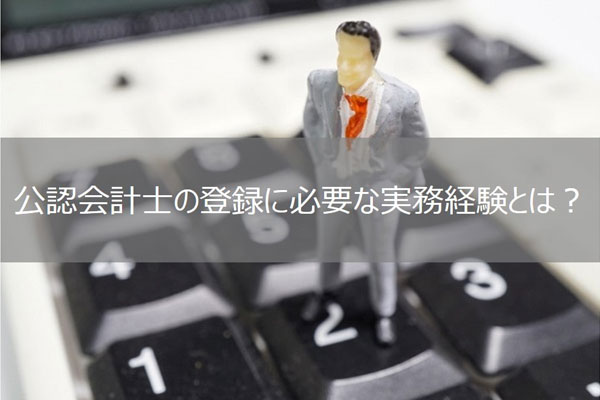
公認会計士試験に合格しても、それだけではまだ公認会計士になることはできません。
2年間の実務経験、および3年間の補習所通学をし、修了考査に合格して、晴れて公認会計士としての登録が可能になります。
この記事では、公認会計士の登録に必要な実務経験とはどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
公認会計士試験合格後 登録までの要件
公認会計士試験に合格し、公認会計士として登録するための要件は、
1. 実務経験の期間が2年以上であること
2. 補習所に通学し、必要な単位を取得すること
3. 修了考査に合格すること
の3つです。
1. 実務経験の期間が2年以上であること
公認会計士として登録するには、実務経験の期間が2年以上であることが必要です。
実務経験は、下で詳しく見る通り、「業務補助」と「実務従事」の2種類があります。
2. 補習所に通学し、必要な単位を取得すること
公認会計士に登録するためには、実務補習に通学し、必要な単位を取得しなければなりません。
実務補習は、東京・東海・近畿および九州の4つの実務補習所で、平日の夜や土日などに、原則として3年間にわたって行われます。
3. 修了考査に合格すること
実務補習を修了するためには、修了考査に合格することが必要です。
修了考査の合格率は、約70%となっています。
公認会計士の登録に必要な実務経験とは?
公認会計士の登録に必要な実務経験について、詳しく見ていきましょう。
実務経験の種類
公認会計士の登録に必要な実務経験の種類は、「業務補助」と「実務従事」の2種類です。
業務補助とは、監査証明業務について、公認会計士または監査法人を補助することです。
1年につき2つ以上の法人の監査業務を行う必要があるとされます。
実務従事とは、財務に関する監査・分析その他の実務に従事することです。
実務従事の業務は、以下のように定められています。
・国または地方公共団体の機関における、国・地方公共団体の機関などの会計に関する検査
・監査、または国税に関する調査・検査の事務
・金融機関や保険会社などにおける貸付や債務保証などの資金の運用に関する事務
・国や地方公共団体、またはその他の法人における原価計算など財務分析に関する事務
実務経験の期間と時期
実務経験の期間は、2年以上とされています。
この2年の実務経験は、週に何日以上行えば良いのでしょうか?
業務補助の場合には、監査法人などの代表者が認めるならそれで良いとされています。
1週間あたりの日数などは特に定められていません。
実務従事の場合には、「常勤で2年」が基準となり、非常勤などで勤務日数が少ない場合は、常勤の勤務日数と比較して期間が考慮されます。
勤務日数が常勤の半分なら、実務経験の期間も半分とみなされることになります。
実務経験の時期は、公認会計士試験合格の前でも後でもかまいません。
しかし、多くの人は、公認会計士試験に合格後、実務経験を行っています。
記事提供元
管理部門の転職ならMS-Japan
転職するなら管理部門・士業特化型エージェントNo.1のMS-Japan。経理・財務、人事・総務、法務、会計事務所・監査法人、税理士、公認会計士、弁護士の大手?IPO準備企業の優良な転職・求人情報を多数掲載。転職のノウハウやMS-Japan限定の非公開求人も。東京・横浜・名古屋・大阪で転職相談会を実施中。

管理部門の転職ならMS-Japan
転職するなら管理部門・士業特化型エージェントNo.1のMS-Japan。経理・財務、人事・総務、法務、会計事務所・監査法人、税理士、公認会計士、弁護士の大手?IPO準備企業の優良な転職・求人情報を多数掲載。転職のノウハウやMS-Japan限定の非公開求人も。東京・横浜・名古屋・大阪で転職相談会を実施中。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
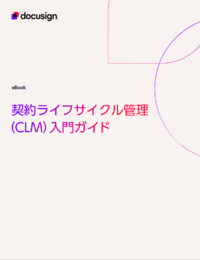
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -
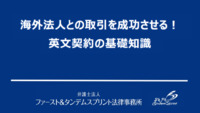
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -
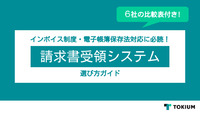
失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】
おすすめ資料 -

<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

厄介な上司を賢く扱う!?明日からできる「マネージングアップ」とは【キャスター田辺ソランのManegy TV #14】
ニュース -

企業が支給する「インフレ手当」の中身とは?
ニュース -
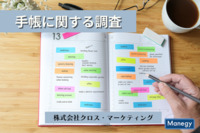
クロス・マーケティングが「手帳に関する調査」結果を発表
ニュース -

USCPAで監査法人に転職できるのか?その後のキャリアは!?
ニュース -
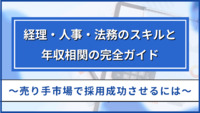
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -
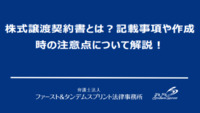
株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

食の福利厚生【OFFICE DE YASAI 】
おすすめ資料 -
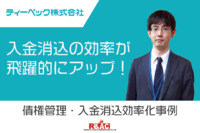
債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -

iDeCo加入年齢を69歳まで拡大する狙いと背景は?
ニュース -

生前贈与の税制簡素化に向けた検討が開始。贈与税の何がどう変わるのかを詳しく解説
ニュース -

経理の転職をエージェントに頼むメリット・デメリット
ニュース -

男女3,013人が1位に選んだストレスの解消方法は? 株式会社ビズヒッツ調べ
ニュース -

「ことら送金サービス」とは?新サービスの概要や活用場面を解説
ニュース