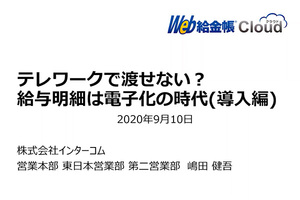公開日 /-create_datetime-/
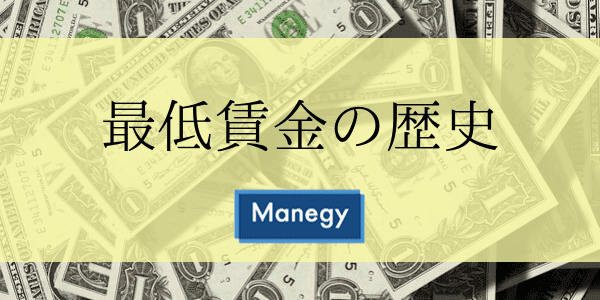
今年7月、中央最低賃金審議会は2019年度における地域別最低賃金の改定について、全国平均の時給を昨年度よりも27円引き上げて901円とする目安をまとめました。27円という引き上げ幅は、2002年度に時給形式で最低賃金を示す現行方式となって以降最大です。全国平均の時給が900円台になるのも初めてのことです。
昨年度から大幅に上昇した最低賃金額ですが、日本ではこれまでどのような変遷をたどってきたのでしょうか。今回は最低賃金の歴史について解説します。
最低賃金とは?
最低賃金とは、国が最低賃金法に基づいて定めた賃金の最低限度のことです。使用者(企業)は定められている最低賃金以上の額を労働者に支払わなければなりません。
厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が、年度ごとに上げ幅の目安を決定し、この目安に基づいて、都道府県の審議会が最低賃金を設定します。
もし使用者側が、最低賃金制度で規定された賃金よりも低い額しか労働者に支払わなかった場合、たとえそれが使用者と労働者の合意であったとしても法律に基づき無効とされるのが原則です。そのため、最低賃金よりも低い給与しか払っていないことが発覚した時点で、使用者はその差額分を直ちに支払う必要があります。
日本で発表される最低賃金には、審議会形式で決められる地域別最低賃金と産業ごとに定められている産業別最低賃金、そして労働協約の拡張方式によって定められる最低賃金等があります。このうち地域別最低賃金については、雇用形態に関係なく適用されるのでアルバイトやパートも対象です。
世界で最も古い最低賃金制
世界で最低賃金制を最も早く導入したのはニュージーランドで、1894年のことでした。当時、ニュージーランドには移民労働者が大量に流入し、それにより失業者が増大。労働者の生活水準は大きく低下し、労使関係は不安定な状況が続いていました。このような状況を改善するために導入されたのが最低賃金制(強制仲裁法)だったわけです。
アメリカやイギリス、カナダ等では、1910年代に入ってから最低賃金制が導入されていきました。アメリカでは1912年にマサチューセッツ州で初めて最低賃金制が導入され、1923年までに全国13の州で導入されています。
1928年には国際労働機関(ILO)が「最低賃金決定制度の創設に関する条約」を採択。現在に至るまで約100カ国が批准しています。
日本における最低賃金制の始まり
日本における最低賃金制度は、1947年の労働基準法に端を発します。
ただ、当時の労働基準法による最低賃金制度は、労働大臣もしくは都道府県の労働基準局が「必要に応じて」賃金審議会の答申や建議によって最低賃金を決めるというあいまいなものでした。そのため実際には、戦後の混乱期が重なったこともあり、制度としてほとんど機能していなかったと言われています。
その後、労働基準法に基づく最低賃金制への批判が強まり、1959年に改めて最低賃金法が制定されました。最低賃金だけを規定する法律が初めて施行されたわけです。
ところが、当初の法案では全国一律の最低賃金制を目指す内容でしたが、使用者(企業)側の強い反発があったことから、「業者間協定」による最低賃金を容認するという妥協案が採用されました。業者間協定とは、業界団体が自主的に最低賃金額を協定によって取り決め、それを国の最低賃金審議会が法的効力を持たせるという方法です。この方法だと、最低賃金の決定において業界とそこに所属する企業の都合が優先される恐れがあるため、労働者の視点に立った本来の最低賃金制とは必ずしも言えません。
最低賃金制における目安制度の導入
業者間協定方式に対する国民の反発が強まっていく中、1968年に最低賃金法が改正され、中立の立場にある審議会が妥当な最低賃金を提示する「審議会方式」が新たに導入されました。この制度を軸に産業別と地域別の最低賃金が設定され、さらに1976年には47都道府県に地域別最低賃金を設定し、全国をA、B、C、Dの4つのランクに分ける目安制度が導入されます。目安制度とは、中央最低賃金審議会が経済指標等を考慮して目安となる最低賃金額を決定し、それを都道府県の地方最低賃金審議会に提示することで、全国的な金額の均質化を図ろうとする制度です。約43年前に定められた目安制度は、現在も変更なく続けられています。
2000年以降の最低賃金の推移
厚生労働省の『平成29年版厚生労働白書』によると、2000年当時の最低賃金額(全国平均)は659円。その後、2000年代半ばまでほぼ横ばいの状況が続いていましたが、2000年代後半から年度当たりの引き上げ額が上昇し、時給換算の最低賃金額も緩やかに上昇していきました。2008年に700円を超え、2016年には800円を突破。そして冒頭で触れた通り、2019年の中央最低賃金審査会が示した目安は901円で、史上初めて900円を超えました。
まとめ
最低賃金制は、世界史的にみると19世紀末には導入を始めている国もありましたが、日本で導入されたのは戦後になってからです。しかし戦後間もないころは制度がしっかりと確立されておらず、現在も行われている目安制度は1976年になってようやく導入されました。1960年代には高度成長の波が来ていた日本ですが、労働者の権利に関わる最低賃金に関しては、安定した制度的基盤の成立は遅かったと言えます。
最低賃金額の変遷をみると、ここ10年程は右肩上がりで上昇。2019年度の中央最低賃金審査会における目安では、東京都と神奈川県の最低賃金が時給換算で1,000円を超えています。
今後もこうした水準が続いていくのか、経営者や人事担当者は動向をチェックしておきましょう。
関連記事:専門家テンプレート紹介:労働条件通知書
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -
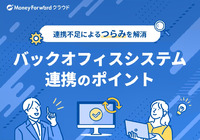
連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -
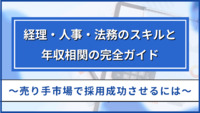
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

電子署名の適法性 ~日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性~
おすすめ資料 -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト
ニュース -
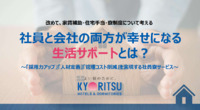
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -
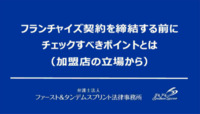
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -
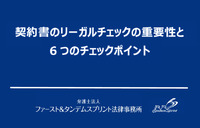
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

経理は転職サイトを利用すべき?経理人材の転職市場での価値を解説!
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ニュース -

ブログカードテスト
ニュース