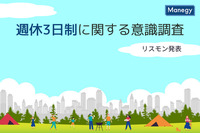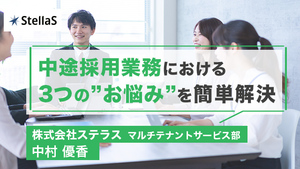公開日 /-create_datetime-/
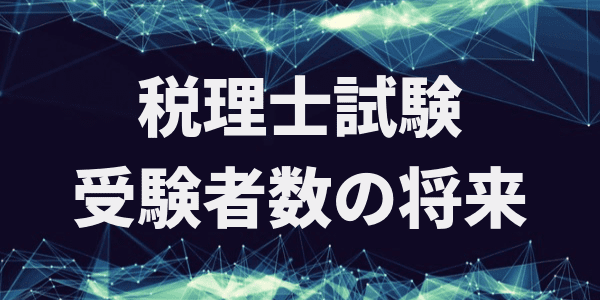
平成30年度の税理士試験は、合格者数が過去最低で、初めて5,000人を割る4,716人となったことで話題となりました。また、令和元年度の受験申込者数も36,701人と、前年度比4.7%減となったことが分かっています。
税理士試験の受験者数は今後も減り続けてしまうのか、また受験者数の減少が業界にどのような影響を及ぼすのか、税理士試験における将来について考察します。
税理士試験の申込者数は過去10年間減少の一途
税理士試験は、通常年1回、8月第1週火~木曜日の3日間行われ、例年7月下旬頃にその年の受験申込者数が、また12月に実際の受験者数が国税庁から発表されます。令和元年度の受験申込者数は前年度比4.7%減の36,701人と発表されたことで、実際の受験者数も昨年より減少することが予想されています。
税理士試験の受験申込者数は、平成22年度から令和元年度までの過去10年間にわたり、毎年数千人単位で連続して減少を続けています。前年に対し最も減少数が多かったのは平成26年度で、7,000人を超える減少数を記録しています。
受験申込者数の減少に比例し、合格者数も年々減少しています。平成29年度の合格者数が5年ぶりに増加したものの、平成30年度で再び減少し、その数も史上初めて5,000人を割り込み過去最低を記録しています。
数字の上では最終的に受験者がいなくなる?
税理士試験の受験申込者数が過去10年間でピークだった平成22年度の受験申込者数は75,785人、令和元年度の受験申込者数は36,701人と発表されており、10年間での減少数は39,084人です。この10年間で、1年ごとの受験申込者数は、平均して39,084÷10=約3,908人ずつ減少していることになります。
このまま毎年約3,908人ずつ受験申込者数が減少し続けたと仮定した場合、10年後には申込者がいなくなることになります。あくまでも単純計算であるため、実際にゼロになることはないでしょうが、昨今の減少傾向に歯止めが掛からなければ、税理士試験自体が破綻する可能性すらあるといえるでしょう。
受験者数が減少し続ける理由
そもそも、なぜ税理士試験の受験者数は年々減少しているのでしょうか。考えられる最も大きな理由として、「仕事として税理士を選ぶことへの不安」が挙げられるでしょう。
日本における多くの産業では、この先数十年にわたるスパンの中で、AIに代替できる業務が激増するといわれています。税理士の業務も例外ではないとされ、実際にAIへと業務が移行するかどうかは別問題として、そのようにいわれていること自体が税理士を目指す人たちに与える影響は小さくないことが想像できます。
税理士試験は基本的に一朝一夕で合格するものではなく、まともに取り組んでも3~5年、本業の合間に勉強しながら臨む場合は5~10年要する可能性が高い、難しい試験です。努力をしても、必要とされないかもしれない職業となれば、目指す人が減るのは当然のことでしょう。
また、税理士試験の受験者数が減少している理由には、税理士事務所の給料や労働条件が良くないというイメージが強いことも挙げられます。
実際には税理士事務所によりさまざまな状況であるといえ、税理士に対するこのようなマイナスイメージが、最近はインターネットで簡単に見られるようになったことも、原因の一つとして挙げられるでしょう。
税理士試験に合格した人たちが発信する、その後の状況に関する生の声を多く拾うことで、悲観的な意見が印象深く残ってしまうこともやむなしといえます。
業界での税理士不足が進み若手にはチャンス
税理士試験の受験申込者数は減少傾向にあるものの、実際にはある段階から回復することが予想されます。
日本税理士会連合会によると、最新の調査結果である「平成26年度第6回税理士実態調査報告書」において、税理士登録をしている人の中では60代以上が50%を超えており、業界全体が高齢化の傾向にあるといえます。60代以上の税理士はいずれ引退することになるため、向こう10~20年の間に業界内で人材不足が顕在化してくるでしょう。
これまでも慢性的に税理士が不足していることはしばしば議論の対象となっていましたが、税理士試験の受験申込者数が減少していることを良い機会とし、本格的な議論が開始されるのも時間の問題だといえそうです。
また、「平成26年度第6回税理士実態調査報告書」によると、20~30代の税理士は全体の11%にも満たない状況であり、これらのことを総合的に考慮すれば、若手の税理士は今後ますます貴重な存在として見られる可能性が高いといえます。
若い税理士が活躍の場を広げることで、これから税理士を目指す人にもメリットが生まれ、税理士試験の受験申込者数が回復することは、十分に考えられるでしょう。
まとめ
税理士試験の受験申込者数は年々減少傾向にあり、このままでは試験自体が存続の危機に直面するようなペースです。ただ、業界の高齢化に伴い若手の税理士に顧客や主導権が移れば、税理士試験の受験申込者数も回復することが予想されます。
今後の受験申込者数の推移や業界全体の動向にアンテナを張りつつ、社会全体の動きにも常に関心を持ちながら過ごすことが重要です。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
新着動画
関連情報
-
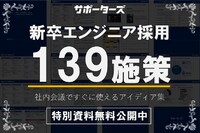
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖
おすすめ資料 -

「人事給与アウトソーシング(BPO)サービス」導⼊事例集【三菱総研DCS】
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -
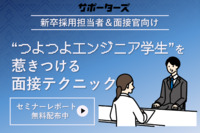
【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!
おすすめ資料 -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!
ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正
ニュース -

提供元表示テスト
ニュース -

もっと見るリンク先:テスト
ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
ニュース -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -
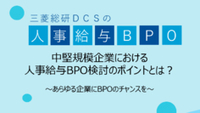
人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)
おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!
おすすめ資料 -

1月9日公開記事
ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
ニュース -

経理は転職サイトを利用すべき?経理人材の転職市場での価値を解説!
ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に
ニュース